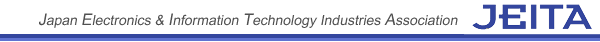
平成26年12月18日 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」に関する コメントについて 一般社団法人 電子情報技術産業協会 ソリューションサービス事業委員会 ITサービス調達政策専門委員会 2014 年12 月3 日に、総務省から「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」が公開されました。新ガイドラインは、原則、全ての政府情報システムを対象にライフサイクル全般(企画〜調達〜運用〜廃棄)に関する発注者側の手続き及び管理の共通ルールを定めているものです。 JEITA IT サービス調達政策専門委員会(委員長:富士通 寺田透)では、2006 年度以来、政府情報システムの信頼性や安定的な運用の確保、発注者及び受注者の双方に有益な政府情報システム調達制度改革の実現という観点から、関係府省に対して提言活動を実施しています。新ガイドラインに関しても、同省が2014 年8 月21 日から9 月3 日の期間で実施した意見公募に対して、JEITA 法務・知的財産権委員会政府委託・調達契約に係る権利帰属に関するタスクフォース( 主査: 富士通 西田雅俊) と共に意見を取りまとめ、(一社)情報サービス産業協会殿と共同で22 件の意見を提出しています。 本専門委員会では、今回の新ガイドラインに関して、主に下記3 点を前向きに評価しています。 1 点目は、これまで「政府情報システムに係る政府調達の基本指針」に基づいて推進されてきた分離調達について、設計・開発工程における過度な分離調達が抑制される等、一定の見直しが図られている点です。従来の「分離調達ありき」の方針から合理的な調達単位を発注者側で検討するという方針に変更されており、情報システム調達におけるリスク低減の観点から評価できると考えています。 2 点目は、契約方式の検討において、例外的に随意契約を選択する際の手順が明確化された点です。これまでは、一般競争入札の原則が強調されるあまり、一者応札の蓋然性が高い場合であっても入札が実施され、結果として発注者及び受注者双方に無用なコストを発生させていました。新ガイドラインにおいて、随意契約によらざるを得ない場合には、企画競争や公募等で透明性や競争性を担保することという方向性が明示された点は、大きな改善であると評価しています。 3 点目は、新規事業者の参入機会拡大等の観点から、産業界が改善を提言していた契約書の記載事項について、一定の改善が図られた点です。具体的には、損害賠償限度額と成果物の知的財産権の取扱いに関するものです。新ガイドラインでは、損害賠償については「契約書への損害賠償範囲の限度の記載をすること」が、成果物の知的財産権の取扱いについては「成果物の知財権は一般的には受注者側に帰属、発注者に帰属する場合は、契約書に例外的にその旨を記載する」等が謳われており、一部に解釈をめぐる運用上の懸念はあるものの、発注者及び受注者双方に有益な調達制度改革に繋がる改善の方向性が示されています。 なお、新ガイドラインの実際の運用に向けた詳細事項は、今後、内閣官房及び総務省が作成する「実務手引書」にて定められると理解しています。本専門委員会としては、今回の制度改善を有効に実行するためにも、発注者側だけでなく受注者側の意見も踏まえた形で実務手引書の記載内容の充実を図っていくことが非常に重要だと考えています。特に、2009 年にJEITA が意見表明(※)を行った「政府調達における再委託先情報の開示」に関しては、この実務手引書作成の過程で開示内容の見直しを図るべきだと考えます。また、上記の成果物の知的財産権の取扱いについても、「国の業務に特化した汎用性のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるもの」の記載の解釈により、事実上、上記の「成果物の知財権は一般的には受注者側に帰属」するという原則が形骸化しないよう運用されるべきだと考えます。 本専門委員会では、関連他団体とも連携の上、政府情報システムの信頼性の向上と発注者及び受注者双方に有益な調達制度改革の実現に向けて、引き続き積極的に貢献していきたいと考えています。 以上 (※)政府調達における再委託先情報の開示に関する意見(2009 年12 月)http://home.jeita.or.jp/is/committee/solution/091221/ ◆「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」に関するコメント同内容PDF版(PDF110KB)◆ |
