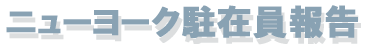
【 2002年11月号 】
~ 米国におけるITSの動向(その1) ~
JEITAニューヨーク駐在員 (JETROニューヨーク事務所) 荒 田 良 平
|
はじめに
今月と来月は、米国におけるITS(Intelligent Transportation Systems)の動向について取り上げる。
ITは我々の日常生活を取り巻く様々な分野において利用され、経済社会に大きな変革をもたらしているが、そのうち交通、運輸等の分野におけるIT利用がITSである。一般的にITSに関しては日本と欧州が先行しており、米国のITSは遅れを取っていると言われてきたが、米国においてもITブームの中にあって、またドットコム・バブル崩壊後もしばらくは、IT業界にとって残された巨大市場としてITS(特にテレマティックス)に期待が集まっていた。
しかし、去る10月14~17日にシカゴで開催された「ITS World Congress 2002」を見た限り、参加者は2~3年前に比べて2/3程度まで減っているのではないかと思われ、テレマティックスに対する熱も冷めてきたことを感じざるを得なかった。
本稿では、まず今月、連邦政府による取組みなど米国におけるITSの全体的な動向について概観し、来月はテレマティックスの動向などについて取り上げることとする。
1.ITS(Intelligent Transportation Systems)とは
(1) ITSの定義
いつものように、まず定義から始めたい。
ITSとは、Intelligent Transportation Systems(欧州や日本ではIntelligent Transport Systems)の略であり、直訳すると「知的運輸システム」ということになる。日本では経緯上「高度道路交通システム」と、道路交通に焦点を当てた言葉が用いられているが、ITSは実際には鉄道や歩行者も含めた幅広い概念である。(陸上交通を指すのが基本であるが、場合によっては空路や海路までも含めた意味で用いることがある。)
ITSは幅広い概念であるが故に、逆に定義があいまいである点は否定できないのであるが、これもITSの特徴の一つであり、ITSの可能性の大きさを表していると理解すべきであろう。
参考までに、ITS関連の産学官による協議体Intelligent Transportation Association of America(ITS America)(http://www.itsa.org/)と連邦運輸省(DOT)のホームページから、「What is ITS?」の部分を図表1に書き出しておく。
図表1 What is ITS?
 (出展: ITS America及び連邦運輸省のホームページ)
(出展: ITS America及び連邦運輸省のホームページ)
(2) ITSの利用者サービス
さて、さすがにこの定義らしきものだけでは何が何だかわからないので、ITSの具体的な分類について見てみよう。
米国におけるITSの全体像については、日本や欧州と同様、「システム・アーキテクチャ」と呼ばれるITSの全体設計図に規定されている。
米国版のシステム・アーキテクチャ「The National ITS Architecture」は、初版が1996年に連邦運輸省(DOT)によって策定されて以来、改定が重ねられてきており、最新のVersion 4.0においては、図表2のように8分野で計32の利用者サービスが設定されている。
図表2 米国のITSにおける8分野32の利用者サービス
1 旅行・交通管理(Travel and Traffic Management)
1.1 旅行前の交通情報(Pre Trip Travel Information)
1.2 運転中のドライバーへの情報(En Route Driver Information)
1.3 経路誘導(Route Guidance)
1.4 搭乗調整・予約(Ride Matching and Reservation)
1.5 旅行者サービス情報(Traveler Services Information)
1.6 交通制御(Traffic Control)
1.7 交通事故管理(Incident Management)
1.8 交通需要管理(Travel Demand Management)
1.9 排気ガス試験・削減(Emissions Testing and Mitigation)
1.10高速道路と鉄道の交差(Highway Rail Intersection)
|
2 公共交通管理(Public Transportation Management)
2.1 公共交通管理(Public Transportation Management)
2.2 旅行中の公共交通情報(En Route Transit Information)
2.3 個人の公共交通乗換え(Personalized Public Transit)
2.4 公共交通の安全(Public Travel Security)
|
3 自動料金支払い(Electronic Payment)
3.1 自動料金収受サービス(Electronic Payment Services)
|
4 商用車両管理(Commercial Vehicle Operations)
4.1 商用車両の電子式許可(Commercial Vehicle Electronic Clearance)
4.2 路側での自動安全検査(Automated Roadside Safety Inspection)
4.3 車載安全モニタ(On-board Safety Monitoring)
4.4 商用車両の行政手続き(Commercial Vehicle Administrative Processes)
4.5 危険物事故への対応(Hazardous Material Incident Response)
4.6 貨物輸送管理(Commercial Fleet Management)
|
5 緊急事態管理(Emergency Management)
5.1 緊急事態の通知と個人の安全(Emergency Notification and Personal Safety)
5.2 緊急車両管理(Emergency Vehicle Management)
|
6 高度車両安全システム(Advanced Vehicle Safety Systems)
6.1 前後の衝突防止(Longitudinal Collision Avoidance)
6.2 左右の衝突防止(Lateral Collision Avoidance)
6.3 交差点での衝突防止(Intersection Collision Avoidance)
6.4 衝突防止のための視認性の向上(Vision Enhancement for Crash Avoidance)
6.5 危険状況の予知(Safety Readiness)
6.6 衝突前の拘束手段(Pre-crash Restraint Deployment)
6.7 自動車両運行(Automated Vehicle Operation)
|
7 情報管理(Information Management)
7.1 保管データの機能(Archived Data Function)
|
8 保守・建設管理(Maintenance And Construction Management)
8.1 保守・建設の運用(Maintenance And Construction Operations)
|
(出展: "The National ITS Architecture Ver.4.0"より作成)
参考までに、1999年にITS関係5省庁(現4省庁)によって策定された日本版のシステム・アーキテクチャにおける利用者サービスについて、図表3に掲げておく。
図表3 日本のITSにおける9つの開発分野と21の利用者サービス
1 ナビゲーションシステムの高度化
1) 交通関連情報の提供
2) 目的地情報の提供
|
2 自動料金収受システム
3) 自動料金収受
|
3 安全運転の支援
4) 走行環境情報の提供
5) 危険警告
6) 運転補助
7) 自動運転
|
4 交通管理の最適化
8) 交通流の最適化
9) 交通事故時の交通規制情報の提供
|
5 道路管理の効率化
10) 維持管理業務の効率化
11) 特殊車両等の管理
12) 通行規制情報の提供
|
6 公共交通の支援
13) 公共交通利用情報の提供
14) 公共交通の運行・運行管理支援
|
7 商用車の効率化
15) 商用車の運行管理支援
16) 商用車の連続自動運転
|
8 歩行者等の支援
17) 経路案内
18) 危険防止
|
9 緊急車両の運行支援
19) 緊急時自動通報
20) 緊急車両経路誘導・救援活動支援
21) 高度情報通信社会関連情報の利用
|
(出展: 「高度道路交通システム(ITS)に係るシステムアーキテクチャ」より作成)
米国版と日本版では、括り方や細かさ、順番等が異なっているが、実際にはシステム・アーキテクチャにはさらに細分化された区分があり、そこまで見ると日米の違いはそれ程大きくはない。しかし、例えば日本版の利用者サービスでは「歩行者等の支援」や「高度情報通信社会関連情報の利用」が大きく取り扱われており、一方で米国版では「商用車両管理」で電子式許可等が規定されているなど、両国の交通事情等の相違が反映されたものとなっている。(例えば米国の幹線高速道路(インターステート)では、大型トラック等の過積載を抜き打ちで取り締まるため州境付近などに計量所(weigh station)が設けられているが、計量の順番を待つトラックの列がしばしば渋滞を引き起こすため、その効率化が課題となっている。)
2.米国連邦政府によるITSの推進
(1) 米国連邦政府におけるITSの推進体制及び予算
ここで、米国におけるITSの推進体制と連邦政府のITS関連予算について簡単に見ておくこととしたい。
米国におけるITSの展開は、陸上交通網整備に関する中期計画である1991年の「Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991」(1991年総合陸上輸送効率化法:ISTEA)及びその後継法である1998年の「Transportation Equity Act for the 21st Century」(21世紀交通最適化法:TEA-21)によって確保されたITS関連の研究開発、実配備等のための予算を活用しながら、各州・地方政府等によって構築されるシステム間の相互運用性に配慮しつつ進められている。この際、図表4に示すように、連邦運輸省(DOT)が中心的役割を担っており、連邦道路局(FHWA)、連邦道路交通安全局(NHTSA)、連邦公共交通局(FTA)、連邦鉄道局(FRA)等の関係機関によるITSジョイント・プログラム・オフィス(JPO)を設けて、関係機関の連携の下に研究開発、試験、実配備等を行っている。
また、連邦・州・地方政府関係機関、民間企業、団体、大学等による協議体でDOTの公式諮問機関であるITS America(http://www.itsa.org/)が、技術開発や標準化に関するビジョンの提言等を行っている。
図表4 米国におけるITSの推進体制
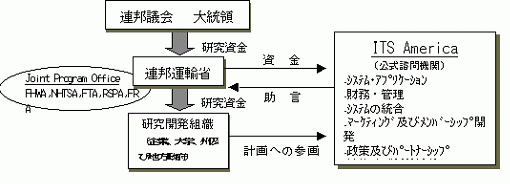
(出展: 電気通信審議会「高度道路交通システム(ITS)における情報通信システムの在り方」)
図表5 TEA-21におけるITS関連予算(百万ドル)
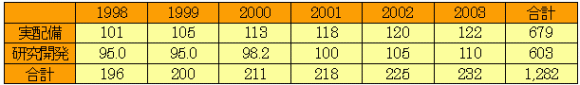
(注)毎年の予算上の制約により、実際の予算額はこれらを下回ることがある。
(出展: DOT)
なお、現行のTEA-21は2003年までの計画であるため、関係者は既にその後継法となる陸上交通網整備に関する第三次の法律(現時点では「TEA-3」と呼ばれている)の準備を始めている。その状況は、DOT(http://www.fhwa.dot.gov///////reauthorization/index.htm)やtea3.org(http://www.tea3.org/)などのウェブサイトで見ることが出来る。
(2) ITS推進計画
次に、米国におけるITSの推進計画について見てみよう。現行のマスタープランである上述のTEA-21に基づいて、DOTとITS Americaは図表6のようにITS推進計画として3種類のITS推進計画を策定している。
図表6 TEA-21の下でのITS推進計画
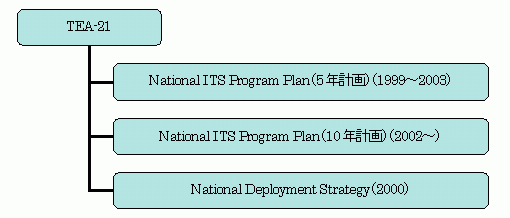
(出展: DOT「National ITS Program Plan: Five-Year Horizon」より作成)
これらのうち、まず当初の5年計画である「National ITS Program Plan: Five-Year Horizon」(http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/jpodocs/repts_pr/97r01!.pdf)では、図表7に示すように4つの計画分野を設定しそれぞれの目標を示すとともに、それらを実現するための戦略を8つの戦略分野に沿って規定している。
図表7 5年計画の概要
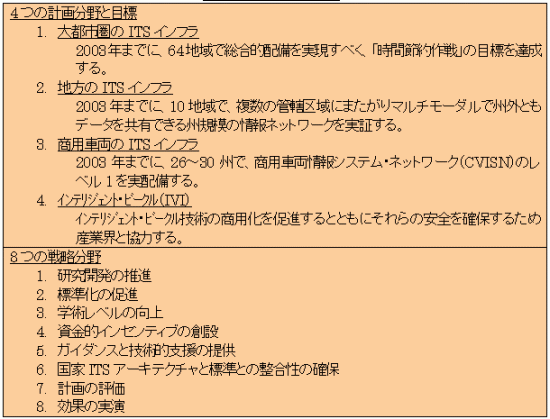
(出展: DOT「National ITS Program Plan: Five-Year Horizon」より作成)
次に、実配備戦略National Deployment Strategyとして2000年2月に取りまとめられた「Saving Lives, Time and Money Using ITS: Opportunities and Actions for Deployment」(http://www.itsa.org/subject.nsf/urls/nitsds.html)では、図表8に示すように「2005年までに人や貨物の輸送のための基本的なITSサービスの全米での実配備を完了する」ことを目標として掲げ、実際の事例を紹介するとともに、14の協力分野について20の関係者が取るべき行動について提言を行っている。
図表8 National Deployment Strategyの概要
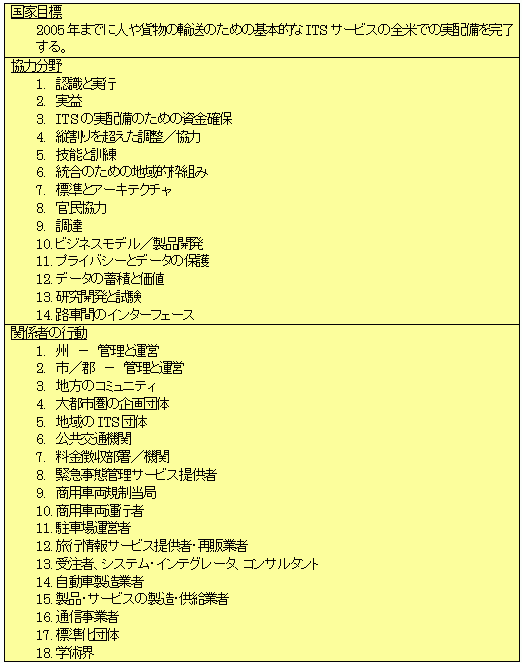
(出展: ITS America「Saving Lives, Time and Money Using ITS: Opportunities and Actions for Deployment」より作成)
また、2002年1月に取りまとめられた「National ITS Program Plan: A Ten-Year Vision」(http://www.itsa.org/resources.nsf/Files/PPRA_Full_Final/$file/PPRA_Full_Final.pdf)と題する10年計画では、図表9に示すように、将来の運輸システムに関するビジョンと具体的な目標を設定した上で、4つの計画上の課題とそれを実現するための4つの課題を上げ、それぞれについて、現状、課題が解決された場合の利益、そのための課題、関係者の取るべき行動について記述している。
図表9 10年計画の概要
ビジョン
- 将来の運輸システムは、年齢、運動能力、場所によらず継ぎ目のないエンド・ツー・エンドのインターモーダルな人の移動と、効率的で継ぎ目のないエンド・ツー・エンドのインターモーダルな貨物の移動を実現すべく管理運用される。
- 政策決定者と民間の意思決定者は、21世紀の運輸システムのビジョンを達成するために不可欠なものとしてITSを活用する
- 将来の運輸システムは、コンピューティング、通信及びセンサ技術から総合的に得られる情報によって、安全で、利用者中心の、成果を重視した、制度上も革新的なものとなる。
|
目標
- 安全2011年までに運輸関連の死亡者数を15%減らし、年間5,000~7,000人の命を救う。
- セキュリティ運輸システムを攻撃から守られ、自然や人的な脅威や災害に効果的に対応できるものにすることによって、有事においても人や物資の移動を可能とする。
- 効率/経済性より良い情報、より良いシステム管理、及び、迅速で継ぎ目のないインターモーダルな公共交通を含む効率的でエンド・ツー・エンドの人と物資の移動の実現による渋滞の抑制により流量と容量を増大させることによって、少なくとも年間200億ドルを節約する。
- 移動度/アクセス運輸システムの利用者が継ぎ目のないエンド・ツー・エンドの移動手段を選択できるように、どこでも情報が得られるようにする。
- エネルギー/環境少なくとも年間10億ガロンのガソリンを節約し、少なくともこれに比例する排ガスを削減する。
|
計画上の課題
- 運輸情報の総合ネットワーク人の継ぎ目のない移動貨物の継ぎ目のない移動気象状況による影響緊急事態と危機への対応総合ネットワークの構築
- 先進的衝突防止技術車載エレクトロニクス、路車間協調、インフラ技術運転者の資質自動取締り
- 自動的な衝突・事故の検知・通報・対応
- 先進的運輸管理先進的運輸管理システム先進的自動運輸システム
|
実現のための課題
- 運輸システムの管理運用の文化
- 公的部門の役割、関係、資金確保
- 民間部門の製品開発促進のための連邦政府の政策・インセンティブ
- 人的要素
|
(出展: ITS America「National ITS Program Plan: A Ten-Year Vision」より作成)
さらに、ITS Americaは2001年9月11日のテロ事件を受けて、2002年9月に上記の10年計画への補足追加という形で、図表10に示すように「Homeland Security and ITS」(http://www.itsa.org/resources.nsf/Files/PPRA_Security_Final/$file/PPRA_Security_Final.pdf)というビジョンを発表している。これは、具体的には10年計画における「計画上の課題」に5番目の課題として「国土安全保障」を追加するとともに、ITSは国土安全保障のためどのような貢献ができるかを整理したものである。
図表10 「Homeland Security and ITS」の概要
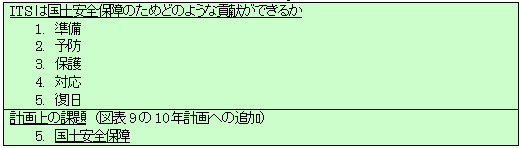
(出展: ITS America「Homeland Security and ITS」より作成)
以上、長々と米国におけるITS推進計画について見てきたが、概括すると、米国ではTEA-21体系下で、それまでのビジョン策定やシステム・アーキテクチャの構築から、より実配備に重点が置かれるようになってきており、こうした中で、多様な関係者間の役割分担と連携が重要な課題になっている。
また、テロ事件を受けて、運輸システムのセキュリティ確保が一層重視されるようになっている一方で、エネルギー/環境という視点は日欧に比べ希薄であると言うことができよう。
3.ニューヨークにおけるITS
政府の計画を見てもITSの具体的な進捗状況はわかりづらいので、次に、実際にニューヨークにおいてITSがどの程度実用化されているのかについて見てみよう。
(1) ニューヨーク州におけるITSの概要
連邦運輸省(DOT)のウェブサイト(http://www.its.dot.gov/staterpt/state.htm)には、州毎のITSの推進状況が掲載されている。ここから、2001年11月時点でのニューヨーク州におけるITSの推進状況について図表11にまとめておく。
図表11 ニューヨーク州におけるITSの推進状況(2001年11月現在)
先進的交通管理システム
- CCTV(監視用テレビカメラ)のプライバシー・ポリシーの策定
- 有料道路を巡回し通行者を支援する「HELP Program」
- 5箇所の交通管理センターを運営
- ニューヨーク/ニュージャージー/コネチカット地域の16機関が協力して交通事故への対応を改善するためのコンソーシアム「TRANSCOM」を形成
- 州都オルバニー地域で州運輸局と州警察が共同で運輸管理センターの設置などの州都地域ITS計画を推進
- ニューヨーク大都市圏でニューヨーク/ニュージャージー/コネチカットの3州の協力により「実配備モデル計画(Model Deployment Initiative)」を推進
- 州運輸局は1.5億ドル以上をかけて7地域で先進的交通管理システム構築のための5年計画を推進
- 様々なメッセージ表示システムなどを含む「INFORM project」を実施中
- 州南部自動車専用道路への装備を導入
- バージニア州からメイン州までの高速道路(インターステート95)の交通改善のため連合体「I-95 Corridor Coalition」を形成
- ニューヨーク市のブロンクス/北部マンハッタン地区で先進的交通管理システムを導入
- ニューヨーク/ニュージャージー港湾管理局はニューアーク、JFK両空港周辺の様々な交通管理システムをリンク
|
関連活動
- 州規模/地域のアーキテクチャの策定
- 州運輸局は2000年春に道路気象情報システムの構築に着手
- 州運輸局は先進的交通管理システムの構築を検討する際のガイドラインとなる「ITS Scoping Procedures」を策定中
- Calspan-バッファロー大学研究センター(CUBRC)がITSオプション分析モデルを開発
- 無休運用(24/7 Operations)に向けた戦略を策定
|
先進的公共交通
- ナイアガラ運輸局は350台のバスでGPS自動車両位置システムを運用
- ロチェスター地域公共交通局は次に来るバスの情報を自動車両位置システムで提供
- 州都地域でバスに「Swipers」と呼ばれる電子式料金カードを導入
- ウェストチェスター郡で公共交通に関する勤務時間外の自動音声応答システムなどを計画
- ニューヨーク市及びロングアイランドでは経路計画・料金・スケジュール情報の自動提供システムなどを実証・運用中
|
商用車両運行
- ニューヨーク州はワシントン地区にかけての7州と共同で商用車両運行におけるIT利用に関する様々な制度的課題をとりまとめ
- ニューヨーク州バッファローとカナダのオンタリオ州フォート・エリーを結ぶPeace BridgeにおいてDSRC(狭域無線通信)を活用した自動国境通行システムを設計中
|
自動料金徴収
- 4州にまたがる7つの料金徴収機関が共通の料金徴収システムE-Zpassを導入し250万人が利用
- E-Zpassはバッファローとフォート・エリーを結ぶPeace Bridgeでも運用予定
|
衝突通報
- CalspanのITSプログラムで自動衝突通報システムの機能を実証中
|
ITS企画立案
- バッファロー/ナイアガラ、ロチェスター、オルバニー、ハドソン川流域南部、ニューヨーク市、ロングアイランドで連邦資金を活用したITS企画立案を完了しシラキュースで実施中
- ナイアガラ地域国際運輸技術連合で国境をまたぐITSを推進
|
ITS実配備
- ロチェスター、バッファロー、シラキュースで交通管理センターの建設、様々なメッセージ表示盤、高速道路ラジオ、CCTV(監視用テレビカメラ)の設置、通信用光ファイバの敷設などを実施
- バージニア州からメイン州までの高速道路(インターステート95)の交通改善のための連合体「I-95 Corridor Coalition」で様々なITSサービスの試験・評価を実施
|
その他の活動
- Tappan Zee Bridge/Cross Westchester CorridorでCCTV(監視用テレビカメラ)やTRANSMITなどの先進的交通管理システムを順次導入
- 電子式料金・交通管理技術を用いて交通管理と料金所の運用管理を行うTRANSMITの活用を強力に推進
- ウェストチェスター郡はニューヨーク市と提携して交通情報センターを設置
|
(出展: 連邦運輸省(DOT)のウェブサイトより作成)
Tappan Zee Bridgeなどニューヨーク在住者でなければわからないようなローカルな話も混じっていて恐縮であるが、この図表11を眺めてみると、米国でITSに対するニーズが最も高い地域の一つであると思われるニューヨークでも、実際に導入されているシステムは、失礼ながら「たいしたことはない」と言えるであろう。交通管理システムの構築・ネットワーク化が進んできてはいるものの、いずこも同じで関係者間の連携に苦心している様子が窺われる。
こうした中で、ニューヨーク州における取組みの中から興味深い点を挙げるとすれば、CCTV(監視用テレビカメラ)のプライバシー・ポリシーの策定(日本ではどうなっているのでしょうか?)、自動料金徴収システムE-Zpassの普及(日本のETCにも期待しているのですが)、Peace BridgeにおけるDSRC(狭域無線通信)を活用した自動国境通行システム(テロ事件後の国土安全保障強化の観点から注目される)などであろうか。
ITSに関わるプライバシー問題については、米国では論争の種となっており、例えばつい先日容疑者が逮捕されたワシントンDC近郊での連続狙撃事件でも、路上に設置されたカメラが不審な白いワゴン車を探すために利用されたのではないかなどと報じられ、犯罪解決を評価する声とともに、プライバシー問題を懸念する声も上がっている。(日本でもオウム真理教事件の際に同様のことがあったと記憶している。)
また、E-Zpass(http://www.e-zpassny.com/)については、日本のETC車載器が能動型で双方向通信によりリアルタイムでのクレジット決済などが可能なシステムであるのに対し、E-Zpass車載器は受動型で非常に簡単なシステムである。このため、E-Zpass車載器は無料で配布されており、通行料は自分のアカウントに入れてあるデポジットから自動的に引き落とされ、クレジットカードを登録しておけばデポジットが少なくなるとそこから自動的に補充されるといった仕組みになっている。実際にE-Zpassを使えば料金が割引になるし、料金所混雑時の所要時間もかなり差が出るので、広く普及しているのも頷ける。ビジネスモデルとしても良くできたシステムであると言えるであろう。
ただし、日本との比較で言うと、こちらの有料道路の料金は通常50セント~1ドル程度、長距離走ったとしてもせいぜい数ドルというところであり、日本とは1ケタ異なる。日本のように少し走ると数千円かかるとすれば、E-Zpassのようなデポジットからの引き落としというわけにもいかないだろうし、捕捉率も高くなければならず(E-Zpassではたまに動作しないことがある)、したがって日本のETCが技術的に高度な(価格も高い)システムになってしまうのも致し方ない面もある。要するに、日米の有料道路のあり方自体が大きく異なるので、そこで利用される自動料金徴収システムについても単純な比較はできないということである。
(2) ニューヨーク大都市圏におけるITS実配備モデル計画(Model Deployment Initiative)
上記の図表11の中にも出てくるが、ニューヨーク/ニュージャージー/コネチカット3州にまたがるニューヨーク大都市圏において推進されているITS実配備モデル計画(Model Deployment Initiative)について触れておきたい。
これは、連邦運輸省(DOT)による大都市圏におけるITS実配備のモデル・プロジェクトとしてテキサス州サンアントニオ、ワシントン州シアトル、アリゾナ州フェニックスとともに選定されたものであり、ニューヨーク/ニュージャージー/コネチカット地域の16機関が協力して交通事故への対応を改善するために形成したコンソーシアム「TRANSCOM」(http://www.xcm.org/)によって推進されている。
さて、その進捗状況であるが、他の3プロジェクトがとっくに実証・評価を終わっているのに対して、このニューヨーク大都市圏のプロジェクトは延び延びになっているようだ。当初このニューヨークのプロジェクトは「iTravel」と呼ばれていたが、どうも途中で商標権が他社に抑えられていることが判明したといった理由で名称変更を余儀なくされ、現在は「Trips123」と呼ばれているようである。(お粗末!) TRANSCOMのウェブサイト上の情報や上述の連邦運輸省(DOT)のウェブサイト(http://www.its.dot.gov/staterpt/state.htm)に掲載されているニューヨーク州のITSの推進状況に関する記述によると、この「Trips123」プロジェクトは①マルチモーダルな旅行情報システムを電話またはインターネットで無料提供、②旅行前に公共交通の利用計画を作れるツールを運輸情報センターがインターネットで無料提供、③利用者サービスセンターが契約者が事前指定した経路に関する事故情報などを電話、FAX、電子メール、ページャーに送信するサービスを有料で提供、という3本柱からなるようで、2002年の早い時期に運用開始となっている。しかし、2002年10月時点で「Trips123」のウェブサイト(http://www.trips123.com/)はまだ建設中という状態である。
(3) ニューヨークにおける道路交通情報提供サービス
ついでに、ニューヨークにおける道路交通情報提供サービスについても触れておこう。
ニューヨーク市近郊は、高速道路が網の目のように張り巡らされているうえ、橋やトンネルにもいくつかの選択肢があり、渋滞も激しいということで、リアルタイムでの道路交通情報に対するニーズは高いと思われる。しかし、意外にもニューヨークでは、ラジオ等での通常の放送はあるものの、東京の感覚で考えて「まともな」道路交通情報提供サービスは無いと言って良いであろう。(驚くべきことに、地元ケーブルテレビ局「NY1」(http://www.ny1.com/)で毎朝放送されている道路交通情報でさえも、具体的な渋滞状況はまったくわからずお寒い限りであると言わざるを得ない。)
図表12 地元ケーブルテレビ局での道路交通情報
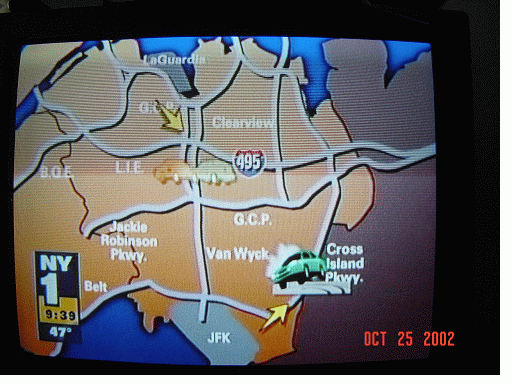
(出展: NY1)
ニューヨークにおけるインターネットでの道路交通情報提供サービスとしては、ニューヨーク市運輸局(http://www.ci.nyc.ny.us/html/dot/home.html)による交通状況のカメラ映像のリアルタイム配信(図表13)や、traffic.com(http://www.traffic.com/)やmetrocommute.com(http://www.metrocommute.com/)といった民間事業者サイトによる事故、工事、渋滞等の情報配信があるが、きめ細かさにおいて日本の道路交通情報提供サービスとは比べ物にならない。
この原因はいくつか考えられるが、やはり資金負担の問題は大きいのではないかと思われる。上述の「Trips123」にしても、そのランニングコストを公的部門がどこまで負担すべきかが議論になっているようであるが、アメリカ人は日本人以上に(?)ケチなので、道路交通情報提供の対価負担を受益者である利用者に求めるビジネスモデルが米国で成立するとは思えない。だからといって公的部門が丸抱えで行うことに対しては、やはり批判的な声もあり、あり得べきモデルを求めて模索が続いているというのが実態ではなかろうか。
図表13 マンハッタンにおける交通状況監視カメラの設置状況
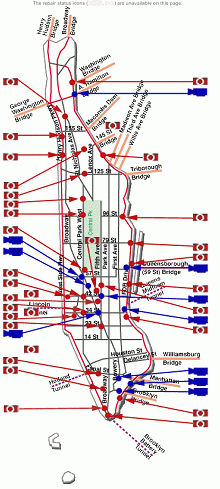
(出展: ニューヨーク市運輸局ウェブサイト)
(続く)
(参照URL)
http://www.itsa.org/whatits.html(図表1関連)
http://www.its.dot.gov/faqs.htm#What%20is%20ITS? (図表1関連)
http://itsarch.iteris.com/itsarch/(図表2関連)
http://www.vertis.or.jp/ISODB/archi/J-SA/pdf/main.pdf(図表3関連)
http://www.itsforum.gr.jp/Public/J7Database/P02/P0202/P0202.html#Chapter1_3(図表4関連)
http://www.its.dot.gov/tea21/tea21bro.pdf(図表5関連)
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/jpodocs/repts_pr/97r01!.pdf(図表6、7関連)
http://www.itsa.org/subject.nsf/Files/Opportunities+and+Actions+Final+report+030300/$file/Opportunities+and+Actions+Final+report+030300.pdf(図表8関連)
http://www.itsa.org/resources.nsf/Files/PPRA_Full_Final/$file/PPRA_Full_Final.pdf(図表9関連)
http://www.itsa.org/resources.nsf/Files/PPRA_Security_Final/$file/PPRA_Security_Final.pdf(図表10関連)
http://www.its.dot.gov/staterpt/NY.HTM(図表11関連)
http://nyctmc.org/xmanhattan.asp(図表13関連)
本稿に対する御質問、御意見、御要望がございましたら、Ryohei_Arata@jetro.go.jpまでお願いします。
(C)Copyright JEITA,2002
|