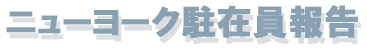
【 2001年10月号 】
〜 米国テロ事件に見るITシステムを巡る論点 〜
JEITAニューヨーク駐在 荒 田 良 平
|
はじめに
去る9月11日に発生したテロ事件によって被害に遭われた皆様方に、心よりお悔やみ、お見舞いを申し上げます。また、テロ事件によって事業活動に大きな影響を被っていらっしゃる皆様方が、この危機を乗り越えられることをお祈りいたします。
今月の駐在員報告では、9月11日に発生したテロ事件について触れることとする。ただし、本稿を書いている9月14日現在では、テロ事件の全容解明や米国経済・産業等に与える影響の詳細な分析はこれからという状況である。そこで本稿では、9月14日時点で行なわれている様々な報道等をもとに、今回のテロ事件を踏まえITシステムに関して浮かび上がってきた論点の整理を試みる。
1.IT関連企業の危機管理
今回のテロ事件では、世界貿易センター北館(1WTC)の101階から105階までに入居していた米国債の電子商取引プラットフォームeSpeedシステムのベンダーCantor Fitzgerald社が、同オフィスに勤務していた従業員1,000名の大部分を失ったという。また、ボストンのインターネット・インフラ企業Akamai Technologies社の共同創設者・最高技術責任者(CTO)であるDaniel Lewin氏がハイジャック機に搭乗していて亡くなったのをはじめ、いくつかのIT関連企業が幹部や従業員を失った。
また、こうした直接的な被害の他にも、多くのIT関連企業が、空港や港湾の閉鎖に伴い一時的に電子部品や製品の搬送が困難になるなどの影響を被ったと言われる。
今回のテロ事件のような不測の事態の場合、こうした直接的・間接的影響は避けようがないが、政府や企業はその影響を少しでも緩和すべく危機管理プログラムを構築している。今回の事件は改めてその有効性を検証する機会となるだろう。
こうした政府・企業の一般的な危機管理の問題のほか、今回のテロ事件ではITシステムに関し以下のような様々な論点が浮かび上がってきている。
JETRO New Yorkから崩壊した世界貿易センター方面を望む

(JETRO New York職員が9月11日午後に撮影)
(注) JETRO New Yorkの場所は、マンハッタンのAvenue of the Americas(6番街)&48丁目にあるビルの42階。世界貿易センターからの距離は7km程度。
2.ITシステムの危機管理
(1) テロ事件の被害に遭った世界貿易センター(WTC)や国防総省(ペンタゴン)には、米国のインターネット・インフラを形成するノードやバックボーンの設備が設置されていたわけではなく、事件後もインターネット・インフラへの影響は報告されていない。(インターネットの原型となったARPANETがこうした有事に強い分散ネットワークとして発案されたことを考えれば、事件後もインターネットが機能したのは当然と言えるかもしれないが。)
(2) しかし、局所的に見れば、WTC内及びその隣接地区には地域電話会社Verizonを始めとする通信キャリアが回線設備やワイヤレス基地局を設置していたため、これらの設備の破損や電源供給停止によって、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の通信回線を含めマンハッタン南部の通信回線が不通になった。
また、WTC隣接地区にはKDDIの子会社テレハウス・アメリカの企業向け通信サービス設備があり、その電源供給停止・自家発電設備のオーバーヒートによって、日系企業の国際専用線等が停止するという影響が生じた。(この影響で9月14日現在、JETRO New Yorkのインターネット接続や電子メール利用もできなくなったままである。同僚からは"インターネットが使えないと仕事にならない"という声があがっており、日頃いかにインターネットに依存して仕事をしているか思い知らされた。)
通信設備の直接的な破損を別にすれば、ITネットワークにとって電源供給の問題は最重要事項の一つである。電源供給は、設備破損という直接的原因のみならず、ガス爆発の懸念といった間接的理由からも停止を余儀なくされる。したがって、こうした場合企業レベルのみならず地域レベルでの危機管理も重要となろう。
(3) WTCはウォール街から数百メートルの場所に位置し、銀行や証券会社が多数入居していた。こうした企業はITシステム上の膨大なデータを保有しており、それが失われた場合その企業は致命的な打撃を蒙ることになる。今回の場合、各社は1993年のWTC爆弾テロ事件の教訓も踏まえComdiscoやSunGardといったデータバックアップ・復旧サービス業者と契約を結んでいたと言われており、WTC内のデータが失われても比較的速やかに業務が再開できると思われる。実際、例えばWTC南館(2WTC)の19フロアを占め3,700人の従業員が働いていたMorgan Stanley社は、事件翌日の9月12日に、「当社の業務はすべて正常に機能しており、今後も機能し続けます」とのメッセージをホームページに掲載したという。
今回の事件は、まさにデータバックアップ・復旧サービスの真価が問われる事件であると言えるだろう。
3.有事におけるITの活用
(1) 事件直後から、ニューヨークとワシントンDCでは固定電話回線と携帯電話回線のトラフィックが急増し、これらの電話がかかりづらくなった。Verizonによると、ニューヨークやワシントンDCの市内通話量は通常の2倍に膨らんだという。また、国際電話の需要も急増し、British Telecomによると、事件直後には欧州から米国向けの回線需要が通常の60倍にも達し、大西洋間の回線がパンクしたという。
こうした中で、多くの人が安否の確認に電子メールやインスタント・メッセージを利用した。(実際に私のところにも多くのメールをいただきました。)また、生存者に関する情報を共有するための市民サイトが速やかに立ち上がるといった動きも見られた。携帯電話が思っていたほど使えなかった中で、インターネットが貴重な通信手段として一定の役割を担ったと言えるだろう。
(2) しかし、インターネットが万能だったわけではない。CNN.comなどのニュース系のウェブサイトには、事件直後からアクセスが急増し、結局これらのサイトは麻痺状態に陥ってしまったという。CBSの呼びかけによってNBC、ABC、CNNなどすべての大手放送局がすべての放送映像を相互提供することに合意し、CMをすべてカットして事件報道を続けたこともあり、少なくとも米国内ではニュース報道に関しては従来型メディアであるテレビがインターネットを圧倒したと言うことができるだろう。もちろん、インターネットも、例えばフライト状況の確認といったニーズに対し一定の役割を果たしたが、速報性の面で課題を残した。
(3) また、インターネットに関して従来から指摘されている様々な課題が、今回の事件後にも顕著に見られた。
例えば、事件発生後、被害者救済のための寄付を呼びかける電子メールが急増したが、これらの中には、例えば赤十字と無関係にもかかわらず赤十字を名乗って寄付を募るといったオンライン詐欺メールが多く含まれていたという。米国人は寄付やボランティアには非常に積極的で、事件翌日の9月12日にマンハッタンの献血会場の前を通ったら献血に来た人々が幾重にもビルの周りを取り囲んでいて驚いたが、こうした善意に付け込む詐欺は本当に許せない。ニューヨークのジュリアーニ市長も記者会見の中で、市民に詐欺に気をつけるよう注意喚起していた。
また、オンライン競売のeBayは事件後に、利用者からの抗議を受け、サイトの出品ポリシーに基づきWTCやペンタゴン関連の物品の出品を中止する措置をとった。これはモラルの問題であろうが、WTCの模型や写真といったもののみならず、ビル崩壊後の破片まで売りに出されたというから何をか言わんや、である。
インターネット上の情報の信頼性の問題もある。上述の安否確認のためのウェブサイトは、誰でも書き込みができるため逆に情報の信頼性に欠けるとも言え、やはり直接電話で話をしない限りは安心できないというのが本音であろう。ネット上のチャットルームも盛況だったようだが、誤報や流言飛語の類もあったようである。ハッカーによる被害は今のところ報告されていないようだが。
(4) 一方、テロ事件を受けて、多くの企業がインターネットを活用した貢献策を打ち出した。Yahoo!、Amazon.comなどは、同サイトを通じて赤十字への募金を呼びかけ、募金した場合に通常かかる手数料を無料化した。ウォール・ストリート・ジャーナルは、普段は有料となる電子版を無料化する措置をとった。調査会社Gartnerは、テロ事件を踏まえ、通常は数千ドル以上するセキュリティ関連のレポートへのアクセスを無料化にした。
(5) 全般的に、民間のウェブサイトは事件後に迅速な対応をとったが、政府系のサイトは情報が少なかったとの指摘がある。例えば、事件後に政府ポータルfirstgov.comに掲載された唯一の情報は、緊急連絡先リストへのリンクだけだったという。もちろん、連邦航空局(FAA)が空港閉鎖状況に関する情報をウェブ上で提供したり、FBIがテロの犯人グループに関する市民からの情報を受け付けるサイトを設けたりと、政府も様々な形でインターネットを活用しているが、残念ながら"緊急時のポータルサイト"として機能したものはなかったようである。もっとも、インターネットは分散しているから有事に強いという考え方と"緊急時のポータルサイト"という考え方は相容れないのかもしれないが。
(6) 以上を総括すれば、今回のテロ事件ではインターネットが一定の役割を果たしたものの、一方でその欠点も目に付いた。こうしたインターネットの長所・短所を充分に踏まえつつ、政府、企業の危機管理プログラムにおけるインターネットの取り扱いについて再点検をしておく必要があろう。
(7) なお、今回のテロ事件では携帯電話は"思っていたほど使えなかった"と書いたが、WTC崩壊で瓦礫の下に埋もれた生存者が携帯電話で助けを求めて救助されたとの報道がある。また、ハイジャック機の乗客が携帯電話で家族と連絡をとっていたとの報道もある。携帯電話はやはり有事における貴重な通信手段であることは確かであろう。
そもそも米国では携帯電話は犯罪や事故の際の通信手段として重要視されており、連邦通信委員会(FCC)は今年の10月1日から「E911」(Enhanced 911。911は日本の110と119に当たる電話番号で、E911は携帯電話から911通報した場合に自動的にその位置が1km〜数kmの精度で特定できるシステム。)の運用を開始するよう通信キャリアに対し求めていた。実際にはE911の導入準備はあまり進んでいないと言われているが、今回のテロ事件を契機に、そのあり方についての議論が起こりそうである。
4.国家安全保障面でのITの活用
(1) 私がテロ事件発生を知り、もうもうと立ち昇る煙を見ながら思ったのは、「FBIやCIAはこれだけの組織的なテロ事件をなぜ事前に察知できなかったのだろうか」ということだった。EchelonやCarnivore(現在はDCS1000と呼ばれている)といった通信や電子メールの傍受システムの導入についてはプライバシー擁護派の強い反発があるが、これだけの大事件が未然に防げなかったことに対する反省や犯行グループ捜索上の必要性から、今後国家安全保障とプライバシー保護のトレードオフが議論になるのは必至である。
なお、事件発生直後、FBIはインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)や電話会社に情報提供等の協力を求め、各社は協力を約束したという。ただし、各社ともCarnivore(DCS1000)の設置は拒否したと報じられている。
(2) もう一つ、今回の事件でテロリストが使用した凶器はナイフだけだったと聞いて思ったのは、「空港の従来の手荷物検査などのセキュリティ・チェックはハイジャック犯人が自爆することを想定しておらず、自らの命を惜しまないタイプのテロに対しては全く役に立たない」ということだった。私は飛行機に乗る際にEチケット(オンラインでチケットを購入し当日空港で運転免許証など写真つきの身分証明書を見せて搭乗券を受け取り搭乗するシステム)を愛用していたのだが、残念ながらこのシステムはセキュリティ対策強化のため見直しを迫られるという。
また、テロリストが簡単に米国に入国できてしまうのは国務省や世界中の在外公館のビザ発給情報システムが前時代的なものだからだとの指摘もある。ゲームソフトとして発売されているフライト・シミュレータがテロリストの操縦訓練に役立ったのではないかといった指摘まで出ているが、これはさすがにゲームソフト・メーカーが可哀想であろうか。
いずれにしても、今回のテロ事件を踏まえ、ハイテクやITシステムの進歩も踏まえた徹底的なセキュリティ・システムの見直しが行なわれることとなろう。
おわりに
IT関連業界にとって、今回のテロ事件を受けての最大の懸念は、米国経済及び世界経済が現在のIT不況から更なる大不況に突入するのではないかという懸念であろう。テレビや新聞の報道などを見ていると、「America under Attack」だとか「パールハーバー以来の悲劇」など、戦争用語が頻繁に使われており、米国本土が攻撃された経験を持たない米国人にとって、今回のテロ事件の心理的影響は我々日本人が想像する以上に大きいと思われる。メジャーリーグ・ベースボールをはじめ大衆的イベントも相次いで中断されたが、まさに「それどころではない」というところであろう。クリスマス商戦をひかえ、消費者心理の冷え込みがたいへん懸念される。この懸念が的外れに終わることを切に祈念したい。
(了)
本稿に対する御質問、御意見、御要望がございましたら、Ryohei_Arata@jetro.go.jpまでお願いします。
(C)Copyright JEITA,2001
|