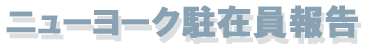
【 2002年9月号 】
~ 米国の通信業界の動向 ~
JEITAニューヨーク駐在(JETROニューヨーク) 荒 田 良 平
|
はじめに
いわゆるITバブルの崩壊は、特に通信業界に大きな影響を与えたが、今年1月のグローバル・クロッシングの破綻に続き、7月にはついに長距離通信大手ワールドコムが連邦破産法11条(日本の会社更生法に相当)申請に追い込まれるなど、米国の通信業界は一向にテレコム・バブル崩壊からの立ち直りの気配を見せない。ドットコム・バブルの清算が一段落し、民間IT投資が底打ちの気配を見せる中で、通信業界は一体どうなっているのであろうか。
ワールドコムの破綻などは、もちろん昨年のエンロン破綻を機に表面化した不正経理問題の側面も有するのであるが、今月の駐在員報告では、米国の通信業界を巡る最近の一連のできごとを、1996年の通信法改正による通信業界への競争導入という流れの中で私なりに整理してみたい。
なお、米国の通信政策や通信業界は非常に奥が深く、とりあえず入手できた文献等でにわか勉強してみたものの、私の手には余る感が否めない。城所岩生氏著の「米国通信改革法解説」など参照した文献等を末尾に記載しておくので、興味のある方はこれらを直接御参照いただきたい。
1.米国通信分野における競争政策の経緯
昨今の米国通信業界の動向を理解するためには、まず、その根底にある、米国通信分野における競争政策の経緯を把握しておく必要がある。以下に、各種参考文献からの受け売りであるが、その大まかな経緯を記しておく。
(1)1996年通信法改正以前の米国通信業界
1996年通信法改正以前の米国通信業界における最大のトピックスといえば、多くの人が1984年のAT&T分割を挙げるであろう。これは、日本の1985年の電電公社民営化にも大きな影響を与えるなど、世界の通信業界にも変革を迫る大事件であった。
AT&Tは、言うまでもなく、1876年に電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルが1877年に設立したThe Bell Telephone社の流れを汲む通信業界の巨人である。AT&Tは、1894年の特許切れに伴い電話事業に参入した独立系の他の電話会社を次々と買収し独占体制を築いていったため、1913年、1949年、1974年の3回にわたり司法省から反トラスト訴訟を提起された。
1913年の第一次訴訟は、AT&Tが司法省に対し、①以後独立系の電話会社の買収は行わない、②独立系電話会社の回線とAT&Tの長距離回線との相互接続を認める、旨を誓約して和解し、これを裁判所が確認することによって判決と同じ効力を持つ同意判決の形で決着した。また、1949年の第二次訴訟は、司法省が非規制の機器製造子会社ウェスタン・エレクトリック社の分離を求めたのに対し、AT&Tがウェスタン・エレクトリック社を引き続き保有する代わりに規制対象の公衆電気通信事業以外に進出しないという同意判決で1956年に決着した。
そして、1974年に提起された第三次反トラスト訴訟は、1982年、AT&Tが機器製造(ウェスタン・エレクトリック社)や研究開発(ベル研究所)を維持し、コンピュータや情報通信分野への進出を許される代わりに、地域通信サービスを提供するベル電話会社を分離するという同意判決(1956年同意判決を修正する形であり「修正同意判決」と呼ばれる)で決着したのである。(なお、余談になるが、AT&Tはベル電話会社を分離してまで守った機器製造部門を、結局は1996年にルーセント・テクノロジーズ社として分離することになる。)
一方、AT&T分割を生む背景となった通信分野における競争導入には、連邦通信委員会(FCC)が大きな役割を果たした。
FCCは、1934年通信法によって設立された州際通信・放送を規制する行政委員会である。(米国は御存知の通り、各州が独立した立法、司法、行政の権限を有し、州政府が対応できない機能だけを連邦政府が担うということになっているので、各州内の公衆電気通信サービスに関する公益事業規制は州の公益事業委員会が担当している。しかし、州内通信と州際通信の規制を完全に切り分けることは困難であり、FCCの規制が州の公益事業委員会の権限を侵しているとして問題になることがある。)FCCは、1968年に他社が提供する付属装置の接続を禁ずるAT&Tの営業規則の見直しを命じ、電話端末機器への競争を導入した。また、1969年には、マイクロウェーブ・コミュニケーションズ社(1971年にMCIに改名。1998年にワールドコムに買収された。)がマイクロ波無線設備を設置して行う専用線通信サービスを認可し、長距離通信分野に競争を導入した。
このように、FCCは、電話端末機器に対するユーザーニーズの多様化や、技術革新による低コストでの代替通信手段の出現といった環境変化を踏まえ、公益事業である公衆電気通信分野に競争を導入していった。こうした競争導入が、AT&Tを分割に追い込む大きな要因となったといえるであろう。(なお、FCCは1992年には地域通信分野でも、自前で回線設備を持ち通信事業を行う競争アクセス事業者(Competitive Access Provider, CAP)の参入を認めた。)
ともかく、このような経緯を経て、1982年修正同意判決に基づき、1984年にAT&Tから分離した7つの地域ベル電話会社(Regional Bell Operating Company, RBOC:ベビー・ベルとも呼ばれる)が設立された。(図表1参照)1982年修正同意判決はまた、長距離通信市場と地域通信市場を明確に区分し、AT&TとRBOCがそれぞれの市場に相互参入することを禁じた。こうして、地域通信市場において事実上の独占が維持される一方で、長距離通信市場における競争が促進されることとなった。(RBOC以外の独立系地域電話会社が長距離通信に参入することは認められ、1899年にカンサス州で設立された独立系地域電話会社大手のスプリントは、その後大手長距離通信事業者に成長した。一方、長距離通信事業者の地域通信市場への参入は認められなかったが、上述のようにFCCは1992年にCAPの地域通信市場への参入を認めた。)(図表2参照)
図表1 RBOCの営業区域
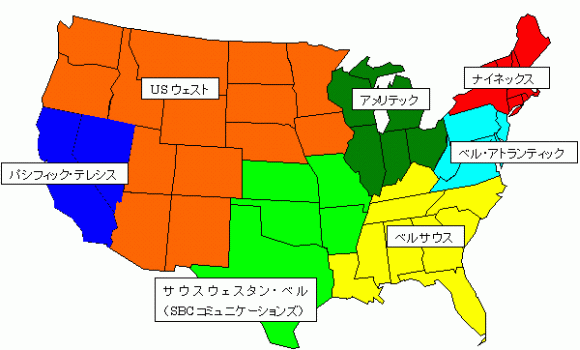
(出展: 各種資料より作成)
図表2 AT&T分割後の米国通信市場区分

(注)LATA: Local Access and Transport Area。全米で196のLATAが設定された。
(出展: 各種資料より作成)
こうした一連の経緯の詳細は他文献に譲るとして、ここでは米国通信業界の動向を見る際の基本的な留意点を挙げておきたい。
それは、日本では他のほとんどの国と同様、電電公社という独占を法定された公共事業体を通じて公衆電気通信サービスの普及が図られたのに対して、米国では、通信インフラは公的部門によって整備されたのではなく、私企業の競争を通じて整備されたということである。(もちろん公益事業規制の重要性を否定するものではない。)AT&Tは米国の地域通信市場を完全に独占していたわけではなく、農村部を中心に数多くの独立系の地域電話会社が存在していた。(現在でも、RBOC以外に引き続き約1,300の独立系地域電話会社が存在している。)
最近、米国ではDSL事業者などの破綻が相次ぎ、ユーザーが突然サービスを打ち切られるなどで大きな問題になっている。また、米国におけるブロードバンド普及の伸び悩みから、ハイテク産業界が新しいブロードバンド普及政策の必要性を訴え、議会・政府における対応が注目されている。日本ではこうした通信サービスの保障や通信インフラの整備に関して、政府等公的部門の果たすべき役割が当然のごとく議論されるが、米国では上述のような経緯もあってか、公的部門に大きな役割を期待するという発想は希薄なようだ。(もちろん、どちらが良いのかは議論の分かれるところである。)
(2) 1996年通信法改正による競争促進
さて、このように1969年の長距離通信分野への競争導入に続き1992年には地域通信分野へも競争が導入されていた通信業界は、1996年の通信法改正によって本格的な競争時代に突入することになる。以下に、その経緯を簡単に整理しておこう。
米国の現在のIT先進国としての基礎を築いた功労者としてゴア前副大統領を挙げることに異論を唱える人は少ないであろう。ゴア氏は副大統領就任以前の上院議員時代から、全米の家庭、企業、学校などを光ファイバで結び高速・双方向の情報通信ネットワークを構築しようという「情報スーパーハイウェイ構想」を提唱していた。そして1993年、副大統領となったゴア氏はこれを発展させて「全米情報基盤(NII)構想」を提唱したのである。
しかし、政府主導のNII構想に対してはAT&TやRBOCなどの大手通信事業者の反発も強かった(上述の米国通信業界の歴史を見れば理解しやすい)ため、クリントン政権はインフラ構築を民間に任せ政府は民間が積極的に投資を行える環境を整備することとし、その一環として時代遅れになっていた1934年通信法の改正を提案した。その後、紆余曲折を経て、1996年2月に1996年電気通信法が成立したのである。
この1996年電気通信法の詳細はやはり他文献に譲ることとするが、ともかくテレビもコンピュータも無かった時代にできた通信法の62年ぶりの大改正であり、様々な内容を含んでいる。ここでは、平成10年版通信白書から、その概要を転記しておく。
《1996年米国電気通信法の概要(平成10年版通信白書より)》
| ① |
地域通信市場における競争の促進のため、相互接続義務をはじめとする接続ルールが明確化され、また、電力・ガス事業者等の参入が認められた。 |
| ② |
AT&T分割の際の修正同意審決(MFJ)により、業務範囲の制限されていたRBOCs(ベル系地域電話会社)による長距離通信分野への参入は、営業区域内から発信されるサービスについて分離子会社によること、地域の競争条件が整備されていることについての承認を得ること、地域通信分野における設備ベースの競争相手との競合が存在すること等、一定の条件の下、認められた。 |
| ③ |
地域電話会社とケーブルテレビの相互参入が認められた。 |
| ④ |
テレビ局、ラジオ局について、集中排除原則及び免許期間等の緩和、また、ケーブルテレビについて、料金規制の緩和が行われた。 |
| ⑤ |
暴力事件の多発を背景に、13インチ以上のテレビ製造メーカーに対して、暴力や性的シーンの多い番組をブロックするVチップの内蔵が義務付けられた。 |
| ⑥ |
このほか、インターネット等によるわいせつな通信についての規制が強化されたが、「下品な(indecent)」及び「明らかに不快な(patently offensive)」表現の規制については、表現の自由に反するとして、1997年6月、連邦最高裁判所において違憲判決がなされた。 |
本稿の文脈に照らして、このうち①について若干の説明を加えておきたい。この地域通信市場における競争促進について、1996年電気通信法は、
- 規制権限を有する州政府が特定の者の参入を禁止することを法律で禁じたうえで、
- すべての通信事業者に対し相互接続を義務付け、
- 1982年修正同意判決を受けて明確化されていた地域通信事業者(Local Exchange Carrier, LEC)と長距離通信事業者(Inter Exchange Carrier, IXC)との間の相互接続料(アクセス・チャージ)に加え、新たに地域通信事業者(LEC)同士の相互接続料(相互補償金)のルールを明確にすること、
- 地域通信事業者(LEC)が他の通信事業者に設備を卸売りすること、
- 既存の地域通信事業者(Incumbent LEC, ILEC:RBOCと独立系地域電話会社を指す)が新規参入者である競争地域通信事業者(Competitive LEC, CLEC:既存の競争サービス事業者を含む)に対し、アンバンドルして(CLECが必要とする設備だけを)提供すること、その際にILEC局舎内にCLEC設備の設置(物理的コロケーション)を認めること、さらに、
- ユニバーサル・サービス(定義が問題なのだがとりあえず「基本的な通信サービスがコストに係らず広く妥当な価格で提供されること」としておく)を促進するためのガイドラインを策定すること、などを定め、具体的な接続ルール等の規則の策定をFCCに委ねた。これを受けてFCCは、「競争三部作」と呼ばれる「相互接続規則」(1996年8月)、「ユニバーサル・サービス」(1997年5月)、「アクセス・チャージ」(1997年5月)などの規則を策定した。
これらによって、CLECが地域通信市場に新規参入するにあたり、設備をすべて自前で設置する、ILECから一部をリースする、ILECから丸ごとリースする、という様々な選択肢をとる道が開かれることになった。
図表3 1996年電気通信法体系下での通信事業者区分
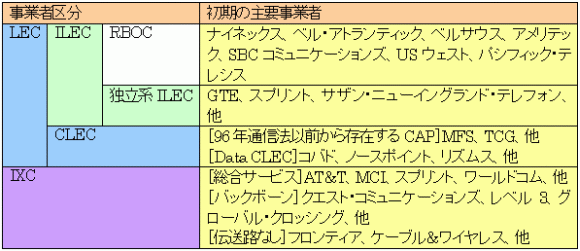
(注)通信分野におけるこの他のプレーヤーとして、96年通信法では通信事業者とされないISP(アースリンク、PSIネット他)やCATV事業者(タイム・ワーナー・ケーブル他)などがいる。
(出展:各種資料より作成)
さて、こうして通信市場に本格的な競争を導入するための基本的な枠組みができたわけであるが、この1996年電気通信法やFCC規則は直接的に通信事業者の競争条件を左右することになるため、その後関係者からの訴訟が相次ぐことになった。この詳細は、城所岩生氏著の「米国通信改革法解説」に詳しいが、例えば、
- 1996年電気通信法がRBOCに対し(上記②のように)長距離通信市場参入等にあたって各種条件を課しているのは、私権剥奪法を禁じた合衆国憲法違反である。(RBOC)
- FCCの相互接続規則が上記DやEの料金の算定方式と州が正式決定するまでの暫定的な代理料率を定めているのは、州政府の権限を侵す越権行為である。また、代理料率が人為的に低く設定されている。(州、ILEC)
- アクセス・チャージを段階的に引き下げるのではなく、即刻大幅に引き下げるべき。(IXC)
- アクセス・チャージを引き下げすぎである。また、アクセス・チャージを免除されているインターネット・サービス提供事業者(ISP)にもこれを課すべき。(LEC)
などといった訴訟が提起された。
さらに、その後インターネットが急速に普及し、ブロードバンド化が進展する中で、1996年電気通信法が想定していなかった様々な問題も表面化した。
例えば、ISPのトラフィックが一方的にインターネット加入者からの着信であることに目を付けたCLECがISPを積極的に取り込んだため、本来バランスするはずの上記CのLEC間相互補償金(発信側LECが着信側LECにトラフィックの分単位で支払う)がILECからCLECへの一方的な持ち出し(月6,000万ドルにも上ったという!)になり、ILECがその見直し・廃止を求めるといった動きが出てきた。
また、RBOCは高速データ通信であるブロードバンドでの競争で遅れをとらないようにするため、高速データ通信には上記②の条件や上記Eの義務を適用しないこと、及び高速データ通信のLATAは州全域を1つのLATAとする(つまり実質的には本来長距離通信にあたる州内LATA間通信に自由に参入できるようにする)ことを要請した。
このように、1996年電気通信法はその複雑な規制体系に必然的に伴う、また急速な技術革新に伴い新たに生じる様々な問題を生み、その解決のため、FCC、州政府、裁判所、議会などが対応に追われることになった。関係者の精力的な対応によって、日本の感覚からすると驚くほど速やかに、多くの問題が決着を見たのであるが、それでも現在なお残されている問題もある。
1996年通信法改正に関しては、よく「規制緩和によって競争を促進した」という表現が使われる。もちろん、地域通信事業者とCATV事業者との間で相互参入が認められたなど、大きな意味では規制緩和であることに間違いないのだが、詳細な規定を見ると、様々な関係者間の利害調整を意識した規定が多く、むしろ「競争を促進すべく規制を見直した(適切な規制を導入した)」というのが実態ではなかろうか。
2.1996年通信法改正以後の米国通信業界
ともあれ、1996年通信法改正によって、RBOCが自社営業区域内から発信される長距離通信事業に参入する場合を除き、通信事業への形式的な参入制限が無くなり、米国通信業界は本格的な競争時代に突入することとなった。
この状況を受けて米国通信業界に起こった現象を要約すると、大きく以下の3点に要約できるであろう。
① CLECの地域通信市場への参入
② IXCやRBOCの戦略的M&A
③ バックボーン・ネットワークへの積極的投資
以下に、それぞれについてもう少し詳しく見てみることとしたい。
(1) CLECの地域通信市場への参入
1996年通信法改正を受けて、数多くの(1,000社程度とも言われる)CLECが地域通信市場に参入した。このCLECは、音声(電話)サービスを中心とするタイプ(Voice CLECとも呼ばれる)と、データ通信サービスを重視したタイプ(Data CLEC又はDLECとも呼ばれる)に大別される。
Voice CLECの中には、MFSコミュニケーションズやテレポート・コミュニケーションズ・グループ(TCG)のように、1996年通信法改正以前から企業向けの高速回線などの自前設備を持ち競争アクセス事業者(CAP)として地域通信市場に参入していた事業者もいる。こうした事業者は、後述するようにその後次々と大手IXCに買収されることとなった。
一方、インターネットやブロードバンドの急速な普及に伴って、数多くのData CLECが地域通信市場に参入して急成長し、コバド・コミュニケーションズ、ノースポイント・コミュニケーションズ、リズムス・ネットコネクションズなどが脚光を浴びるようになった。こうした事業者は、株高を背景に借入などで資金を調達し、また取引先である通信機器ベンダーから機器調達のための融資を受けて、事業を拡大していったと言われる。
なお、上述のように、CLECの中にはISPを顧客として取り込んで、又は自らがISP事業を行うことによって、ILECから巨額の相互補償金を得ていた者がいると言われる。確かに、有力なISPを取り込むだけで毎月何千万ドルもの大金が転がり込むのだから、おいしいビジネスであることは間違いない。(麻薬取引よりもウマいという陰口まである。)当然、ILEC側は強く抗議したわけであり、これにはさすがに同情の余地もあるのであるが、実はこの相互補償ルールを決めた時点では、むしろ規模の大きいILECの方が着信が多くなりCLECから相互補償金を巻き上げることができると期待していたらしい。それに、ILECだってISPを取り込むことはできたはずなのにその努力をしなかっただけではないか、とCLEC側は応酬した。結局、FCCは2001年にパウエル新委員長の下でISP向けのトラフィックについて相互補償金を段階的に逓減させる方針を打ち出した。
まあ、どちらにも言い分はある中で、新政権下でILEC側の政治力が勝ったということなのかもしれないが、気になるのは、この相互補償金に大きく依存していたCLECやISPがいたという指摘があることである。ビジネスモデルが相互補償金で支えられているような脆弱なものだったとすれば、容易に破綻しても不思議ではないであろう。
(2) IXCやRBOCの戦略的M&A
一口にIXCと言っても、その中には、自らが伝送路も保有しながら総合的な長距離通信サービスを手がけるAT&T、MCI、スプリント、ワールドコムといった事業者や、光ファイバによる高速大容量のデータ・バックボーンを建設し伝送路を他のIXCに卸売りするクエスト・コミュニケーションズ、レベル3といったバックボーン事業者、伝送路を借りて長距離通信サービスを提供するフロンティアやケーブル&ワイヤレスなど様々な事業者が含まれる。
AT&Tをはじめとする大手IXCは、いわゆるラストワンマイルを手に入れてワンストップ・サービス構築を進め総合通信サービス事業者への脱皮を図るため、あるいは急速なトラフィック拡大が予想されるデータ通信向けのバックボーン・ネットワーク建設及びインターネット・データ・センターなどの関連サービスで主導権を握るため、その体力を生かして次々と戦略的M&Aを行った。
例えばAT&Tは、1998年にVoice CLEC大手のテレポート・コミュニケーションズ・グループ(TCG)を買収し、地域通信市場への足がかりを築くとともに、大手CATV事業者に目をつけ、1999年にテレ・コミュニケーションズ(TCI)を、また2000年にメディアワンを矢継ぎ早に買収した。AT&Tはさらに、国際的なIP(インターネット・プロトコル)ベースのネットワーク構築に生かすため、1999年にIBMのグローバル・サービス事業を買収した。
また、ワールドコムもM&Aに積極的だった。ワールドコムは、不正経理問題が発覚し破綻して広く知られるようになったように、元々は1983年にミシシッピー州の長距離通信会社として設立されたのだが、その後数十に及ぶM&Aを繰り返して成長した企業である。IXC第4位のワールドコムは、1996年に世界最大のインターネット・バックボーン・ネットワーク・サービス事業者であるUUネットを傘下に持つ地域通信事業者MFSコミュニケーションズを買収し、1998年にはIXC第2位で自社の2.5倍の売上高を有するMCIを買収して、ついにIXC第2位にまでのし上がった。ワールドコムはさらに1998年に、IXC第3位で地域通信事業と携帯電話事業も有するスプリントの買収を発表するのだが、さすがにこれは長距離通信市場における競争が損なわれることを懸念した司法省の差し止め訴訟を受けて断念せざるを得なかった。
一方、バックボーン大手のクエスト・コミュニケーションズは、2000年にRBOCの一つで自社の5倍の売上高を有するUSウェストを買収した。(長距離通信事業は売却。)この一見奇妙な組み合わせは、国際バックボーン事業者グローバル・クロッシングがUSウェスト及びニューヨーク州の独立系地域電話会社から大手IXCに成長したフロンティアとの合併を1999年に次々に発表したことに危機感を抱いたクエスト・コミュニケーションズが、USウェスト及びフロンティアに対し敵対的買収を仕掛けたことによって生まれた。クエスト・コミュニケーションズはUSウェストを強引に横取りしてしまったわけである。なお、グローバル・クロッシングはフロンティアについては予定通り1999年に買収している。(その後地域通信事業などは売却。)
こうした大手IXCの積極的なM&Aの一方で、RBOCも通信業界における主導権確保のため合従連衡を繰り広げた。
ベル・アトランティックは、まず1997年にナイネックスを買収して大市場である米国北東部一帯の地盤を固めるとともに、2000年には独立系ILEC最大手のGTEを買収し、ベライゾン・コミュニケーションズとなった。ベル・アトランティックはまた、競合他社への設備開放など長距離通信事業への参入に必要な条件を満たしたとして、1999年にRBOCとして始めてニューヨーク州から発信される長距離通信事業への参入認可をFCCから得て、地域通信と長距離通信のワンストップ・サービス提供への道を開いた。
また、SBCコミュニケーションズは、1997年に経営の厳しかったパシフィック・テレシスを買収し、1999年にはアメリテックを買収して、テキサス、カリフォルニア、イリノイといった大市場を傘下に収めることとなった。
このような他のRBOCの積極的な動きの中で、手詰まりであったUSウェストは、上述にように結局2000年にバックボーン大手のクエスト・コミュニケーションズに買収される道を選ぶこととなったのである。
こうして、1984年のAT&T分割によって生まれた7社のRBOCは4社に再編された。(図表4参照)
図表4 RBOCの再編
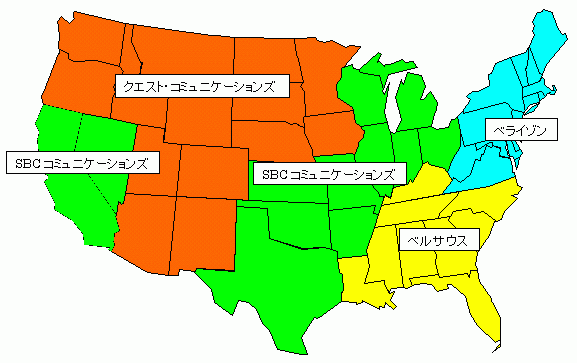
(出展: 各種資料より作成)
御存知の通り、これら以外にも数多くのM&Aが行われたのであるが、ここでは割愛させていただく。
なお、上述のような大型のM&Aは、司法省やFCCの認可を必要とした。司法省とFCCは、通信事業者の巨大化が競争を阻害し消費者の不利益になることがないかどうかという観点から審査を行い、場合によっては長距離通信事業の分離や携帯電話事業の分離など様々な条件のもとにこれらのM&Aの認可を行った。(ワールドコムのスプリント買収のように拒否したものもある。)その詳細は省略するが、これら規制当局の案件ごとの判断が、1996年電気通信法の下での米国通信業界の競争状態を左右する重要な要因になったと言えるであろう。
もう一点、ここで触れておかなければならないのは、ワールドコムのMCI買収やクエスト・コミュニケーションズのUSウェスト買収に象徴されるような、100億ドルから数百億ドルにも及ぶ、また時として小が大を飲み込むようなM&Aがどうしていとも簡単に行われたのかということである。よく知られているように、これらのM&Aはそのほとんどが株式交換方式で行われており、買収する側はキャッシュを必要としない。株式交換方式自体は戦略的・機動的なM&Aを可能にするし株主重視の経営にもつながるため、経済構造改革のため重要な役割を果たすものなのであるが、当時のように「IT革命」「ニュー・エコノミー」の名の下に株価が右肩上がりを続ける局面では、株高を背景としたM&Aが一層の株高を生むという形でバブルを助長するとともに、その後のワールドコムの不正経理問題に見られるように「株主」ではなく「株価」を重視する風潮を助長する一因になってしまったことは否めないであろう。その後、2001年12月に企業の買収価額と純資産額との差額である「のれん」の扱いについて企業会計基準が変更され、膨大な「のれん」を抱えた多くの企業が頭を悩ませることとなった。
ところで、1996年通信法改正で条件付きで可能になった、RBOCの長距離通信市場への進出はどうなったのであろうか。RBOC各社にとって、地域通信と長距離通信のワンストップ・サービスの提供は大きな魅力ではあったが、当初は競合他社への設備開放などの条件についてFCCを満足させることが出来ず、上述のように1999年にベル・アトランティック(現ベライゾン)がニューヨーク州発信の長距離通信事業を認められたのが最初だった。その後、2001年に入って(政権が変わって)認可が進み、これまでベライゾンがマサチューセッツ、コネチカット、ペンシルバニア、ロード・アイランド、バーモント、メイン、ニュージャージー各州について、SBCコミュニケーションズがテキサス、カンサス、オクラホマ、アーカンソー、ミズーリ各州について、またベルサウスがジョージア、ルイジアナ各州について、長距離通信事業への参入を認められている。(図表5参照)
図表5 RBOCの長距離通信事業参入の認可状況(2002年8月現在)
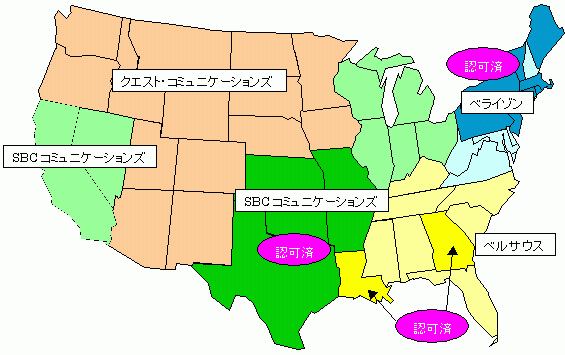
(出展: FCC資料より作成)
(3) バックボーン・ネットワークへの積極的投資
このように、インターネットやブロードバンドの急速な普及に伴いData CLECなどが成長し、また大手IXCやRBOCが合従連衡を繰り広げるのと並行して、バックボーン事業者は急速なトラフィックの増大を見込んでバックボーン・ネットワークへの積極的な投資を行った。
全米での光ファイバ網建設で先行したのは、クエスト・コミュニケーションズだった。同社は、元々サザン・パシフィック鉄道の子会社として鉄道沿線に光ファイバを敷設する会社だったのであるが、1996年に独立してから急成長を遂げた。1997年に上場され、巨額の資金を調達して光ファイバの敷設を進めたが、他社に先行した強みもあって、GTE、フロンティア、ワールドコムといった通信事業者に回線の半分を卸すことによって建設費の9割を回収できたという。こうして同社の株価はうなぎ上りとなり、その高い株価を背景にさらに巨額の資金を調達して、全米に2万5千マイル(4万km)にも及ぶ光ファイバ網を建築した。
このクエスト・コミュニケーションズに対抗して、レベル3コミュニケーションズやウィリアムズ・コミュニケーションズ、IXCコミュニケーションズといったバックボーン事業者も積極的に光ファイバ網への投資を行った。また、地域通信事業者も、大都市圏の幹線ネットワークや企業向け専用線に光ファイバを導入した。このようにして、総延長およそ3,900万マイル(地球を1,560周分!)とも言われる光ファイバが全米に張り巡らされることとなった。(この数字には、未使用のいわゆるダークファイバが含まれていると思われる。大都市で光ファイバ敷設を進めたメトロメディア・ファイバ・ネットワーク(MFN)社は、一度に864本の光ファイバを束ねたケーブルを最低4本、場合によっては20本以上もまとめて敷設していたという。)
また、グローバル・クロッシングは巨額の資金を調達して従来大手通信事業者がコンソーシアム形式で共同で行っていた海底ケーブル敷設を単独で行い、世界中に16万km(地球4周分)の光ファイバ網を敷設した。
このようなバックボーン・ネットワークへの積極的投資の背景には、IT革命の進展によってトラフィックが天文学的に増えるという予測があった。最盛期には、光ファイバの需要は1年に10倍のペースで増大したという。
投資ブームに沸く通信業界に対して、銀行などは先を争うように資金を提供した。国際決済銀行(BIS)の2002年2月のレポート「IT innovations and financing patterns: implications for the financial system」によると、米国の通信業界の1998年から2001年の4年間における借入金は4,113億ドル、債券による資金調達額は991億ドル、合わせて5,100億ドルに上ったという。
こうして、1997年に540億ドルだった米国通信業界の設備投資額は、2000年には1,130億ドルにまで膨らんだ。
3.通信バブルの崩壊
右肩上がりを続けると思われたインターネット関連株価は、2000年に入って変調を来たし始める。2000年3月10日に5,000を超えるピーク値を記録したNASDAQ総合指数は、一部ドットコム企業の株価急落に端を発して値を下げ、秋口以降のインターネット関連株価全体の下落につながっていった。そして、2000年末までにNASDAQ総合指数はピーク時の半分以下にまで下落したのである。
こうした中で、まず2000年5月頃から始まったドットコム企業の相次ぐ破綻もあって期待されたほど顧客を獲得できなかったDSL事業者や固定無線アクセス(FWA)事業者などのCLECが、2001年になって次々と連邦破産法11条(日本の会社更生法に相当)の申請に追い込まれた。RBOCのアンバンドルされたDSL設備を利用したDSL事業者は、RBOCとの間で顧客サービスなどに関するトラブルを抱え魅力的なサービスを利用者に提供できず、また専用線や固定無線アクセス(FWA)など自前設備を導入した事業者は、多額の債務を抱えることになった。こうした中で、株価下落によって銀行などからの追加資金調達が苦しくなったCLECが次々と破綻に追い込まれたということである。
ドットコム企業の破綻がCLECの破綻に波及し始めると、次第に通信バブルの実態が明らかになってきた。つまり、IT革命の進展によって天文学的に伸びると思われていた通信トラフィックが、実は期待されたほど伸びておらず、光ファイバが過剰設備の状態になっているということである。1本の光ファイバに少しずつ波長の違う複数の光を通すことで通信容量を飛躍的に増やすことの出来る波長分割多重(WDM)技術が進歩したこと、大都市間のバックボーン回線への光ファイバ導入に比べ都市内の幹線網や加入者回線のブロードバンド化が遅れたことも、光ファイバの過剰状態に拍車をかける結果となった。2001年6月に明らかになったメリル・リンチの推計によると、米国中に張り巡らされた光ファイバの通信容量のわずか2.6%しか実際には利用されていないという。(上述のように、これはダークファイバを含んだ数字だと思われるので、かなり極端な数字になっている。通信事業者側は、実際に両端がネットワークに接続され使える状態にある光ファイバの稼働率はずっと高いと反論している。)
こうした中で、2001年10月に発覚したエンロンの不正経理問題が2001年1月に破綻したグローバル・クロッシングに飛び火し、米国証券取引委員会(SEC)が2002年2月に同社の会計疑惑について調査を開始した。同社がクエスト・コミュニケーションズなど他のバックボーン事業者との間で違法なキャパシティ・スワップ(通信事業者が売上を実態よりも大きく見せるため、他社と相互に自社回線の空き容量を長期リースし、受け取る長期リース料を当期の売上高に一括計上する一方で、支払うリース料を長期に分割して費用計上すること)を行っていたのではないかという疑惑である。
この疑惑が表面化すると、投資家の疑いの目が他の長距離通信事業者にも向けられて株価が急落し、ウィリアムズ・コミュニケーションズなどが連邦破産法11条申請に追い込まれることとなった。そして、やはりSECの調査を受けていたIXC第2位のワールドコムが、利益を多く見せるため経費を資本支出として計上するという粉飾決算を行っていたことが明らかになり、同社はついに2002年7月に連邦破産法11条の申請に追い込まれた。(図表6参照)
図表6 連邦破産法11条を申請した主な通信事業者
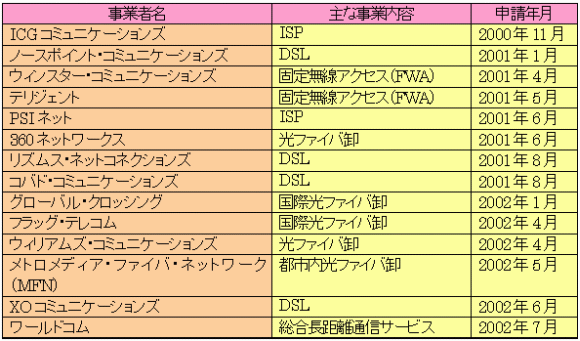
(出展: 各種資料から作成)
もちろん、エンロン事件以降の不正経理問題は、通信バブル崩壊と直接の関係はない。しかし、いずれもその根底に行き過ぎた株価至上主義があったことは否めない。実力以上に高い株価がM&Aによる急成長や多額の設備投資を可能としてバブルを招き、一方でその株価の維持の必要性が不正経理を生む大きな動機となった。
そして、株価を巡るもう一つの問題、すなわち企業役員による株の売り抜け問題もマスコミをにぎわせている。Fortune誌2002年9月2日号は、その表紙で「You Bought. They Sold.」と題して、クエスト・コミュニケーションズの創設者アンシュッツ氏が15億7,000万ドル、グローバル・クロッシングのウィニック会長が5億800万ドル、などと、現在業績悪化による株価低迷に苦しむ企業の役員が株価下落前に自社株を売り抜けて巨額の金を手に入れていたことを顔写真入で伝えている。こうした記事に見られる一般投資家の憤懣が、ストック・オプションの経費計上問題などにも反映されており、いわゆるオールド・エコノミー企業は次々とストック・オプションの経費計上を表明している。
いわば、通信業界(のみならず広くハイテク業界)の発展を支えてきた「株価さえ高ければすべてがうまくいくシステム」が変革を迫られていると言うことができるであろう。こうした観点から見ると、米国の通信業界の復活のためには、過剰設備の調整がいつ頃までかかるのかといった話とは全く別次元の話として、米国における新しい経済的インセンティブ・モデルがいつ頃どのような形で再構築されるのかが重要なポイントとなろう。
4.競争政策と通信バブル崩壊
このようにして、いわゆる通信バブルに浮かれていた米国通信業界はバブル崩壊によって苦境に陥り、現在、企業によって程度の差はあるものの多かれ少なかれその清算に追われているわけである。こうした中で、地域通信市場については以前に増して巨大化したRBOCが結局は勝ち残り、遅ればせながら着々と長距離通信市場への進出を進め、一方、IXCは音声通話需要の漸減とデータ通信部門の過剰設備で青息吐息という状況で、1996年通信法改正が目指した競争促進は今のところうまく行っていないと言わざるを得ないであろう。
では、1996年通信法改正は失敗だったのであろうか。
FCCのマイク・パウエル委員長は、2002年7月15日付けウォール・ストリート・ジャーナル紙におけるインタビューにおいて、1996年の通信法改正によって出現した競争事業者が多すぎたことがバブル崩壊を招く一因となったという意味で1996年電気通信法に責任が無いとは言えない旨を表明するとともに、RBOCによるワールドコム買収への期待を表明し、前ウィリアム・ケナード委員長が強力に進めてきた地域通信市場における人為的な競争導入からの決別を示唆している。
もちろん、こうしたパウエル委員長の考え方に対しては、異論もあるであろう。
つまり、1996年電気通信法は競争を促進すべくよく設計されていたが、その後のインターネットの予想を超えた急速な普及や株式市場の過剰な反応によって、規制当局による競争状態の創出・維持のための対応の範囲を超えて現実が暴走してしまった、という考え方である。
ただ、いずれにしても、このままでは競争は促進されず、一層のブロードバンド化のための投資も進まないことは明らかであり、何らかの手をうつ必要があるであろう。
パウエル委員長は、独占の弊害を懸念する前にまず投資を促進しブロードバンド化を進めることが先決だとして、その過程である程度の高料金を容認しても寡占事業者によるインフラ整備促進を図る意向だと見られている。
おわりに
今月は、私のお勉強に皆様にもお付き合いいただいたような形になってしまったが、御容赦いただきたい。
本稿を書きながら、改めて公益事業規制と競争政策の関係について考えさせられた。そもそも「公益」とは何なのか。妥当な料金か、安定したサービスか、新技術の普及か、はたまた産業競争力の強化か。これらのどれにどの程度の重きを置くかによって、競争政策の有り様も変わってくるであろう。そして、それは最終的には国民の選択の問題である。
日本でも、1999年にNTTが分割され、電気通信政策のあり方を巡る議論が活発化しているが、日本と米国とでは歴史、国民性、経済状況、国土条件など諸条件が異なるので、日本にとって望ましい選択肢について議論していけばよいであろう。
ただ一つ言えるのは、米国の状況を見ると、通信のような技術革新の激しい公益事業分野に競争を導入し維持するためにはたいへんな労力が必要だということである。米国のようにFCC、州政府、裁判所、議会が総動員されるような形が日本の現状から見て適当なのかどうかはともかく、このような変化の激しい分野では、技術革新、事業環境の変化等を踏まえ、様々な関係者の意見を調整しながら、過去の政策の評価を速やかにフィードバックしつつ、機動的に政策を見直していく仕組みが重要ではなかろうか。
(了)
参考文献:
城所岩生「米国通信改革法解説」木鐸社(2001年2月)
篠崎彰彦・手嶋彩子「イノベーション時代の政策像~クリントン政権の情報通信政策にみるフロンティア拡大とセイフティーネット整備~」フジタ未来経営研究所(2001年5月)
小池良次「アメリカ情報通信」(http://www.ryojikoike.com/)
DRIテレコムウォッチャー(http://www.dri.co.jp/watcher/index.htm)
平成10年版「通信白書」
(http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/papers/98wp2-8-1.html)
「IT innovations and financing patterns: implications for the financial system」国際決済銀行(BIS)
(2002年2月)(http://www.bis.org/publ/cgfs19.pdf)
本稿に対する御質問、御意見、御要望がございましたら、arataryohei@jetro.go.jpまでお願いします。
(C)Copyright JEITA,2002
|