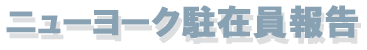
【 2002年10月号 】
~ ニューヨーク州におけるナノテクへの取組み ~
JEITAニューヨーク駐在 荒 田 良 平
|
はじめに
今月は、ニューヨーク州都オルバニー(Albany)近郊におけるナノテクノロジーへの取り組みについて紹介する。
多くの方は、「ニューヨーク州でナノテク?」「オルバニーってどこ?」といった反応を示されるのではないかと思うが、本年7月にニューヨーク州がInternational SEMATECHの次世代の300mm半導体ウェハー対応R&Dセンター誘致に成功したこともあって、最近オルバニー地区におけるナノテクへの取組みが注目を集めつつある。
本稿では、本年9月11~13日にオルバニー郊外で開催された「Albany Symposium 2002 on Global Nanotechnology」の概要報告をベースに、主に半導体分野におけるナノテクの動向とニューヨーク州における取り組みについて概観してみたい。
なお、上記シンポジウムの取材は、JETROニューヨーク事務所(JEITAニューヨーク駐在員)の同僚である石井伸治氏とともに行った。
1.Albany Symposium 2002 on Global Nanotechnology
9月11~13日、ニューヨーク州の州都オルバニー(Albany)郊外にて、「The Global Business of Semiconductors & Nanotechnology」をテーマとするシンポジウムが開催された。
このシンポジウムは半導体分野におけるナノテクノロジーの事業化に焦点を当てたものであり、ニューヨーク州立大学オルバニー校(SUNY/UAlbany)の関連組織Albany NanoTechとオルバニー地区の経済発展を目的とする非営利団体Center for Economic Growthの主催により、International SEMATECHのBob Helms社長兼CEOを議長として、昨年に引き続き開催されたものである。
昨年の本シンポジウムにニューヨーク州のGeorge Pataki知事が出席して以来、ニューヨーク州とInternational SEMATECHは次世代の300mm半導体ウェハー対応のR&Dセンター建設について協議を進め、今年7月18日に総額3.2億ドルを投資してUAlbany構内に同R&Dセンター(International SEMATECH North)(以下ISMTN)を設置することで基本合意に達していた。(図表1)
図表1 International SEMATECH Northの概要
- International SEMATECHとUAlbanyは、超紫外線(EUV)リソグラフィに関するR&D推進のためInternational SEMATECH North(ISMTN)と呼ばれる戦略的提携に向けて協議を始めることで合意。
- ISMTN計画への投資額は5年間で3.2億ドル。
- International SEMATECHがISMTNの技術的な計画の明確化、実行、管理、人員配置を担当し、UAlbanyは施設提供と資金的支援を実施。経営幹部の派遣とInternational SEMATECHによって決定される設備や材料の調達は、両者で分担。
- ISMTN支援のため、ニューヨーク州は2.1億ドル(既に発表され2002-2003年度の州予算に計上されているCenter of Excellence in Nanoelectronics at Albanyの300mmウェハー対応研究予算0.5億ドルを含む)を支出。一方、International SEMATECHとそのメンバー企業(IBMを含む)は1.93億ドルを支出。
- International SEMATECHはAlbanyで250名の研究者を雇用。
|
(出展: 2002年7月18日の報道発表から作成)
[ 参考 ] International SEMATECHとは:
前身のSEMATECH(Semiconductor Manufacturing Technology)は、日米半導体摩擦が激化する中で米国の半導体産業の国際競争力を回復するため、日本の1970年代の超LSI技術研究組合をモデルに1987年に国防総省(DOD)と米国半導体業界が共同出資して設立した共同研究コンソーシアム。1990年代に日米の市場シェアが再逆転したことから1996年に直接的な政府支援が打ち切られ、1998年には半導体分野における国際連携の必要性の高まりを受けて、現代(韓)、ジーメンス(独)、フィリップス(蘭)等の外国企業も参加して子会社International SEMATECHが設立された。その後、2000年にSEMATECHは正式に名称をInternational SEMATECHに改めた。現在、テキサス州オースチンに本拠を置き、リソグラフィ、光学、材料等に関する先進的技術開発や生産技術改善に取り組んでいる。
ナノテクノロジーに対する関心の高まりに加え、こうした大規模投資に対する期待もあって、今年の本シンポジウムにも、半導体メーカー、素材・設備ベンダー、関連ベンチャー企業、連邦・州・地方政府、大学、銀行、ベンチャー・キャピタル、エンジェル投資家、法律事務所などの関係者約260人が参加した。
それでは以下に、シンポジウムの概要報告をベースに、主に半導体分野におけるナノテクの動向とニューヨーク州における取り組みについて概観する。
2.ナノテクと半導体
まず、ナノテクの定義及びナノテクと半導体の関係について頭の整理をしておきたい。
ナノテクノロジーとは、シンポジウムで講演を行った国立科学財団(NSF)のナノテク上級アドバイザーMihail Roco氏によると、「微小構造に起因する根本的に新しい性質・機能を有する材料、素子、システムを創造するための、概ね1~100nm領域における原子、分子、超分子レベルの作業」である。
この定義のポイントは「根本的に新しい性能・機能」という部分で、要するにナノテクとは、微小構造のサイズが単分子(概ね1nm前後というオーダー)の倍数として考慮できる領域において発現する特性を活用するという点で、従来の微細加工の単なる延長ではなく、政府が共通的基盤的技術として積極的に取り組むべき分野である、との意味が込められている。
図表2 ナノテクノロジーとは
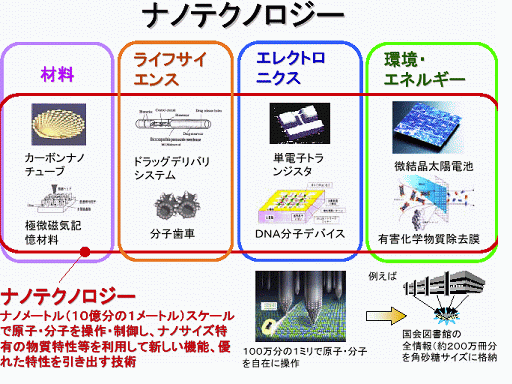
(出展: 総合科学技術会議)
図表2からもわかるように、ナノテクは、材料、エレクトロニクス(半導体を含む)、医薬品、化学などの分野への応用を含む幅広い技術であるが、エレクトロニクスへの応用(ナノエレクトロニクス)は、材料への応用(ナノマテリアル)などと並んで大きな市場になると期待されている。
ナノテクには、微細加工技術が進展しナノ領域に入ってくる「トップダウン・ナノテク」と、原子レベルの材料創製技術に基づく「ボトムアップ・ナノテク」があるが、半導体では現在、線幅0.13μm(130nm)の製品が量産されており、トップダウンではナノテクの領域に入りつつあると言うことができる。
3.半導体産業から見たナノテクの位置づけ
シンポジウムにおいて、IntelのAlan Allan氏、International SEMATECHのDave Anderson氏、テキサス大学ダラス校のDonald Hicks氏など多くの半導体業界関係者は、半導体はこれまでムーアの法則(半導体の集積度は18~24か月で2倍になる)に従って性能を向上させることで用途を広げ売上を指数関数的に増大させてきたが、エレクトロニクス製品の売上の伸び率が鈍化傾向にあること、エレクトロニクス製品のコストに占める半導体の比率が頭打ちになってきていること、製品寿命が短くなり価格下落が早くなってきていることなどから、1995年頃を境に半導体の売上の伸び率は鈍化しており、半導体産業は成熟しつつあるのかもしれないと指摘した。
(余談になるが、こうした半導体業界関係者の危機感に比べ、あるウォールストリートの投資銀行や某地区の連邦準備銀行(FRB)の講演は、「半導体業界は現在非常に厳しい経済状況下にあるが、潜在成長率は現状より高いはずであり、シリコンサイクルを考慮すれば2003年には緩やかに回復するだろう」といった楽観的なものであり、対照的であった。)
International SEMATECH会長兼CEOのBob Helms氏は、「こうした経済的制約下においても半導体業界が発展を続けるためには、加工線幅の微細化に関するロードマップに沿って技術革新を続けることが不可欠であるが、最近使われ始めた193nmの露光光源(フッ化アルゴン)から2006年頃と予想される157nm(フッ素ダイマー)や2009年頃と予想される13nmの極紫外線(EUV)への移行が円滑に行われる保証はなく、ウェハーサイズ拡大と微細加工化というロードマップに依存するリスクは増大している。したがって、我々は微細加工技術を引き続き追求する一方で、新メモリ技術などオフ・ロードマップ技術への期待を高めているのであり、ナノ領域の新材料創製技術などナノテクによるブレークスルーが期待されている」と、半導体業界から見たナノテクの位置づけを説明した。
また、IBM上級副社長のJohn Kelly氏は、「加工線幅が50nm以下の時代になるとシリコンではトランジスタの性能向上は難しくなるだろう。その解決策の一つとして、最近ナノチューブの活用への注目を高めている」と、ナノテクへの期待を具体的に述べた。
こうした見方は、2000年にクリントン前大統領が打ち出した「国家ナノテク戦略(National Nanotechnology Initiative:NNI)」にも反映されている。2002年6月に公表されたNNIの年次報告書(http://www.nano.gov/nni03_aug02.pdf)では、ナノテクのエレクトロニクス・コンピュータ分野へのインパクトについて、以下のように記述されている。
「米国半導体工業会(SIA)は、情報処理素子における微細化、速度及び低電力化の継続的改善のためのロードマップを策定している。現行のSIAのロードマップ(http://public.itrs.net/Files/2001ITRS/Home.htm)は概ね2016年までの将来を見通しており、その時までには重要な意味を持つ部位のサイズ(ゲート長)がナノ構造素子と呼ぶのに十分な9nm程度の小ささになっているだろうと見積もっている。さらに重要なのは、2001年版ロードマップではいくつかの分類の半導体素子で将来の製造技術の見通しが立っていないとされていることである。1999年版で初めて「Red Brick Wall(赤いレンガの壁)」と記述された際には、2005年にはこうした技術的な壁に当たるかもしれないと予想されたが、2001年版ロードマップでは、2003年には「Red Brick Wall」の一部に当たるかもしれないとされている。今や情報技術分野における継続的進歩の最先端は明らかにナノスケールの時代に入っており、情報技術に適用されるナノスケールの科学技術の基礎・応用両面での研究が従来にも増して必要になっている。」
4.国際的なナノテクR&D競争の現状
ここで、米国連邦政府によるナノテクノロジー戦略と、ナノテクR&Dに関する国際的競争の現状について簡単に触れておこう。
ナノテクは、上述の定義等からもわかるようにその目指しているもの自体はそれ程目新しいものではなく、日本でも旧通商産業省や旧科学技術庁によって国家プロジェクトとして関連のR&Dが行われるなど古くから取り組みが行われてきた。
こうした中で、よく知られているように、2000年にクリントン前大統領が「国家ナノテク戦略(National Nanotechnology Initiative:NNI)」を打ち出してから、ITやバイオテクノロジーと並んでナノテクが戦略的技術分野として一躍脚光を浴びるようになったのである。
NNIは、国家科学技術会議(NSTC)の技術委員会Nanoscale Science, Engineering, and Technology小委員会(NSET)による総合調整の下、全米科学技術財団(NSF)、国防総省(DOD)、エネルギー省(DOE)など16の省庁・機関によって推進されている。
NNIの内容や進捗状況については、NSETの事務局であるNational Nanotechnology Coordination Office(NNCO)が年次報告書としてとりまとめて公表している。2002年6月に公表された最新の年次報告書(http://www.nano.gov/nni03_aug02.pdf)によると、米国連邦政府のNNI予算は、2001年度実績4億6,430万ドル、2002年度見込6億440万ドル、2003年度要求7億1,020万ドルと順調に伸びている。また、その分野別内訳を見ると、基礎分野では素子・システムなどが、また応用分野ではナノエレクトロニクスなどが、大きな位置づけを占めていることがわかる。(図表3、4)
図表3 NNI予算の省庁別内訳
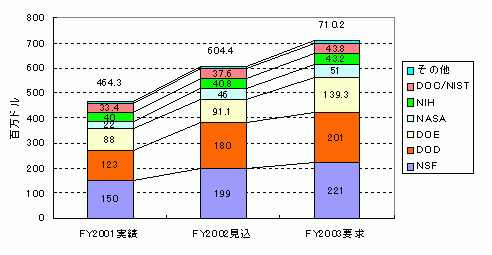
(出展: NNI年次報告書から作成)
図表4 NNI予算の分野別内訳
(単位: 百万ドル)
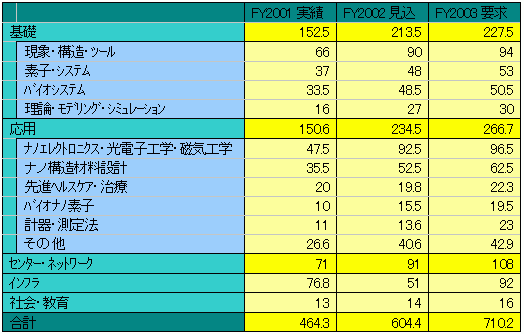
(出展: NNI年次報告書から作成)
しかし、このようにナノテクに力を入れているのは米国だけではない。
シンポジウムの講演でNSFのRoco氏は、各国政府による2002年度のナノテクR&D支出は日本6.5億ドル、米国6億ドル、西欧4億ドル、その他(韓国、台湾等)5.2億ドル、合計21.7億ドルに上り、1997年の4.3億ドルに比べ5年で5倍になったとして、ナノテクR&D分野で国際的に激しい主導権争いが演じられていることを指摘した。(図表5)
図表5 各国政府のナノテクR&D予算
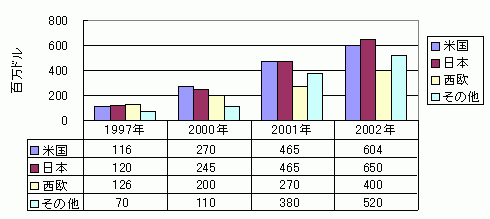
(出展: Roco氏講演より作成)
また、Global Emerging Technology Instituteの和賀三和子氏はシンポジウムにおける講演の中で、日本のMIRAI、HALCA、ASUKA、ASPLAといった半導体関連のナノテク・プロジェクトに加え、韓国、台湾などの動向を紹介し、アジア地域においてナノテクへの投資が急増していると指摘した。
こうした状況を踏まえNSFのRoco氏は、ナノテク分野では米国は他のバイオ、IT、宇宙開発、核開発等の分野のように主導的立場を確立できていないと述べ、暗に米国政府によるナノテクR&D予算の大幅増額の必要性を指摘した。
なお、今回のシンポジウムへのアジア系の参加者は、講演を行った和賀氏の他、日系企業ではエレクトロニクス大手1社、半導体製造装置大手2社(いずれも米人)、投資企業1社(米人)及びJETROで、韓国、台湾、中国系の企業からの参加は確認できなかった。(ただし、在米韓国人、中国人による在米ベンチャー企業が参加していた)。また、在ニューヨーク中国総領事館から参事官が参加し、注目を集めていた。
5.半導体業界における中国脅威論
今回のシンポジウムでは、近年のトレンド(?)である「中国脅威論」も聞かれた。
米国半導体工業会(SIA)のDaryl Hatano氏はシンポジウムの講演で、世界的なIT不況下にあって中国の半導体市場は2001年に30%成長を遂げ(世界市場の13%)、中国政府の非常に魅力的な投資誘致政策もあって半導体業界の設備投資が中国に向かっていると指摘し、半導体業界における中国脅威論を展開した。
また、Hatano氏は、米国政府は半導体業界の米国内における投資を促進するため、①海外子会社の利益を懲罰的課税なしに米国に移転できるようにすべき、②企業誘致のための非課税地方債(Industrial Revenue Bond)の限度額を廃止すべき、③ハイテク特区を創設すべき、④州税軽減の効果が連邦税の増加によって薄められない仕組みにすべき、といった具体的な提言を行った。
Hatano氏の対中国観は半導体事業に関するものであり、ナノテクに関するものではない。しかし、ナノテクのユーザーである半導体の製造で中国が巨大なポテンシャルを持っていること、またHatano氏が指摘するように中国の工学部卒業生が日米の約10万人に対し既に倍の約20万人に達していることなどを考慮すれば、将来ナノテクにおいても中国が重要なプレイヤーになる可能性は高いと言えるであろう。
6.オルバニーでナノテク?
正直に言って、ニューヨーク州に住んでいる私でさえ、オルバニーをナノエレクトロニクスのCenter of Excellenceにするという構想を最初に耳にした際の印象は、「オルバニーでナノテク?」というものであった。(実際、今回のシンポジウムでも、地元関係者以外と話をすると同様のことを口にする人がいた。)
そこで、以下にオルバニーの近況について見てみることとしたい。
ニューヨーク州の州都オルバニー(Albany)は、ニューヨーク市の北約230km、車で約2時間半の所にあり、2000年時点の人口は近郊も含めると90万人弱(全米56位)を有する地方中核都市である。(図表6)
図表6 米国北東部とニューヨーク州都オルバニー
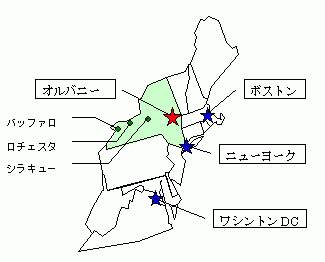
しかし、ニューヨーク州の南東端にある「世界の首都」ニューヨーク市から見ると、州都オルバニーを含めた「ニューヨーク市以外」の州北西部(アップステートと総称される)は、歯に衣着せずに言うと「無視され」「忘れられた」地域ということになってしまう。
したがって、ニューヨーク州にとって、オルバニー近郊を含む州北西部の振興は大きな政治的課題の一つであり、本年11月に州知事選を控える現Pataki知事にとってハイテク産業誘致は是非とも実現させたいテーマだったのである。(オルバニーの地元紙Times Unionは、Pataki知事の今回のInternational SEMATECH North誘致成功は彼の政敵の最大の攻撃材料の一つを封じ込めることになるだろうと報じている。)
Pataki知事は、ニューヨーク州にハイテク企業を誘致するための総額10億ドル規模の構想を打ち出し、オルバニー(ナノエレクトロニクス)、バッファロー(バイオインフォマティックス)、ロチェスター(フォトニクス)、シラキュース(環境システム)などのCenter of Excellence化を進めることとし、各地にSTAR(Strategically Targeted Academic Research)センターやCAT(Center for Advanced Technology)などを設置した。
こうした中で、オルバニーでは、UAlbanyに設置されたAlbany NanoTechを中心として、UAlbanyのSchool of Nanoscience and NanoengineeringやInstitute for Materialsなどの組織と、州政府の支援によるNanoelectronics and Optoelectronics Research and Technology CenterやCenter for Advanced Thin Film Technologyなどの研究所が連携することによって、ナノエレクトロニクスに関するCOE化が推進された。
オルバニー近郊には、元々GEのシリコン開発・製造・販売部門GE Siliconesの本社やIBMのコンピュータ及びマイクロエレクトロニクス事業部(かなりニューヨーク市寄りだが)などの企業が立地している。そこで、地元ではオルバニー近郊を「Tech Valley」と名付け、ハイテク企業の誘致による地域振興を図った。
このようにして、Pataki知事は今回のISMTN誘致を実現させたわけである。つまり、今回の成功は、UAlbanyを中心としたナノエレクトロニクスのCenter of Excellenceの建設やTech Valleyの振興といった目標に向けた大きな前進であり、地元の期待は非常に大きいものがある。(New York Times紙は、今回のISMTN誘致の発表を受けて、「何年か前に地方政府が緑深いハドソン川流域をTech Valleyと呼んだ時は相当無理しているなという感じがしたし嘲笑する人も多かったが、ISMTN建設が発表された今、もう嘲笑する人はいない」と多少茶化して記している。)
さらに、Pataki知事は最近、ISMTNからのスピンオフ企業などのためにUAlbanyに隣接する300エーカー(120万㎡)の州政府事務所敷地に新しいテクノロジーパークを建設することを発表している。
このような州政府の熱心なハイテク企業誘致は、もちろん他州も同様である。NSFのRoco氏によると、半導体関連に限らずナノテク全般で見ると、南カリフォルニア、ペンシルバニア、テキサス、バージニア、デンバー、シリコンバレー、サンディエゴ、ミシガンなどの地域でも、それぞれ集積地域化を目指した計画が進められているという。
しかし、今回のニューヨーク州のコミットメント2.1億ドルは、州政府としては最大規模のものである。(図表7、8)
図表7 ナノテク関連の地域的連携
- Nanotechnology Alliance in Southern California www.larta.org/Nano
- Nanotechnology Franklin Institute, Pennsylvania www.sep.benfranklin.org/resources/nanotech.html
- Texas Nanotechnology Initiative www.INanoVA.org
- Denver Nano Hub www.nanobusiness.org/denver.html
- Sillicon Valley, San Diego and Michigan Nano Hubs
|
図表8 ナノテク拠点設置に対する州の関与
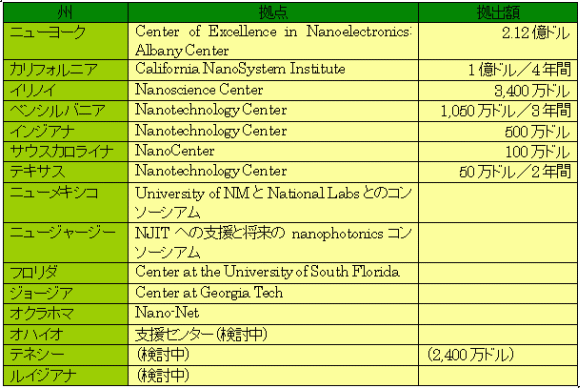
(Roco氏講演より作成)
なお、このようなハイテクによる地域振興の成功例としては、SEMATECHの最初のR&D施設が建設された地であるテキサス州オースチンが有名である。
テキサス州の州都であるオースチンには、以前からテキサス大学オースチン校やIBM、TI、Motorola、DELLなどの企業が立地していたが、1982年にMCC(Microelectronics and Computer Consortium)が、また1988年にSEMATECHが誘致され、さらにATI(Austin Technology Incubator)などのベンチャー企業支援組織が設立されて、1990年代にハイテク企業の集積地として大きく発展した。現在、オースチンには約2,000社のハイテク企業が立地しており、その発展のメカニズムは、いわゆる「オースチン・モデル」として知られている。(オースチンの発展におけるテキサス大学、MCC、SEMATECHの役割は十分検証できないとの説もあるが。)
今回のISMTN誘致を受けて、地元オルバニーでは「オルバニーは第二のオースチンになれるかもしれない」という論調が目立った。
しかし、オルバニーが実際にオースチンと同様の成功を収めることができるかどうかについては未知数であろう。現下の厳しい経済環境下で、しかも半導体産業の投資が中国を中心とするアジア地域に重点を移している中で、ISMTNの誘致が地域経済に及ぼす影響は限られるのではないかとの指摘もある。今回のシンポジウムの参加者からは、「オースチン・モデル」に対する「オルバニー・モデル」はまだ確立されておらず、これから作られることになるのであろうとのコメントも聞かれた。
7.大学の役割
オルバニーにおけるCenter of Excellence建設を通じたハイテク企業誘致のため、UAlbanyは大きな役割を果たしている。
UAlbanyの関連組織Albany NanoTechの敷地内には、既に原子間力顕微鏡(AFM)や超音波力顕微鏡(UFM)、IBM製のスパコンといった先端的R&D装置に加えて、クラス10のクリーンルーム内に0.18μmレベルの200mmウェハー対応のR&D施設が設置されており、現在、本年10月及び来年10月完成予定の300mmウェハー対応R&D施設2棟(インキュベーション・スペースを含む)を建設中である。
図表9 Albany NanoTech

(正面が200mmウェハー対応施設、左が本年10月完成予定の300mm対応施設)
(出展: 石井伸治氏撮影)
UAlbanyのKaren Hitchcock学長はシンポジウムでの講演の中で、技術革新に関する大学をとりまく環境は変化しており、政府支出による基礎研究を大学が発展させ産業界が実用化するという従来のリニアモデルではなく、大学の研究者とISMTNのような大型施設とビジネス・インキュベータが同居することによって技術革新と実用化を加速化するというコロケーションモデルが重要になっていると指摘し、UAlbanyもナノテクの実用化に積極的な役割を果たしていくことを表明した。
Hitchcock学長はまた、Albany NanoTechの200mmウェハー対応R&D施設がSchool of Nanoscience and Nanoengineeringによって教育用に利用されていることを挙げ、こうした先進的施設を人材教育に利用している大学は他に例を見ないとして、この分野におけるUAlbanyの優位性を強調した。
8.ナノビジネス
シンポジウムでは、ナノテクの事業化(ナノビジネス)の現状と展望についても紹介された。
2001年10月に設立され既に200社のメンバーを有するナノビジネスの業界団体NanoBusiness Allianceの創設者・専務Mark Modzelewski氏によると、ナノビジネスの世界市場は2006年に2,000億ドルに達するとも、10年余りで1兆ドル規模になるとも、また既に3,000億ドルに達しているとも言われる。また、エレクトロニクス関連では、カーボンナノチューブを活用した素子、有機ナノエレクトロニクス、Magnetic RAM(MRAM)、量子コンピュータ、光スイッチなどが有望だという。
ただ、Modzelewski氏によると、IBMやGMなどの大企業がナノテクに熱心な一方で、ベンチャー企業で成功している例はVeeco、Zyvex、C Sixtyなどまだ少ない。ベンチャー・キャピタルがいわゆる技術の死の谷(Death Valley)を乗り越える有望なビジネスモデルを持つ企業に出会えない一方で、企業内ベンチャーやエンジェルが一定の役割を担っているという。
ニューメキシコ大学のSteven Walsh氏は、トップダウン・ナノテクは従来のマイクロエレクトロニクスの延長に留まっており、一方でボトムアップ・ナノテクのような革新的技術が大きな市場を生むには時間がかかるとして、ナノビジネスは一夜にして花開くものではないと指摘した。
シンポジウム会場からは、「ナノテクは最近盛り上がっているが、エレクトロニクス・半導体業界は従来から様々な努力を積み重ねてきており、目新しいものは少ない。」「いや、ブレークスルーは突然やってくるものだ。」といった様々な声が聞かれた。
おわりに
今回のシンポジウムは、成長分野としてのナノテクに対する期待の高まり、半導体産業の置かれた厳しい経済環境、興隆するアジア諸国との連携・競争戦略の模索、といった様々な要素を併せ持つ、まさに「総括の難しい」シンポジウムであった。
ともかく、Pataki州知事の強力なリーダーシップのもとに急速にナノエレクトロニクスのCOE化を進めつつあるオルバニー地区について、第二のオースチンになれるか否かは未知数ながら、今後注目していく必要があるであろう。
ナノエレクトロニクス分野では、一般的には日本が米国に比べ優位に立っていると言われていたが、2001年3月に取りまとめられた三菱総研の「米国ナノテクノロジー分野研究開発の推進戦略に関する調査」(http://www8.cao.go.jp/cstp/project/nanotech/index.htm)によると、この分野で米国が急速に差を縮めており、量子デバイスや量子コンピュータなど一部では日本を引き離し始めているという。
今回のシンポジウムでは、半導体分野におけるナノテクに関する詳細な技術的講演はなかったが、本分野においては、トップダウン・ナノテク(一層の微細加工化の追及)とボトムアップ・ナノテク(新素子の実用化)との間にまだ少し距離があり、いつ頃どのような形で前者から後者への移行が行われるのかが関係者の重大な関心事であることが伺えた。そして、半導体業界の将来を見通してボトムアップ・ナノテクでも着々と手を打とうとする米国の姿が印象的であった。
激しい国際競争と厳しい不況の中で生き残りをかけて業界再編に取り組んでいる日本の半導体業界にとって、遠からず訪れるであろうトップダウン・ナノテク領域で巻き返しを図ることが喫緊の課題であることは間違いないのであるが、ある日突然ボトムアップ・ナノテクによるブレークスルーが訪れ、気がついたら大きく引き離されてしまっていた、ということにだけはならないよう祈りたい。
(了)
【 参照URL 】
Albany Symposium 2002: http://www.albanysymposium.org/
ニューヨーク州立大学オルバニー校(UAlbany): http://www.albany.edu/
Albany NanoTech: http://www.albanynanotech.org/
Center for Economic Growth: http://www.ceg.org/
International SEMATECH: http://www.sematech.org/
総合科学技術会議: http://www8.cao.go.jp/cstp/project/nanotech/index.htm
国家ナノテク戦略(NNI): http://www.nano.gov/
米国半導体工業会(SIA): http://www.semichips.org/
ニューヨーク州科学・技術・学術研究局(NYSTAR): http://www.nystar.state.ny.us/
Tech Valley: http://www.techvalley.org/
NanoBusiness Alliance: http://www.nanobusiness.org/
http://www8.cao.go.jp/cstp/project/nanotech/index.htm(図表2関連)
本稿に対する御質問、御意見、御要望がございましたら、Ryohei_Arata@jetro.go.jpまでお願いします。
(C)Copyright JEITA,2002
|