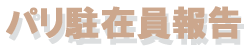
【 2001年6月号 】
欧 州 動 向
~ユーレカ計画におけるIT分野の取り組み~
|
Ⅰ.ユーレカ計画におけるIT分野の取り組み
前号ではEUフレームワーク計画におけるIT分野の取り組みについて解説した。今回はフレームワーク計画とともに、欧州の2大研究開発支援スキームであるユーレカ(EUREKA)計画におけるIT分野の取り組みについて解説する。
1.ユーレカ計画の概要
ユーレカ計画は、フランスの提案に提案に基づき1985年に開始された。フレームワーク計画は1984年に開始されており、双方とも同時期に開始されている。ユーレカ計画への加盟国は、発足当初は17ヶ国及び欧州委員会であったが、現在では、EU15ヶ国、EFTA3ヶ国、中東欧諸国8ヶ国(チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、リトアニア、ラトビア)、ロシア、トルコ、イスラエルの29ヶ国に増加している。
EUフレームワーク計画が市場前段階にある研究開発に対する支援スキームであるのに対して、ユーレカ計画は企業ニーズを反映した市場指向性のある技術開発に対する支援スキームであり、相互補完的な関係となっている。もっとも、現在の情報通信分野の研究開発では、研究開発のアイデアから市場化までの時間的距離が短いため、本分野に限って言えば両計画の支援対象フェーズに市場前段階と市場指向性という明確な住み分けが存在しているかどうかは疑問なところではある。
プロジェクトの立ち上げを希望する民間企業は、欧州内のパートナーと自らコンタクトすると同時に、自国のユーレカ事務局(多くは産業省や研究省に置かれている)を通じ、政府レベルでの共同研究開発プロジェクトが準備される。この準備には各国政府からその国のプロジェクト・メンバーに対する助成決定も含まれる。こうした準備を受け、ユーレカ加盟国の各コーディネート事務局がラベル認定プロジェクトを推薦し、ユーレカ・ハイレベル・グループ会合で承認されればユーレカ・ラベルが認定される。これらのプロジェクトが毎年6月終わりに開催されるユーレカ閣僚理事会で公式に発表される。このように、民間企業等のプロジェクト参加者の発意によりプロジェクトが形成されることが、ユーレカ計画が“ボトムアップ方式”と言われる所以である。計画開始以来、プロジェクト数は実施中674件、終了1,041で、合計1,715件に達している(2000年5月末現在)。
各プロジェクトへの助成は、各国政府それぞれの助成制度によってなされる。このため、補助率等は一定ではない。本稿執筆時点で2001年の各国におけるユーレカ計画に適用される助成制度に関して、同計画のホームページから得られる情報(英、独、オーストリア、ベルギー、ノルウェー、アイスランド、スロヴェニアの助成制度が記載されている)では、補助率は概ね50%以下となっている。なお、実際に個別プロジェクトにどれだけの補助率が適用されているかは公式なデータがない。
ユーレカ計画は、表1に示す9つの技術分野に分けられて実施しているが、活動規模では情報技術が全体の6割以上と他を圧倒している。
表1 ユーレカ計画の対象技術分野
| ・情報技術 |
| ・通信技術 |
| ・レーザー技術 |
| ・医療/バイオテクノロジー |
| ・新素材 |
| ・ロボット及び生産自動化 |
| ・エネルギー技術 |
| ・環境技術 |
| ・運輸技術 |
以下では、ユーレカ計画におけるIT分野として、情報技術と通信技術の現行プロジェクトについて解説する。
2.情報技術プロジェクト
情報分野でのユーレカ・プロジェクト数は現在、終了したものを合わせて累計285件である。このうち終了プロジェクトが173件、2000年6月の閣僚理事会までに発表されて実施中のものが95件、2001年6月の閣僚理事会での発表を待ってラベル認定を受けているものが17件である。この他、未認定のプロジェクト提案段階のものが4件、アイデア提示段階のものが11件、呼びかけ段階のものが3件ある。
なお、実施中のプロジェクト95件の中には、プロジェクト自体はすでに終了していても最終レポートの提示がないためプロジェクト登録上は“実施中”の扱いになっているものもある。(1993年に開始され、欧州の周辺機器産業のレベル・アップを目指したJEEPがその例で、プロジェクトは2000年1月1日に終了しているが、実施中として登録されている。)
<実施中のプロジェクトの規模>
ここでは登録上「実施中」の扱いを受けている95件のプロジェクトについて、ユーレカ計画のホームページから参照できるプロジェクト紹介(project form)に記されているプロジェクト予算をもとに、プロジェクトの規模を分析する。
これら95件のプロジェクト予算の合計額は104億9,146万ユーロ(参加者の自己負担及び政府助成金)に達する。すでに数年前に開始されたものから、2008年まで実施が予定されるものまでを含み、複数年度にわたって使用される予算であって単年度の予算ではないため、単純にフレームワーク計画との比較はできないが、かなりの規模である。
プロジェクトの平均規模は合計額を95で割れば、1億1,000万ユーロ強となり、フレームワーク計画のISTプログラムにおける研究技術開発プロジェクトの平均規模である364万ユーロの約30倍と大きい。ただし、この先に説明するようにユーレカ計画では、個々のプロジェクトによって規模が大きく異なることに留意する必要がある。表2に、95件の実施中のプロジェクトを規模別に分類してみた。プロジェクト規模には数十億ユーロから百万ユーロ以下のものまで、極めて大きなばらつきがある。
表2 ユーレカ計画の情報技術プロジェクトの規模の分布(単位:万ユーロ)
| プロジェクト規模 (単位:万ユーロ) |
プロジェクト数 |
| マイクロ・プロジェクト |
( ~ 100) |
23 |
| 小規模プロジェクト |
( 100~ 200) |
24 |
| 中規模プロジェクト |
( 200~ 1,000) |
31 |
| 大型プロジェクト |
( 1,000~10,000) |
12 |
| クラスター |
(10,000~ ) |
5 |
| 合 計 |
95 |
100万ユーロ以下のプロジェクトは全体の約1/4、100万~200万ユーロのプロジェクトは全体の約1/4、200万~1,000万ユーロのプロジェクトは全体の約1/3、1,000万ユーロ以上のプロジェクトは全体の約1/6を占めている。ユーレカ計画のプロジェクトの相当割合は、フレークワーク計画のISTプログラムのプロジェクトよりも規模が大きいことが分かる。
(1)マイクロ・プロジェクト
100万ユーロ以下のプロジェクトは、“マイクロ・プロジェクト”ととも呼ばれ、ユーレカ・ラベルの認定など国際共同研究の運営に伴うコストの割に、成果から期待される経済効果が少なすぎると批判される反面、中小企業など国際共同活動への参加が少ない組織が自らプロジェクトを提案できる貴重な機会を提供しているとする意見もある。
なお、このグループにはアンブレラ・プロジェクトであるMULTIMEDEAが含まれている。アンブレラ・プロジェクトは、特定テーマにおけるプロジェクトの立ち上げやコーディネートを支援する活動であり、研究開発活動そのものに対する助成は行わない。このためプロジェクト予算はゼロとされている。これを例外として除けば、マイクロ・プロジェクトの中でも最小のものは、INFRADOKとEUROFISHEXCHANGEの2つで、プロジェクト予算はともに27万ユーロである。前者はメディア・データのインフラや異なる種類フォーマットのデータをPCベースのデジタル・データ・バンクに変換するドキュメンテーション・システムの開発プロジェクトである。後者は、鮮魚の品質データの標準化を目指した魚類の電子商取引に関するプロジェクトである。
これらのマイクロ・プロジェクトの平均規模は74万ユーロである(MULTIMEDEAを除く)。
(2)小規模プロジェクト
100万~200万ユーロのグループのプロジェクトの平均規模は140万ユーロである。この規模のプロジェクトの例としては、建設業における従業員に対する機材・製品(木材製品)の説明のためのマルチメディア技術を開発するTWIG2000、教員・学生用のマルチメディア教育プログラムの開発のためのTIM7、個人利用のマルチメディア・コンテンツ検索用データベース・システムの開発のためのCULT-BASEなどがある。
(3)中規模プロジェクト
200万~1,000万ユーロの規模のプロジェクトのグループでは、全体の31件のうち500万ユーロ以下のプロジェクトが23件と約3/4を占めている。500万ユーロを超えるあたりからプロジェクト数が少なくなっていることが分かる。
200万~500万ユーロのグループのプロジェクトの平均規模は306万ユーロで、プロジェクトの例としては、二次元イメージとバーコードの読みとりを行う2Dスキャナーの開発を目指すIRIS(309万ユーロ)、生化学と免疫学の双方に利用可能な自動分析評価装置の開発を目指すPEGASE(308万ユーロ)などがある。
500万~1,000万ユーロのグループのプロジェクトの平均規模は600万ユーロで、プロジェクトの例としては、職業専門用語や技術専門用語などの知識を大規模に管理する知識管理アーキテクチャーの開発及びその知識集約型生産プロセスへの統合を目指すITMC(652万ユーロ)や、バーチャル家具市場の設置のためのOVMF(592万ユーロ)などがある。
1,000万ユーロを超える17件のプロジェクトについては、1,000万ユーロ強から40億ユーロに達するものまで広範囲にわたる。これらは、表3のように、①1,000万ユーロ~2,000万ユーロ程度、②数千万ユーロ台、③一億ユーロ台、④数十億ユーロ台の4つのグループに分けることができる。このうち、①及び②を大型プロジェクト、③及び④をクラスターとして以下に述べる。
表3 情報技術分野の大型及びクラスター・プロジェクト(単位:万ユーロ)
| プロジェクト略称 |
予算総額 |
備 考 |
MEDEA+
ITEA
MEDEA |
400,000
320,000
200,000 |
実施中、クラスター、MEDEAの後継
実施中、クラスター
2001年1月1日終了、クラスター |
EURIMUS
PIDEA |
40,000
40,000 |
実施中、クラスター
実施中、クラスター |
JEPP
PEACEMACHINE |
8,800
5,000 |
2000年1月1日終了
実施中 |
NESSI
ISOCIAT
BLUESPOT
VSI
REMOD
IKF
FACIAL
SIMBA
ON-AIR
COMEDIA
|
2,100
2,065
2,001
1,940
1,693
1,414
1,104
1,102
1,093
1,015 |
2001年1月1日終了
2001年4月1日終了
実施中、REMODの後継
実施中
2000年1月1日終了
実施中
2000年6月1日終了
実施中
2001年4月1日終了
実施中
|
(4)大型プロジェクト
大型プロジェクトには以下のようなプロジェクトがある。
COMEDIAは服飾デザインを支援するソフトウェアの開発、ON-AIRはISDN及びGSM移動体通信ネットワーク上で動画をリアルタイム伝送するために必要な技術プラットフォームの開発、SIMBAは水深500mの深海オフショア用の解析装置(海底地図、海底映像、地震学的分析、等)の開発、FACIALは、ファジー理論を家電用アプリケーションに応用するためのソフトウェアの開発である。アプリケーション・ソフトウェア開発のためのプロジェクトとしては、1,000万ユーロ程度の規模が上限のようである。
IKFは分散型インフラとサービス・システムの開発、REMODは書き込み可能な多層光ディスクの開発、VSIはシリコン回路の積層システム技術の開発、BLUESPOTは光ディスクの開発プロジェクトとしてREMODを受け継ぐ片面15G・両面28Gの光ディスクの開発、ISOCIATは製品ライフ・サイクルにおける市場動向への反応度を高める知識管理技術の開発、NESSIはマイクロエレクトロニクス関係の欧州研究開発プログラムの成果の中小企業への移転を図る技術移転プロジェクトである。後継プロジェクトのNESSI+は、2001年1月から開始され、次期閣僚会合での公表待ちの状況にある。
数千万ユーロ規模のプロジェクトとしては、周辺機器分野における欧州産業全体の技術レベルの向上を目指して1993年に開始されたJEEPと、バーチャル・ミュジーカルの制作実現に関するPEACEMACHINEの二つがある。前者は欧州の周辺機器メーカーを結集した共同プロジェクトであったが、2000年始めの終了以降、後継プロジェクトはない。PEACEMACHINEは技術開発コストの他、制作コストが多く含まれているように思われる。
(5)クラスター
1億ユーロを超えるプロジェクトには、4億ユーロのEURIMUSとPIDEA、20億ユーロのMEDEA、32億ユーロのITEA、40億ユーロのMEDEA+の5つがある。これらはいずれもユーレカ計画を代表するプロジェクトといえる。
これらの5つのプロジェクトは、上記で説明した(1)~(4)のプロジェクトの規模とは格段の差がある。これは、これら5つは“プロジェクト”と呼ばれるとはいえ、実際には一つの“プログラム”であり、多くのサブ・プロジェクトを通じて実施されているためである。例えば、EURIMUSの場合は最初から100以上のサブ・プロジェクトを予定して開始されている。このように多くのサブ・プロジェクトから構成される大規模プロジェクトを、ユーレカ計画では「クラスター」と呼んでいる。クラスターの概念には、大規模プロジェクトの準備を容易にするための対応が含まれている。数十に上るサブ・プロジェクトの個々の概要や見積もり予算を決定した上で大規模プロジェクトを立ち上げるには、大きな準備努力が必要となる。規模が大きくても柔軟な研究開発戦略が必要とされるIT関連の研究開発においては、このような積み上げ式の準備手法は不適切ともいえる。こうした事情に対応しつつユーレカというラベル認定の意味を維持するために、プロジェクトの大枠だけを決定し、それに対するラベル認定を行ったうえで、傘下のプロジェクトを決定・実施するのがクラスター方式である。このためITEAのような大規模プロジェクトでは、実施期間中、数次のサブ・プロジェクトの公募が予定されている。クラスターの概念は1998年からユーレカ計画で正式に採用されている。
ユーレカ・プロジェクトのうち規模の大きさでは、MEDEA+、MEDEA、ITEAの3つがそれぞれ40億ユーロ、20億ユーロ、32億ユーロと突出したスケールで実施されている。これらのうちMEDEA+は2001年からの8年計画、MEDEAは1997年からの4年計画、ITEAは1998年からの8年計画であり、一年あたりの規模は概ね同じである。MEDEAは、日米に対し遅れていた欧州の半導体技術レベルの引き上げを目指して開始されユーレカ計画の看板となったJESSIを引き継いだプロジェクトである。2001年1月から開始されたMEDEA+もMEDEAの後継としてJESSI以来のユーレカ計画の中核プロジェクトである。一方、ITEAは、ソフトウェア分野で米国に対する遅れを取り戻すため、特にミドルウェア分野での欧州の技術レベルの押し上げをねらっている。ITEAには欧州委員会の第Ⅲ総局も参加しており、半導体技術に関しての最初の大規模プロジェクトであったJESSIのような欧州全体の取り組みとなっている。このように、90年代後半から現在に至るまで、ユーレカ計画の情報技術分野では、マイクロエレクトロニクス分野におけるMEDEA(及びその後継プロジェクトであるMEDEA+)とソフトウェア分野におけるITEAが二つの柱となっている。
これらに続き4億ユーロ規模のプロジェクトとして、マイクロシステムに関するEURIMUSと、インターコネクションとパッケージングに関するPIDEAがある。いずれもクラスターの概念が導入された1998年に立ち上がったプロジェクトである。EURIMUSは、欧州全体では一定の市場規模を持ちながらも細分化されたセクターに関する技術であり、セクター全体の技術開発能力を結集して、関連分野における欧州の技術力の向上を狙ったものである。
以上のクラスター・プロジェクトで注意を引くのは、これらのプロジェクトにおけるメンバーの多くがプロジェクト間で共通していることである。 MEDEA+のプロジェクト・リーダーがMEDEAの時と同じように蘭フィリップスであるのは作業の連続性から当然だが、フィリップスはITEAのプロジェクト・リーダーでもある。フィリップスはEURIMUSにも参加している。フィリップスに限らず、仏トムソン、仏アルカテル、仏ブル、独シーメンス、独ボッシュ、エリクソン(スウェーデン)、ノキア(フィンランド)などはこれらのクラスターの3つ以上に参加している。また、公的研究機関でも仏原子力庁LTCIなど、同じ機関が複数のプロジェクトに参加している。このようなプロジェクト参加者の重複から、欧州の産業技術競争力の強化を目標にするユーレカ計画に相応しく、欧州を代表する大手企業や主要研究機関がネットワークを作って、複数の大規模プロジェクトを進めていることがうかがわれる。
《 認可済みプロジェクト 》
2000年6月末のユーレカ閣僚理事会以降、2001年6月の閣僚理事会における発表前にユーレカ・ラベルの認定を受けたプロジェクトはこれまでに17件ある。これらのうち大型プロジェクト以上の規模のものは、NESSIの後継プロジェクトであるNESSI+(2,862万ユーロ)のみである。
これまで説明してきたプロジェクトで読者の方もお気づきかもしれないが、ユーレカ計画の情報技術分野のプロジェクトの中には、純粋な技術開発プロジェクトの他に、特定分野でのアプリケーション開発も多く含まれているように思う。この背景としては、ユーレカ計画はプロジェクト参加者からのボトムアップ方式であるとともに、ユーレカ・ラベルの認定には個々の国の意図が大きく影響するため、欧州各国においてIT技術の名のもとに広い分野にわたる技術開発支援が行われていることが推測される。
3.通信技術プロジェクト
通信技術に関するプロジェクトの数は、情報技術に比べてかなり少なく、終了、実施中、認可済みの三種類を合わせて66件である。この内訳は、終了プロジェクト43件、実施中23件、認可済み1件である。このうち実施中として登録されているものの中には1999年及び2000年に終了したものが11件、2001年1月に終了したものが3件あり、これを考慮すれば現在進行中のプロジェクトは9件しかない。さらに、認可済みプロジェクトの数が少ないことを合わせて考慮すれば、通信技術におけるプロジェクトの数は今後増加しないことが予想される。これは、フレームワーク計画において情報技術プログラムと通信技術プログラムが一体化にされたように、現在では“情報”と“通信”の区別の必要性がなくなってきているため、情報技術にも関係する通信技術関連のプロジェクトが情報技術の枠内で扱われる傾向があるためと考えられる。
以下に、実施中の扱いを受けているプロジェクトについて説明する。
(1)マイクロ・プロジェクト
100万ユーロ以下のマイクロ・プロジェクトは7件で(全体の30%)、平均規模は53万ユーロである。このグループのプロジェクトの例としては、通信設備・機器周辺の電磁気影響を評価する手法を開発するSARSYS(54万ユーロ)がある。
(2)小規模プロジェクト
100万~200万ユーロの小規模プロジェクトは7件で(全体の30%)、平均規模は130万ユーロである。このグループのプロジェクトの例としては、デジタル・ネットワーク用の高品質の遠隔パワー・スイッチの開発を行うALTERN(135万ユーロ)がある。
(3)中規模プロジェクト
200万~1,000万ユーロのプロジェクトとしては、比較的規模の大きなものに、マルチメディア対応マルチ・ユーザ用ATM接続技術の開発を行うSMARTSWITCH(711万ユーロ)、インターネットとローカル・ネットワークへの次世代ワイヤレス接続のためのプラットフォーム技術に関するNOWIREGEN3(560万ユーロ)、高速・低電力エレクトロニクス用マイクロ冷却器の開発を行うDICOPAC(520万ユーロ)、世界の異なる時間帯の工場をネットワークで連結し24時間工場の実現を目指すROUND THE CLOCK(424万ユーロ)、xDSLを介したATM接続技術の開発を行うFLEXRATE(408万ユーロ)がある。この他、200万ユーロ規模ものとして、TETRA標準によるプロ用デジタル無線の携帯端末と基地局の開発を行うPDC(278万ユーロ)と、ホーム・シネマなどのマルチチャンネル音響システムに関するMEDUSA(268万ユーロ)がある。
(4)大型プロジェクト
大型プロジェクトとしては、1997年に開始された大衆家電端末間の家庭内ネットワーク技術とその標準化に関するプロジェクトCOMMEND(1億2,600万ユーロ)と、1993年に開始されたデジタル・オーディオ放送の標準化を目指したDAB(8,920万ユーロ)がある。DABは2000年1月1日、COMMENDは2001年1月1日に終了しており、通信技術に関しては、現在進行中の大型プロジェクトは存在しない。
(5)クラスター
通信技術分野にはクラスター・プロジェクトはない。
《 認可済みプロジェクト 》
唯一の認定済みプロジェクトPC RADARについてはproject formが発表されていないが、海洋利用のPCレーダーというタイトルからして、大きなプロジェクトとは考えにくい。
4.ユーレカ計画の今後の課題と方向性
ユーレカ計画は1985年に誕生して以来15年が経過したが、これを機にユーレカ計画の再活性化を目指した中期計画の作成の準備が1998年から進められてきた。特に1999年には外部独立専門家グループによるシナリオ評価レポートが提出され、閣僚理事会における決定を通じてユーレカを活性化するための明確な政治的コミットメントを求めていた。このような流れの中で、2000年6月のユーレカ閣僚理事会は「EUREKA 2000plus」と呼ばれるガイドラインを採択した。
ガイドラインでは、「ユーレカの使命」としてユーレカ計画の基本的存在意義を確認した後、「戦略的プロジェクトへの支援」、「中小企業の参加促進」、「中東欧の取り込み」、「世界的協力に向けて」、「ユーレカ・ブランドの意識」、「ユーレカ・ネットワークの効率改善及び産業界・科学界との対話の継続」の項目毎に今後の基本的方向を示している。以下に、これらの項目における主要な内容を示す。
--- EUREKA 2000plusガイドライン ---
■ ユーレカの使命:革新的プロジェクトの創造
ユーレカの存在意義はボトムアップ方式によるプロジェクトの創造であるとの認識から、国際共同プロジェクトとしてのパートナー探しの支援等の強化の必要性が指摘されている。プロジェクト準備段階に関する最大の決定として、ユーレカ・ラベルを申請してユーレカ・ネットワークに登録されたプロジェクトについて、そのプロジェクト・メンバーが所属する国は、プロジェクトに対する助成を優先的に判断するとともに、申請から6ヶ月以内に助成に関する決定を行うという努力目標が設定された。またプロジェクト成功の鍵がプロジェクト資金の調達にある点を意識して、プロジェクトに対する銀行や金融機関の参加を奨励、モニターすべきことも指摘されている。さらにはエクイティ・ファイナンス、ベンチャー・キャピタル、シード・マネーをプロジェクト資金として利用しやすくするための努力についても言及されている。
■ 戦略的プロジェクトへの支援
欧州の競争力に大きな影響を与える戦略的プロジェクトの支援を強化する。本ガイドラインは、“戦略的”とされるプロジェクトの要件として、①大規模で欧州さらには世界レベルのインパクトを持つ、②長期的な見通しのもとしばしば規格化や標準化に至る、③多面的かつ多国間、④ハイリスクかつノウハウ分担型、⑤政府の参加や支援がある、という5点を挙げている。
これに関連して最も注目されるのは、EUフレームワーク計画がこのようなユーレカ計画の戦略的プロジェクトを支援する役割を持つという点でコンセンサスがあると述べられている点である。フレームワーク計画からユーレカ・プロジェクトに対する助成可能性は、これまでもフレームワーク計画の準備の度に提案されてきたが実現してこなかった。フレームワーク計画の資金を、プログラム運営委員会の政治的な監督から自由にユーレカ計画に投入することには、少なからぬ抵抗があったためである。すでに開始された第6次フレームワーク計画の準備作業において、これが実現するか否かは注目されるところである。
■ 中小企業の参加促進
中小企業のユーレカ・プロジェクトへの参加を支援するネットワーク等はすでにかなり整備されているため、それらの十分な利用が強調されている。新しい事項としては、新技術立脚型企業(NTBF)への支援強化策として、これらの企業への技術開発支援の他、市場参入(特に国外市場)に対する支援が行われる。
■ 中東欧の取り込み
中東欧諸国の研究開発能力をより広範に取り込むため、これら諸国からの参加を促進する。
■ 世界的協力に向けて
グローバル化する経済社会において競争力を維持するためには、民間企業や研究機関には積極的に世界的な研究協力に参加することが求められる。このため、加盟国やユーレカ事務局はこれに呼応して、ユーレカ非加盟国のユーレカ計画への参加促進に務める。
■ ユーレカ・ブランドの意識
ユーレカ計画のブランド・イメージの拡大向上に努めることで、プロジェクトの準備作業などを容易にする。このため世界的に重要な見本市等のイベントへの参加、インターネットのより積極的な活用、加盟国のイノベーション政策との一体化などを図る。
■ ユーレカ・ネットワークの効率改善及び産業界・科学界との対話の継続
他のEUレベルの研究開発施策との重複回避等、ユーレカ計画の運営の効率化の必要性等が指摘されている。
5.主要なIT関係プロジェクト
代表的なIT関係プロジェクトとして、現在実施中の4つのクラスター・プロジェクト(MEDEA+、ITEA、EURIMUS、PIDEA)について紹介する。
(1)MEDEA+
・略称:MEDEA+(登録番号:E!2365)
・タイトル:「E-エコノミーのためのシリコン基板上のアプリケーション・システムにおける欧州のイノベーションに寄与するマイクロエレクトロニクスの開発」
・プロジェクト開始:2001年1月1日
・プロジェクト終了:2009年1月1日
・実施期間:96ヶ月
・実施コスト:40億ユーロ
・参加メンバー:フィリップス(蘭)、英貿易産業省・ユーレカ事務局(英)、ブル(仏)、トムソン・マルチメディア(仏)、STマイクロエレクトロニクス(仏)、MEDEA事務局(仏)、ロバート・ボッシュ(独)、インフィネオン・テクノロジー(独)、カール・ツァイス(独)、STマイクロエレクトロニクス(伊)、国立マイクロエレクトロニクス研究所(西)、ASMリソグラフィー・ホールディング(蘭)、ASMインターナショナル(蘭)、アルカテル・マイクロエレクトロニクス(ベルギー)、インフィネオン・テクノロジー・マイクロエレクトロニック・デザイン(墺)、CHIPIDEAマイクロエレクトロニカ(ポルトガル)、エリクソン(スウェーデン)、ノキア(フィンランド)
・コスト分担:未定
|
《 プロジェクト内容 》
MEDEA+は、半導体製造技術における日米に対するキャッチアップを目指したJESSI、MEDEAの後継プロジェクトである。
MEDEA+の目標には、重要市場における「シリコン・アプリケーション・プラットフォーム技術」の開発と、これを支える「基盤技術」の開発の2つがある。MEDEA+の特徴は、システム技術と半導体技術とをこれまで以上に緊密に連携させようとしている点である。「シリコン技術におけるシステム・イノベーション」がMEDEA+のターゲットとされ、半導体技術に関するプロジェクトとともに、それぞれのアプリケーション分野に関するプロジェクトもプログラムの対象とされ重視されている。
第一に、「シリコン・アプリケーション・プラットフォーム」に関しては、経済・社会をEエコノミーに誘導するとともに欧州の長所を生かすことにもなるキー・アプリケーションを目指した複数のサブ・プロジェクトが組織される。これらのプロジェクトからは、多くのパートナーが利用できる知的プラットフォームの構築、デ・ファクト標準の形成が期待されている。現在これに関する対象分野として、以下が設定されている。
・高速通信システム
・インターネット社会における情報・通信・娯楽一体型端末
・安全なインターネット・アプリケーション用スマートカード
・自動車内通信、乗員安全、環境保護のための自動車用エレクトロニクス
これらの優先分野の選択はプロジェクト進行中に見直され、4年間の第一フェーズが終了した時点で評価が行われる。
第二の「基盤技術」については、半導体に関する国際技術ロードマップが提示している技術要件のクリアが目標となっている。これに関する主要な取り組み領域は次のように設定されている。
・システム・オン・チップの設計手法と設計ツール
・特定のアプリケーション用市場に関する革新的IC技術
・IC技術
|
[ JESSI、MEDEA、MEDEA+の関係 ]
ユーレカ計画といえば現在でも、欧州が半導体製造技術の遅れを取り戻すために開始したJESSI(1989~1997、総額38億ユーロ)の名が出てくるように、ユーレカ計画におけるマイクロエレクトロニクス分野の大型プロジェクトは、ユーレカ計画のみならず、欧州の共同研究開発を代表してきた。またユーレカ計画は、JESSI以降、マイクロエレクトロニクス分野の大型プロジェクトの更新によって、計画自体の再活性化を図りつつ、研究開発計画としてのブランド名を維持してきた。JESSIは1997年6月に終了したが、それを引き継ぐMEDEA(1997~2001、総額20億ユーロ)は、大規模なプロジェクトを設置できにくくなってきていたユーレカ計画の存在意義を維持してきた。MEDEAの実施期間はJESSIの半分の4年で、2001年1月1日で終了したが、これを受け2000年6月のユーレカ閣僚理事会では、MEDEA+(2001~2009、総額40億ユーロ)の開始が決定された。現在はMEDEA+のスタート時期にある。
このようにシリコン半導体技術に焦点を絞ったマイクロエレクトロニクス技術の中核的な研究開発プロジェクトとしてJESSIからMEDEA+まで一貫した流れがあるわけであるが、JESSIと二期にわたるMEDEAの間には、若干の性格の相違点がある。これは端的に両者の呼称に表れている。JESSIは、「シリコン半導体技術欧州合同計画」と呼ばれ、欧州のエレクトロニクス関係の研究開発能力を結集して159組織が参加していた。これを反映して、8年間で38億ユーロのプロジェクト・コストのうち17.2%は欧州委員会が負担していた。プロジェクトの運営には行政的組織であるJESSI PLANNING COUNCILが特別に設置されていた。
これに対しMEDEAのプロジェクト参加者は、プロジェクト運営方式がクラスター方式になったこともあり、フィリップス、アルカテル-アルストム、ボッシュ、シーメンス、SGSトムソン、STマイクロエレクトロニクス、エリクソン、ノキア等の大手エレクトロニクス企業等の15組織でしかない。欧州委員会の資金負担はない。プロジェクトの運営面でも、プロジェクト・リーダーはフィリップスである。MEDEA+は立ち上がったばかりで、プロジェクト参加者を募っており、8年間で40億ユーロと見積もられているプロジェクト・コストの分担は固まっていないが、現在の参加メンバーはMEDEAのメンバーとほぼ同じであり、リーダーもフィリップスが務めている。ただしプロジェクト進行中の参加を認めていることから、この方向でイギリス、スイス、ギリシア、チェコが参加の意向を表明しており、最終的にMEDEA+ではオール・ヨーロッパ的な性格が幾らか回復されるかもしれない。しかし、いずれにしても欧州委員会の資金参加は予定されていない。
なお、現実のプロジェクトの実施は、MEDEAもMEDEA+においても十数社のプロジェクト・メンバーだけで行われているわけではない。これらはPIDEA、EURIMUS、ITEAなどクラスターと呼ばれている他の大規模プロジェクトと同様に、主要なプロジェクト・メンバーが中心になって構成するプラットフォームが決定する作業計画から、必要になる研究開発課題をサブ・プロジェクトに振り当てているのはすでに解説した通りである。
(2)ITEA
・略称:ITEA(登録番号:E!2023)
・タイトル:「欧州の発展のための情報技術」
・プロジェクト開始:1998年10月1日
・プロジェクト終了:2006年10月1日
・実施期間:96ヶ月
・実施コスト:32億ユーロ
・参加メンバー:フィリップス(蘭)、英貿易産業省・ユーレカ事務局(英)、アルカテル-アルストム(仏)、ブル(仏)、トムソン-CSF(仏)、トムソン・マルチメディア(仏)、バルコN.V.(ベルギー)、ロバート・ボッシュ(独)、ダイムラー・ベンツ(独)、シーメンス(独)、ITALTEL(伊)、CDTIユーレカ事務局(西)、フックス・スプラシュマン&パートナー(墺)、リンツ大学(墺)、TTテク・コンピュータテクニック(墺)、LBデータ(墺)、ビルディング・インフォメーション・センター(アイルランド)、テレビット・コミュニケーション(デンマーク)、ビノバ・エージェンシー(スウェーデン)、ノキア(フィンランド)、EPFL-CAST(スイス)、ユニス・スポル(チェコ)、欧州委員会DGⅢ
・コスト分担:オランダ20%、ベルギー8%、ドイツ22.5%、イタリア17%、フィンランド7%、フランス22.5%。その他、オーストリア、スイス、チェコ、デンマーク、スペイン、英国、スウェーデン、アイルランド、欧州委員会は負担率未定。さらにイスラエルが参加の意向を示している。
|
《 プロジェクト内容 》
“ソフトウェア・インテンシブ・システムのためのソフトウェア”、具体的にはオペレーティング・システムとアプリケーションの間のミドルウェアの開発に関するプロジェクトである。将来の情報システムは、設定変更の自由度、適応性、インテリジェント性、状況対応性、高い安全性等が要求され、いっそう複雑になる様々な状況(家庭、職場、移動環境など)で使用され、多様なデジタル・データ(画像、ビデオ、音声、テキスト、等)を扱うようになる。これらのシステムはより多くのソフトウェアを必要とするようになる。このように情報社会の鍵となるソフトウェア分野で、欧州は米国に対して遅れているとの認識がある。米国では、米国ソフトウェア市場の90%を自国のソフトウェアでカバーしているが、欧州ではそのカバー率は65%(1996年)である。この傾向を早急に改善し、欧州産業にとって戦略的に重要であるソフトウェア技術を急速に強化・発展させようというのがITEAの目標である。
ITEAはこのため、複雑なシステム構築に必要なソフトウェア・インフラ(ミドルウェア)の開発を目指す。そのためには、欧州に固有のニーズがある分野、欧州が得意とする分野における技術動向を先取しながら、それに応える方向で欧州レベルでのアクションを行う。戦略的分野としては次の3つがあり、これがITEAの中核対象分野となっている。
・拡張(Extended)マルチメディア
・通信
・分散型情報・サービス
これらのアプリケーションの技術を確立するには、さらにサービスの信頼性に関する以下の3つ分野の技術が必要となる。
・コンテンツ処理
・ユーザ・インターフェース
・複雑系エンジニアリング
ITEAのサブ・プロジェクトは、これらのテーマのうち最低2つの分野をカバーすることとなっているが、特に複雑系エンジニアリングが重視される。
このようにITEAは、システム・アーキテクチャー、標準化、システム・インテグレーションを通じ、ミドルウェア設計の主導的地位の確立を目指すプロジェクトである。なお、ITEAの運営は、域内に設置された専用事務局が行っている。
|
(3)EURIMUS
・略称:EURIMUS(登録番号:E!1884)
・タイトル:「マイクロシステム利用のためのユーレカ産業イニシアチブ」
・プロジェクト開始:1998年4月1日
・プロジェクト終了:2003年4月1日
・実施期間:60ヶ月
・実施コスト:4億ユーロ
・参加メンバー:セクスタン・アビオニック(仏)、ラザフォード-アップルトン研究所(英)、シュルンベルジェ(仏)、フィリップス部品・半導体(仏)、仏原子力庁LETI(仏)、EURIMUS事務局(仏)、オリベッティ(伊)、R.T.M.S.P.A研究所(伊)、イタリア国立研究機構(伊)、COPRECI(西)、国立マイクロエレクトロニクス研究所(西)、フィリップス(蘭)、バルコ・インダストリー(ベルギー)、IMEC(ベルギー)、DTU(デンマーク)、IONAS(デンマーク)、フィフティ・フォー・ポイント・セブン(ノルウェー)、センソナー(ノルウェー)、VTI HAMLIN(フィンランド)、エレクトロニック・ビジョン(墺)、NMRC(アイルランド)、CSEM電子・マイクロエレクトロニクス・スイス・センター(スイス)、カウナス大学(リトアニア)、欧州委員会DGⅢ
・コスト分担:フランス20%、オーストリア5%、ベルギー5%、スイス12%、ノルウェー9%、イギリス9%、イタリア14%、スペイン5%。その他、アイルランド、リトアニア、デンマーク、欧州委員会の負担率は未定。さらにトルコが参加の意向を示している。
|
《 プロジェクト内容 》
EURIMUSは、大企業、中小企業を合わせて100以上のサブ・プロジェクトから構成されている。設計、シミュレーション技術、ライブラリー、シリコン/非シリコン技術、製造技術、パッケージング、組立とテスト、カスタマイズド・ソフトウェア・システム等を対象としており、日米の世界レベルの技術進展と拮抗できるマイクロシステム技術の確立を目指している。製品開発や製造技術面では、製造に至るまでの時間の短縮、コスト競争力、世界レベルの品質といった要素も考慮される。
開発されるマイクロシステム・デバイスやシステムの利用分野としては、以下が挙げられている。
・マルチメディアと通信:マイクロマシン・マイク、シリコン・マイクロ・イメージング ・デバイス、インクジェット・ノズル、シリコン読み取り/書き込みヘッド、位置決めデバイスとスマート・マウス、マイクロマシン・スイッチ、マイクロアンテナ、等
・自動車、交通・運輸:MAP、ギアボックス、燃料インジェクション、タイヤ・モニター、エンジン・オイル圧、燃料タンクモニター、排気ガス圧、ターボ・モニター、等
・医療・バイオ医療:ペースメーカー、加速度計、圧力センサー、バイオチップ、グルコース・センサー、化学センサー、等
・マイクロマシン加速度計:エアーバッグ、角速度センサー、ジャイロスコープ、車体安定、振動センサー、等
・消費者製品:対侵入システム、家庭用機器、等
この他、エネルギー管理、工業プロセス・コントロール、航空宇宙、地球科学、電子商取引(認証とスマートカード)、コンピュータ・ゲームなど広範な分野にわたる。
EURIMUSのサブ・プロジェクトは、製造メーカをリーダに据えながら、そのユーザ事業者グループと製品の評価分析を行う研究機関を組み合わせて共同プロジェクトを構築することが体制面での目標となっている。
EURIMUSの技術開発課題は以下の通り。
・材料:開発中の新材料の事業化(SOI、SIC等)
・設計とシミュレーション技術(能動型CADツール、プロセス・フォローアップとプロセス・データCAD)
・マイクロ技術基礎プロセス(これらの産業化や技術移転)
・製造技術:装置と柔軟なライン構成
・特定用途用パッケージング、組立とテスト
・システム・ソフトウェア
|
(4)PIDEA
・略称:PIDEA(登録番号:E!1888)
・タイトル:「欧州のアプリケーションのためのパッケージングとインターコネクションの開発」
・プロジェクト開始:1998年6月1日
・プロジェクト終了:2003年6月1日
・実施期間:60ヶ月
・実施コスト:4億ユーロ
・参加メンバー:トムソン-CSF DETEXIS(仏)、トムソン-CSF コミュニケーション(仏)、トムソン-CSF マイクロエレクトロニクス(仏)、TEKELEC-TEMEX(仏)、LATECOERE (仏)、マトラBAeダイナミクス(仏)、フラマトム・コネクター・インターナショナル(仏)、GTID(仏)、ブル(仏)、3D PLUS(仏)、CIRE(仏)、EGIDE(仏)、RADIALL(仏)、SAGEM(仏)、仏原子力庁LETI(仏)、シーメンス(独)、ハーティングKGAA(独)、アレニア・アエロスペース(伊)、CSELT(伊)、PIRELLI CAVI SYSTEMI(伊)、SIMESA(西)、ELECTRONICA BASICA(西)、CIEMAT(西)、国立マイクロエレクトロニクス研究所(西)、SENTER(蘭)、アルカテル・マイクロエレクトロニクス(ベルギー)、IMEC(ベルギー)、M.Vテクノロジー(アイルランド)、NMRC(アイルランド)、ノキア(フィンランド)、ELECOTEQ NETWORK(フィンランド)、VTT(フィンランド)、BVK HRADEC KRALOVE(チェコ)、
・コスト分担:フランス25%、ベルギー7%、チェコ2%、ドイツ13%、イタリア12%、アイルランド5%、スペイン5%、フィンランド12%。
|
《 プロジェクト内容 》
本プロジェクトにおけるインターコネクションとは、電子機能を実現するためコンポーネントやサブ・アセンブリーを接続することと定義されている。こうした電子機能とは、特定機能と標準機能、受動機能と能動機能、エレクトロメカニカル機能、連動機能と別動機能などすべての機能にわたっている。PIDEAは、このように定義されたインターコネクション等に関する研究開発である。主要な取り組み領域は以下のように整理されている。
・「製品」アプローチ:コネクター、ケーブル、プリント回路基板、マルチチップ・モジュール、パッケージ、等
・「技術」アプローチ:サブストレート、アセンブリーとコネクション、パッケージ、材料、等
・「アプリケーション」アプローチ:交通・運輸、データ処置と通信における新技術、等
現在、インターコネクション・メーカは次の二つの課題に直面している。
・一層新しい製品が求められている技術競争における生き残り
・きわめて細分化されたセクターにおいて大量生産の求めに応えること
これらの課題に応えるため、PIDEAでは、大きな成長が見込まれる情報通信分野と交通運輸分野におけるインターコネクション技術とパッケージング技術の開発を目指している。特に、半導体の大量生産のための低コストかつ高性能のインターコネクション技術やパッケージング技術の開発が目指されている。
具体的には、MCM、サブストレート、電気・光学コネクター、キーボード、新しいマン ・マシン・インターフェース(高速システム、携帯端末、消費者製品のマイクロエレクトロニクス)等の多様な分野において、それらに対するパッケージングやインターコネクションに関するソリューションを提供することを目標としている。サブストレートに関する新世代の基礎素材の開発から、特定用途における各種パッケージング/インターコネクション製品の実現、さらにはそれらの製品の大量生産システムの確立に取り組んでいる。
|
Ⅱ.産業動向
<スペイン:次世代携帯電話のサービス開始を10ヶ月延期>
欧州では一般に2002年から次世代携帯電話のサービスが開始されることになっているが、スペインでは欧州で唯一2001年8月からサービスが開始されることになっていた。しかし今般、通信網の整備の遅れ等により、サービス開始が2002年6月に延期された。
<欧州:第一四半期のパソコン市場シェア>
2001年第一四半期の欧州パソコン市場シェア順位は以下の通り。
・コンパック …………………13%
・デル ………………………10%(世界市場では1位)
・ヒューレット・パッカード…… 9%
以下、富士通=シーメンス、IBMの順
Ⅲ.政策動向
<仏:IT関係の首相諮問委員会を設置>
仏政府は4月11日、米国のPITAC(大統領府情報技術諮問委員会)をモデルにした情報技術戦略評議会(CSTI) を設置した。CSTIの委員は、インターネット・電気通信関連企業、スタートアップ企業、研究機関、ベンチャー・キャピタルから構成される。今後、同評議会は、年間10本ほどの報告書を首相に提出する予定である。
(C)Copyright JEITA,2001
|