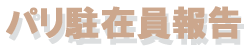
【 2002年3月号 】
Ⅰ.欧州諸情報
毎回1つのテーマに着目して特集形式で報告しているが、情報収集の過程で、特集として採りあげるほどではないもののレポートしてみたい個別の案件が蓄積してきた。このため、今回はいくつかの小テーマについて報告する。
1.IT分野でのフレームワーク計画とユーレカ計画に対する企業の見方
欧州諸国での産業界に対する助成金の交付による技術開発支援施策は大きく3つに分けられる。①EUのフレームワーク計画による支援、②ユーレカ計画による支援、③各国独自の政策ツールによる支援である。フレームワーク計画は、欧州委員会が助成金を支出する市場前段階における研究開発に対する支援スキームである。1984年に開始されて以来、4年毎の計画が繰り返される形で進められ、2002年は第5次フレームワーク計画(1998年~2002年)の最終年であるとともに、第6次フレームワーク計画(2002年~2006年)の初年度に当たる。一方、ユーレカ計画は、欧州委員会は原則として助成金を支出せず、各国政府が助成金を支出し合う市場指向性のある技術開発に対する支援スキームである。いずれの計画も、個々のプロジェクト毎に複数の国の企業/機関が参加する点で、共同研究が原則になっている。
フレームワーク計画では、全予算のうち最大の割合である約1/4がIST(Information society Technologies)プログラムとしてIT分野に割り当てられているが、個々のプロジェクトの規模は小粒である。1件あたりのプロジェクトに対する助成金額は平均約2億円(補助率は原則50%のため自己負担も含めたプロジェクト規模は約4億円)に過ぎない。しかも、この値は単年度ではなく全プロジェクト期間(長いもので36ヶ月)を通じたものであり、また1プロジェクトへの平均参加者数は7~8社/機関であるため、1参加者が単年度に受け取る助成金額はごく僅かにならざるを得ない。これでどれだけの政策効果があるのか、特に大手企業にとっては、プロジェクトへの参加意欲がわかないのではないかと疑問に感じていた。そこで、ドイツの某有名大手企業を訪問した際に、大手企業にとってのフレームワーク計画のプロジェクトへの参加意義を尋ねてみたところ、①助成金額は問題にならないほど小さいのでそもそも助成金獲得を目的としているのではなく、②競合他社と共通のスタンダードを作る土俵として意義を見いだしているとのことであった。
一方で、ユーレカ計画については、半導体開発(MEDEA+)に代表される大型プロジェクトが存在しているが、コンピュータ、ソフトウェア、インターネットといったIT分野よりも、マイクロエレクトロニクス系が中心となっているので、企業内のIT部門では、ユーレカ計画についてはフレームワーク計画ほどには関心が高くないように見受けられた。ユーレカ計画の方が1プロジェクト当たりの規模が大きいため、自ずとハードウェア的な多額の研究費用を要する分野にシフトしてしまっているということかもしれない。
2.ICカード
欧州ではICカード(スマート・カード)の利用が進んでいる。ICカードは、電子決済やPKIをはじめ情報化社会の基本ツールになると考えられる。欧州委員会は、eEurope計画の枠内のeEuropeスマート・カード・イニシアチブの下、2000年4月にスマート・カード憲章を策定し、産業界を巻き込んだタスクフォースを設定して2002年末を目途にICカードの諸課題の解決に取り組んでいる。
欧州委員会がICカードを手がけているのは、現在はICカードの利用が国毎、セクター毎に分断されていることから、より一層の発展の障害になっているという解決の必要性に迫られた面もないわけではないであろうが、ICカードは情報化社会の重要な基本ツールと目され、欧州はICカード分野で世界でのアドバンテージを有してことから、欧州が世界のICカード技術をリードするという強い政策意図から発しているものと想像される。
ところで、欧州で既に一般に利用されているICカードの利用分野としては、デビット・カード、電子マネー、テレホンカード、駐車料金カード、携帯電話のSIMカードなど幅広い。高い安全性や大容量のメモリー機能といったICカードの特徴を活かした現時点での欧州3大利用分野と言えば、①デビット・カード/電子マネー、②住民カード、③健康保険・医療カードだと思う。このうち、比較的最近利用が開始されたのが、住民カード(フィンランドで1999年12月から実用化)と健康保険・医療カードだ。
フランスの健康保険・医療カード(Carte Vitale)について若干紹介する。フランスでは、1998年5月から健康保険・医療カードの国民への配布が開始された。1999年6月までに全世帯にカードが配布され、2001年6月からは世帯毎ではなく個人別のカードの配布が行われている。従来、フランスでは医療保険の申請は、日本のように病院側が行うのではなく、患者が一旦病院に費用の総額を支払った上で、1件毎に申請を医療保険当局に郵送し、保険金の還付を受ける方式をとっていた。このため、患者側にとって手続きは煩雑であり、当局側にとっても作業量は膨大で誤処理率も高かった。そこで、健康保険証をICカード化し、医療保険手続きがオンライン化されたわけである。これにより、従来保険金の還付までに2ヶ月を要していたのが、2日で入金されるようになった。
2003年~2004年には新しいタイプのカードが配布される予定であり、公的保険を補完する民間保険や、既往症などの個人医療データもカード内に記録されることとなっている。
3.欧州共通の電子マネー
ドイツのゲルトカルトをはじめ、欧州各国ではICカードによる電子マネーが導入されてきている。現時点では、各国の電子マネーに互換性はない。そこで、将来の国境を越えて利用可能な電子マネーの標準として目されているのがCEPS(Common Electronic Purse Specification)である。
欧州委員会は、①ENV(決済系のICカード・端末仕様)の普及と、②CEPSによる国境を越えた電子マネーの普及を政策としている。欧州委員会はCEPSの欧州各国間での相互運用性を実証するDUCATOプロジェクトを支援してきた。DUCATOプロジェクトは昨年12月に成功裏に終了し、欧州共通の電子マネーの導入に向けての技術的な準備が整ったとしている。DUCATOプロジェクトが昨年12月に終了期限を設定したのは、本年1月からの欧州共通通貨ユーロの導入を念頭においたものであり、現実の共通貨幣の導入が電子マネーについても国境を越えた利用を求めるニーズを喚起していくことになろう。実際にCEPSが共通標準になるかどうかは現時点ではまだ分からないが、欧州委員会では、2005年にはCEPS/ENV仕様のカードが欧州で国境を越えて使用されるようになると予想している。
ICカードの普及が遅れているわが国では、例えば接触型か非接触型かという問題についても一足飛びに非接触型を目指しているように聞いているが、あまりに高いレベルを目指しすぎて導入が遅れるというのは日本の悪い癖であるように思う。電子マネーやデビット・カードといった電子的な支払い手段は単に支払いが便利になるだけではなく、これを元にして新たなサービスが生まれるという性格を有しており、導入の遅れは致命的なIT化の遅れに繋がることが懸念される。
4.認証局のセキュリティ
昨年、ドイツのDトラスト社を訪問した。同社は元々ドイツの紙幣やパスポート等の印刷を行い、我が国で言えば財務省印刷局のような存在であったが、1999年に民営化され、現在では認証局事業を行っている。この認証局の運用システム及び物理的な建物等のセキュリティの“ものものしさ”は印象的であった。認証局のサーバは安全な環境で運用されるべきというのは日本でも常識であろうが、Dトラスト社では、認証局は「信用」を売る商売であるとの理念のもと、外部からの“攻撃”に対して極めてハイレベルの防御がなされていた。0~5レベルの6段階のセキュリティ・レベルが設定され、IDカード、フィンガープリントで入退室が管理されていた。電気系はもちろん二重系である。対火災対策や、建物の構造上外部からの侵入に対しても完璧にガードされていた。まるで国家機密を納めた金庫でも守っているかのような状況であった。
「信用」を売るということは大変なことであると感じた。日本は安全な国であるが故に、安全に金をかけるという意識レベルが低いように思うが、目から鱗がとれるような印象を受けた。
5.産学連携・国際経験を通じた人材育成
先日、フランス中部にあるグランドゼコール(上級の大学)の1つであるフランス先端機械工学院(IFMA)を訪問した。IFMAは、産業界にハイレベルの機械技術エンジニアを供給することを目的に1991年に設立された高等教育機関である。このIFMAの教育システムに興味を有した。
まず、密接な産学連携を通じ極めて実学的である点である。研究内容は企業との共同研究で、双方の研究者が相互に行き来しながら研究が進められている。大学の研究設備は、まるで企業内の工場のようであり、座学が多い日本の理工系の大学とは相当にイメージが異なる。全ての大学がこのように実学的であっていいとは思わないが、一方でわが国では大学を卒業しても企業でそのまま実戦力として使える人材は少なく、企業内での再教育が必要と言われており、わが国にも中にはこのような実学的な高等教育機関があってもよいように感じた。
2点目は、外国の企業文化を学ばせるため、学生の90%が卒業までに1年間外国(企業及び大学)で研修を行う点である。20%の学生が卒業後に外国に就職してしまうのが学校側の悩みのタネであるらしいが、ほとんどの学生が国際的な経験を積むというのは日本では見られない教育システムである。
IFMAの言によれば、IFMAでは技術だけではなく、ビジネス、国際的マネージメントの習得も目的としており、実社会のリーダとなるべきフランスで最もハイレベルなエンジニアを輩出している自負があるとのことであった。なお、フランスでは、わが国と異なり、理工系人材の社会的地位は高い。
 IFMA正面
IFMA正面
 IMFA内部
IMFA内部
6.国境を越えたテクノポリス、メディコン・バレー
昨秋に、デンマークとスウェーデンにまたがるテクノポリスであるメディコン・バレーを訪れた。デンマークとスウェーデンは、北海とバルト海をつなぐエーレズント海峡で隔たられているが、2000年7月に橋が開通し陸続きとなった。両地域のつながりの緊密化を背景に、両岸のデンマーク・コペンハーゲン側とスウェーデン・マルメ側がタイアップし、当地を1996年以来バイオテクノロジーの集積地“メディコン・バレー”として売り出している。メディコン・バレーでは、1にバイオテクノロジー分野、2にIT分野の企業誘致に力が注がれている。現在、メディコン・バレーでは、約500社のバイオ関係企業が集積し、関連就業者数は3万人(うち研究者数は4,000人)である。著名なバイオ関係企業としては、ファルマシア、ノヴォ・ノルディスクがある。メディコン・バレー設立当初は、当地でのバイオ産業はまだまだであったが、大企業からのスピンアウトでベンチャー企業が設立されてきた。特に、ベンチャー創設が活発になったのはここ3年のようだ。現地側の説明によれば、メディコン・バレーはバイオテクノロジーの分野でロンドン、パリに次いで欧州第3位を占めている。
欧州統合により、経済上の国境がどんどん低くなっているが、欧州統合はこのようなテクノポリスの世界にも現れてきているわけだ。

メディコン・バレーの企業集積図 (クリックすると拡大します)
7.追記
2年半にわたり毎月パリから欧州駐在員報告を送り続けているが、レポートの読者の方々のターゲットをどこにおくか、レポートの基本構成をどのようにするかといったことを常に考え続けてきている。
本レポートは欧州のIT分野最新情報を旨としている訳であるが、IT分野は深く追求すればするほど専門的になる。例えば、日経○○といったIT分野の月刊情報専門誌などを読もうとすると、あまりにカタカナ言葉やアルファベットの略号等の専門用語が多く、小生などは少し読んだだけでげんなりしてしまう記事が多い。これらを完全に理解して読破しようと思うと、相当のパワーが必要になる。小生はIT分野のずぶの素人という訳ではないのだが、このように感じてしまうのが偽らざるところだ。結構同じような感覚をお持ちの方も多いのではないかと思う。
本誌は、IT・エレクトロニクス産業界の皆様にお読みいただいているので、かなり専門的な読者がおられるのは当然であるが、一方で、今や非常にすそ野が広いIT分野では、個々人の専門分野から離れると、IT業界に属する方でも必ずしもIT全般にわたって詳しいという訳でもないように思う。このため、色々なレベルの読者がおられると想定し、本レポートはあまりに技術的に専門的な内容にはせず、むしろ欧州の状況を大きく把握していただけるような内容にするように心がけている。
テーマの選定としては、ITといえば米国が先行している部分が多いが、米国の二番煎じでは意味がないため、例えば先々月号の仮想移動体通信事業といったように極力欧州らしいテーマを選定するようにしている。ただ、通信の標準化では欧州が世界の中心となってきた歴史があるように、欧州のITは通信分野が牽引する部分があるため、小生のレポートはITと言いつつもどうしても通信の色彩が強くなってしまっているのは、自分でも認識している事柄である。
小生の任国はフランスであるが、欧州のIT事情といっても必ずしも国によって状況は一様ではない。限られた紙面で、一国についてのみ詳報しても意義は少ないいと考え、なるべく各国毎の状況を概観し、欧州全体あるいは欧州主要国を比較できるような方式にするよう努めている。
それにしても、毎回何をテーマとして採り上げると読者の方々に興味をもってお読みいただけるかというのは、常に頭から離れない悩みのタネである。
Ⅱ.産業動向
<フィンランド:ノキア、高級携帯端末会社を設立>
フィンランドのノキア社は1月21日、世界初の高級携帯端末会社バーチューを設立した。新会社は、金やプラチナなどで装飾された手作り携帯端末を製造販売する。同社は、2002年半ばから、米国、欧州、アジアで販売を開始する予定。
<仏蘭:INRIA、フィリップス、トムソン・マルチメディアが共同研究>
INRIA(フランスのIT分野の国立研究所)、蘭フィリップス、仏トムソン・マルチメディアは、インテリジェント・ハウスに関する技術の共同開発のため、コンソーシアムAIR-Dを設立した。対象技術は、マイクロプロセッサの内蔵による日常生活用品のデジタル化(ユビキタス・コンピュータ)、これらの日常生活用品とユーザとの間のワイヤレス通信(ユビキタス通信)、音声認識等のインテリジェント・ユーザ・インターフェースの3つである。
<英仏:大手ネットバンクの買収>
英ネットバンク最大手のエッグ(英プルデンシャル生命保険子会社)は1月28日、仏唯一のネット専業銀行ZEバンクを買収することで契約書に署名した。エッグは1998年設立で、192万人の顧客を有する。ZEバンクは2001年設立で、顧客数は7万人である。
Ⅲ.政策動向
<EU:財政相理事会、電子商取引への付加価値税課税案を採択>
2月12日、EU財政相理事会は、電子商取引に対する付加価値税(日本の消費税に相当する間接税)の課税措置を取り決めた協定を承認した。従来、米国等のEU域外の電子商取引サイトがソフトやゲーム等のデジタル商品をEU域内の顧客にオンライン販売する場合は、付加価値税が課されていなかった。今回の措置が導入されれば、このようなケースにも付加価値税を課税することで、域外と域内の電子商取引事業者に対する税法上の取り扱いの不公平が是正されることになる。
<仏:電子政府>
フランスでは、本年1月から売上高1億フラン(約1,500万ユーロ、約17.5億円)以上の企業は、付加価値税のオンライン納付が義務付けられた。対象となる企業数は約23,000社である。
(C)Copyright JEITA,2002
|