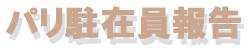
【 2002年6月号 】
フランスに駐在して3年間が経過した。6月に帰国することとなり、小生の駐在員報告は今回が最終回となった。今回は、3年間の駐在生活を振り返って、欧州及びフランスについて感じた点について記載する。
Ⅰ 欧州について
1.1つではない欧州
欧州(西欧)は、日本から見ると“欧州”という1つの単位で見てしまいがちだ。しかし、欧州は1つではない。もちろん、欧州連合には15ヶ国があるように、複数の国が存在するので1つでないのは当たり前だが、民族的、歴史的に似通った国もあれば、異なる国もある。
最も違いを感じるのは、ライン川の北と南、すなわち北のゲルマン系及びアングロ・サクソン系と、南のラテン系で、国民気質が全く異なる点である。ゲルマン系及びアングロ・サクソン系は、比較的物事を秩序・計画立てて進める方のように思うが、ラテン系は何事につけてもアバウトで、時間厳守性も乏しい。分かり易い例で言えば、切符売場などの窓口に並ぶ際、北側ではしっかりと列を作る。特に、北欧諸国では単なる駅の切符売場でさえ、日本の銀行窓口にあるような整理番号発券機がある。片や、南側では、列を作るという概念が薄く、我先に窓口に押しかけるという具合だ。この点では、ゲルマン系やアングロ・サクソン系の方が比較的日本人に近く、フランス以南のラテン系の国で日本人が仕事をするのは、秩序概念とか時間的感覚が異なり結構ストレスがたまるものである。
仕事の仕方も両者では異なる部分があるようだ。ゲルマン系の某社の方に聞いた話であるが、ゲルマン系やアングロ・サクソン系では、物事を会議でしっかりと議論をして決める。一方、ラテン系では事前の根回しで決めてしまい、会議をするころには実際には事前に物事が決まってしまっていることが多いらしい。もちろん、これが全ての仕事のスタイルではないであろうが、当の欧州人ですら、北と南の間では大きな違いを感じているようだ。
ちなみに、北と南では体格も全く異なる。欧州人は背が高いと思いがちであるが、ゲルマン系、アングロ・サクソン系はその通りであるが、ラテン系の人々はほとんど日本人と同じような背格好である。この点では、フランス以南で仕事をする場合、日本人は妙なコンプレックスを感じる必要はない。
同じ欧州でありながらこれほどの違いがあるというのは、欧州に住んでみてこそ実感できるものである。
2.先進国の密集地域
欧州では、いくつもの先進国が隣接している。一方、東アジアでは、経済協力開発機構(OECD)に加盟している先進国は日本と韓国だけで、多くの近隣諸国が発展途上国であり、この地理的要因において、種々の点で欧州の方が有利であるように思える。
多くの先進国が密集しているため、欧州各国企業に対して、各国はお互いが高い購買力を備えた市場を提供している。また、通貨統合により経済的国境がなくなり、より企業間の競争が激しくなっているが、企業側にとっては単一通貨で全欧市場を対象にでき、より発展の可能性があるとも言える。
購買力を有する近隣諸国の人口が多いことは、例えば観光産業にとってみても非常に有利である。欧州の長いバカンスの習慣と相まって、南欧諸国は近隣諸国からの多くの観光客を受け入れ、多額の観光収入を得ることが出来る。日本も、潜在的には観光資源が少なくないように思うが、近くに観光客を提供する先進国がないだけに、多くの外国人観光客からの収入が期待できない。その証拠に、フランスのパックツアーのパンフレットを見ると、東アジア・東南アジアでは、中国、ベトナム、タイ辺りまではツアーが設定されているが、日本行きのツアーは存在しないのである。
政策面でも、各国が切磋琢磨しているように見える。例えば、情報化社会に向けての政策でも、欧州委員会のeEurope計画による先導の他、各国が情報化政策を競って展開しているように感じられる。
政治・経済面では欧州連合が存在し、安全保障面でも、中世・近世の戦い、2度の世界大戦と、欧州の中では歴史的には多くの敵対関係があったものの、現在では欧州諸国が結束することによるメリットが大きい。
欧州と比較した場合、日本は“孤独な”存在に見え、それをカバーするだけの政治的努力、経済的努力が必要な気がする。
3.情報化社会の先進地域
情報化社会への移行のための物的要素としては、以前は、単純に言えば、インターネットやパソコンの普及が重要かと思っていた。しかし、欧州で生活してみて、実はICカード型のデビット・カードや電子マネーの方がはるかに重要なのではないかと思うようになった。欧州各国では、ICカードを使った電子決済は当たり前なので、これは既に情報化社会の一種ではないかと思っている。
インターネットやパソコンの普及率は、国によって多少の差があるが、各国とも着実かつ急速に普及率が増加しており、これらが情報化社会への移行競争の鍵になるとは思えない。一方、デビット・カードや電子マネーがあれば、単に現金を持ち歩かなくてよいという利便性だけではなく、例えば個人のパソコンからセキュリティの高い支払いができ電子商取引が飛躍的に普及する可能性があるなど、アプリケーションの広がりは大きい。日本ではICカード型のデビット・カードの普及が遅れているばかりでなく、仮にこれが物的には普及したとしても、現金主義の傾向が強い日本では国民の性向は簡単には変化せず、実際の利用が容易には普及しない懸念がある。その点、既にICカード型のデビット・カードや電子マネーの利用が普及している欧州との情報化進展度の差は極めて大きいのではないだろうか。
フランスでは、これまでのレポートでも触れたように、世界に先駆けて10年以上前からICカード型のデビット・カード(カルト・バンケール)が普及している。通常の商店での利用に加え、例えば、高速道路の料金所でも、無人支払機で簡単にデビット・カードによる支払いが可能だ。料金所の前で渋滞ができることもないし、料金徴収係の人件費も節約でき、低廉な料金としてユーザにもメリットが反映される。フランスでは、いち早くデビット・カードを導入することにより、これをベースとして、新しい便利なサービスが生まれているのである。ちなみに、高速道路については、日本でも、自動料金徴収システム(ETC)があるではないかという指摘があるかもしれないが、そのようなものは、日本での導入以前から欧州では普及している。日本は高度な技術を徹底的に追求しすぎ、そのために返って新システムの導入が遅れるという傾向があるような気がする。
欧州は、日本よりも情報化社会への移行が進展している。
4.活発な産学連携と発展するテクノポリス
産学連携による研究開発と言えば、米国だけではなく欧州においても活発である。小生は、この3年間で北欧諸国のテクノポリスを何度か訪れた。大学の研究者が民間企業とタイアップし、給料を企業からも得つつ、研究対象が大学の研究か企業の研究か分からない程に融合した状況で研究が行われているのが印象的であった。北欧は、厳しい気候であるだけにテクノロジーで生きていかなければならないという意識が明確であるように見受けられた。
日本でも、これまで国立大学や国立研究所の研究公務員について、各種規制の緩和等によって産学連携が推進されてきたが、世界レベルの産学連携を行うためには、規制の存在を前提とした緩和措置ではなく、規制無しすなわち“何でもあり”の世界になる必要があろう。この点で、国立大学の非公務員型の独立行政法人への移行は期待大であり、実際の運用において各種規制が名実ともに撤廃されることを望みたい。
発展するテクノポリスの条件としては、欧州の例を見ると、以下の2つが重要であるように考えられる。
①核となる大学等の研究機関が存在していること。その研究機関が産学連携に大きく門戸を開いていること。・・・研究団地を整備し、研究所を誘致するだけではテクノポリスは発展せず、核となる大学等の周りに自ずと民間企業の研究所が集積する形でないと、活発なテクノポリスの形成は望めない。逆に、研究団地の整備は必ずしも必要でないように思う。
②国際空港が近くにあること。・・・研究者の往来が容易であり、研究者間の交流を活発に行えることが必要である。
インキュベータの整備や、ベンチャー・ファンドの設定は、どこのテクノポリスでも実施していることなので、これらは当然の必要条件である。なお、地中海沿岸のテクノポリスを訪問したときは、「温暖で魅力的な居住環境は研究者にとって不可欠」と、地中海沿岸のメリットを強調していたが、欧州で活発なテクノポリスが北欧や英国に集中していることを考えれば、気候はあまり関係ないようである。
5.今後の生産拠点としての東欧
これまで、業務を円滑に行う観点から欧州では英語圏に生産拠点を立地する日系企業が少なくなかった。欧州の英語圏と言えば、英国とアイルランドである。しかし、アイルランドでは経済発展とともに人件費が急速に上昇し、今では低賃金のメリットは全く消滅したようである。このため、全体として日系企業は同国から撤退傾向にある。また、英国はユーロ圏に属していないため、為替的に不安定な面が懸念されている。安い労働力コストを求めて南欧に立地している日本企業も多いが、東欧の人件費の安さにはかなわないようだ。特に、東欧の中でも西欧に隣接しているポーランド、チェコ、ハンガリーに対する西側企業の進出が活発のようだ。
東欧の物価水準の低さを紹介すると、最近チェコを訪れた際に、地方都市の青空市場では、じゃがいも1kgが20円、ニンジン・タマネギ1kgが40円という安さであった。ちなみに、携帯電話端末は、平均で3,000円~1万円であるが、4円という販促品もあれば日本製の最新型は4万円のものまで幅広い。この国には、食料品のような安価な国産品と、電気製品のような高価な輸入品という2つのレベルの物価水準が存在しているように感じた。統計を見ると1人当たりのGDPは南欧諸国をはるかに下回っており、上記の食料品の物価水準が一般市民の経済レベル、賃金水準を表しているように思われる。もっとも、都市部を見ている限りにおいては、決して生活レベルが貧しいようには感じられない。いずれにしても、このような安い労働力コストは、西側諸国の企業にとって大きな魅力であろう。
日系企業の最近の話題としては、トヨタ自動車が仏プジョー・シトロエンと合弁でチェコに工場を建設することが挙げられるが、今後、東欧諸国に益々欧州の生産拠点がシフトしていくものと思われる。
Ⅱ フランスについて
堅い話はこれまでにし、以下では、フランスでの社会生活面について感じた点に関して、気の向くままに列挙する。
1.都市景観・インフラ
(1)街そのものが芸術
ある旅行者は、「パリは街そのものが芸術だ。」と言っていた。こちらでは、昔からの建物がよく保存されており、中世、近世の街並みがそのまま現代に続いている。建物を立て直す場合も、建物の外壁面はそのまま残し、内側の部分だけを新しくするといった方式がとられている。日本のようにビルの側面に看板がひしめくようなこともなく、また法律で洗濯物を外に干すことも禁止されているので、落ち着いた風情ある街並みとなっている。もちろん、生活するに当たっては洗濯物を太陽が当たるところで干せないなど不便はあるものの、街並みの保存は文化の保存であり、行政がしっかりとコントロールすることにより、古き良きものを受け継ぎ次世代に残していこうという方針が徹底されている。
振り返って日本を考えてみるに、現代の日本の街並みで趣のあるものは少ないように思う。日本にも保存に値する昔の街並みもあるであろうし、近代的なビル地帯であっても、単に長方形の消しゴムを縦にしたような無味乾燥なビルではなく、ラ・デファンス(パリ西部の新都心)のような工夫した街作りがあってもあってもよいように思う。
街並みを整備することにより、パリには多くの観光客が訪れ、GDPの向上に寄与するだけでなく、世界の中心地の1つとして、フランスという国の地位を向上させているようにも思う。
(2)交通網の整備
フランスでは日本に比較して高速道路網がよく整備されている。フランスは平野が多く、多くが農耕地のため用地買収が簡単であるという日本との違いはある。道路舗装も日本のように雨が降っても水を吸収するような高級アスファルトの部分は少なく、また、地方に行くと、ろくにパーキング・エリアも整備されていないといったような状況ではあるが、あまり費用をかけずに簡素に作ることにより、高いサービスを提供するよりも、いち早く利用者に道路を供用することの方を重要視しているように思われる。
日本は山がちな国であり、住宅地が密集しているので用地買収が容易でないという不利な点はあるが、一方で日本は国土面積がフランスの68%なのに対してGDPは2.5倍以上であり、道路整備能力は高いはずである。しかるに、我が国では何故こうも高速道路の整備が簡単には進まず、一方で東名や名神の料金はいつまでたっても無料のならないのであろうか。もちろん、日本道路公団の全国プール制といった説明を聞けば、東名や名神の料金が無料にならない理屈は理屈として分かるが、しかし、ふとフランスと比較してみると、日本はいったい何なのだろうと思ってしまう。
話は変わるが、なぜ日本の新幹線は高架橋ばかりを走っているいるのだろう。こちらの新幹線であるTGVは“地べた”を走っている。都市部を高架橋にするのは当然であるが、日本では田んぼの真ん中を新幹線の高架橋が走っている。踏切が要らないとか色々理由があるのかもしれないが、高架橋にすれば、いずれコンクリートの耐用年数も来るであろうし、何と言っても“地べた”に線路を作るよりも建設コストは格段に高くなるであろう。不思議である。
(3)都市部には公共駐車場が整備
フランスの都市には公共駐車場が多い。パリでは、地盤がしっかりしていることもあり、街のあちこちに地下駐車場がある。どんな地方都市に行っても、街中に必ず複数の公共駐車場が整備されている。もちろん、無料ではなくそれなりの駐車料金は取られるが、大変便利である。フランスでは、路上駐車も料金を払えば一定時間(パリは2時間まで)はOKであり、さらに公共駐車場も整備されている訳で、違法路上駐車の取り締まりが厳しくても納得できる。
パリは地下鉄も発達しており、単位面積当たりの地下鉄網密度ではおそらく世界一で、本当は自動車を使わなくても市内移動に何の支障もない。それでも、自動車用インフラも整備されているのである。
日本では、都市部の公共駐車場は極めて少ない。駐車スペースもないのに駐車違反取り締まりだけ厳しいというのは納得できない、と思っておられる方も少なくないのではないだろうか。これも、長年、都市部のインフラ整備がおろそかにされてきたツケなのであろう。日本にいたときは、都市部に駐車場がないのは致し方ないことかと諦めに近い感覚を持っていたが、単に日本が遅れているだけなのであった。
最近、公共投資を都市インフラの整備に再び振り向ける議論がされてきているが、当局の目的が単に地方偏重の批判をかわすためかどうかは別として、本質的に重要な事柄であると思う。
2.生活スタイル
(1)長いバカンス
フランスのバカンス期間は長い。小生の事務所でも、現地スタッフは夏期にしっかりと1ヶ月近く休みをとる(日本人スタッフについては日本流であり、羨ましい限りである)。どうやら、他の企業も同様の状況であるようである。1ヶ月も休んで仕事は大丈夫なのかと思うが、これで現に社会が回っているから不思議である。それに比べて、日本人は一体何のために働いているのだろうと、思わず考え直さざるを得ない。お盆休みの短い期間に一斉に海外旅行をする日本人のニュースを見ると、こちらの状況に比較すると滑稽にさえ思えてしまうほどである。一生懸命仕事をする、その代わりに思いっきり余暇を楽しむ、ということは人生大切な気がする。
フランスの年次有給休暇は年間30日+α(企業により異なる)であるが、これは“休みをとることができる”ではなく、“休みをとらなければならない”に極めて近い。日本も社会全体で考え直してみる時期に来ているのではないかと思う。
(2)子供に厳しい大人社会
フランスでは、“子供は勉強するもの”と思われているようだ。フランスには、グランド・ゼコールという一般の大学(ユニヴェルシテ)よりも上級の大学があり、グランド・ゼコールを出ないと社会で出世できないという完全な学歴社会である。
少なくともパリ市内では、児童や学生が遊んでいる姿は見かけない。学校の行き帰りなのか、児童・学生が集団で街中を歩いている姿は見かけるが、個人で歩いている若年者は少ない。ファミリー・レストランなるものもほとんど存在せず、レストランは大人だけの社会である。
どうやら、フランス、あるいは、少なくともパリは、子供に厳しい大人社会のようである。もちろん、抑圧された社会である分、少年犯罪もあったりするようであり、子供に厳しい社会が一義的によいというわけではないであろう。しかし、“日本は世界レベルに比較して、学校で勉強を教えすぎで、もっとゆとりを持たせる必要があるのではないか”、という考え方が従来の多数派であったように思うが、日本以上に子供に勉強させようとしている先進国があることを忘れてはならない。
近年、日本の中高生の間に低俗な文化が浸透しているが、フランスとのあまりの違いに嘆かざるを得ない。日本での駐在経験があるフランス人が、先日久しぶりに日本を訪れた時の感想は、「日本の若者は悪くなった。残念です。」であった。
国土が狭く、天然資源や農業収入の少ない日本は、技術力で生きてゆかざるを得ず、そのためにハイレベルな教育すなわち優秀な人材の育成は、最も重要な要素の1つであると思う。日本は、もっと若年層に厳しい社会であってよいように思う。
(3)食事は優雅にゆっくりと会話を楽しむ
フランスのレストランで夕食をすると、高級レストランであっても普通の定食屋クラスのレストランであっても、アントレ(前菜)、プラ(主菜)、デセール(デザート)、カフェと、2時間から3時間かけてゆっくりと会話をしながら食事を楽しむことになる。日本で飲みに行くとすれば、居酒屋に行ってから、カラオケ、最後にラーメン+ビールというように、2軒、3軒はしごすることになるが、フランスでは結構お安く1軒のレストランでゆっくりと夜を楽しめるのがよい。カラオケでガヤガヤするのも楽しくはあるが、どうもあまり高尚な文化のようには小生には思えない。もっとも、本件については、個人々々の好みの問題であるので、どちらが良い悪いという問題ではない。
3.ラテン系の国民性
(1)柔軟な対応
フランスでは、一人の労働者に対して与えられている権限が大きいのか、あるいは細かいルールが設定されていないのか、通常の業務からは想定外の事態が発生したときに、結構柔軟に物事に対応してくれる傾向にあるようだ。
ある時、パリからイタリアのA都市に飛行機(エール・フランス)で行こうとした際、イタリアの全空港が管制塔のストライキで全面閉鎖してしまった。エール・フランスの各イタリア便は、米国のデルタ航空との共同運行便が多いため、パリのシャルル・ド・ゴール空港は、米国からの多くの乗り継ぎ客を含めて大混乱に陥ってしまった。しかるに、翌日便への振り替え手続きに着手されるわけでもなく、乗り継ぎ客用のホテルの手配があるわけでもなく、ただただ混乱するばかり。エール・フランスは“運休になったのはイタリアの管制塔組合の責任なので、我々には関係ない”という態度だ。秩序概念が比較的日本人に似ていると思われる米国人は、なぜもっときちんと対応しないのかとカウンターをたたいて怒るのだが、一向に埒があかない。
フランスではこのような時、怒ってはダメだ。自分の個別事情を訴えるに限る。小生は、比較的すいている窓口を探した上で、翌日はA都市ではなくB都市に到着していなければならないので、翌日のA都市便に振り替えてもらうだけでは支障が出てしまう、と自分の窮状を訴えると、A都市行きのエコノミー格安チケットを残席1席しかないB都市行きのビジネス・チケットに比較的容易に変更してくれた。変更してくれたのは責任者クラスではなく、単なる窓口の担当者である。この時点で、米国人の大混乱の方は終わる兆しなく続いていた。
日本であれば、このような場合、整理券を配るとかもっと混乱を最小限にとどめるような措置がとられるであろうが、一方で、飛行機に乗れなくて困っている人が千人以上もいる状況で、小生だけのために便宜を図ってくれるようなこともないであろう。日本では、個々の一般従業員の役割のルールがしっかりと定められている一方で、その分権限も大きくないように思う。
全体としてみれば、フランス流よりも、日本流の方がよいようには思うが、物事への柔軟な対応という面白い一面を見た。ちなみに、その後別の時に、またイタリアの管制塔のストで同様の大混乱に巻き込まれ、その際も“個別事情訴え作戦”で、他の乗客を尻目に混乱を切り抜けた。どうやら、この手の大混乱は時々発生しているようである。
(2)何事につけてもアバウトなのだが・・・
フランス人は何事につけても結構アバウトである。時間厳守でなく、またギリギリにならないとことを進めない。
例えば、小生が業務で経験したことで言えば、あるVIPが出席する予定だった各国代表を集めたディナー・パーティでは、事前準備が前日になるまで遅々として進まず、一週間前になっても主催責任者(ホスト役)自身すら会合の存在自体を知らない有様で、結局何のアナウンスもなく知らぬ間に主催者が変わっていたり、パーティ当日に各国代表団の宿泊ホテルにようやく案内状がFAXで送られてきたりと、日本人の感覚では信じられない状況であった。
ここでは、物事を事前からしっかりと準備する日本では考えられないようなことが平気で発生する。しかし、結果的には何事も何とか問題なく終了しているから不思議である。フランス流がいいとは思わないが、一方で、日本のように、事前に物事を詳細までつめすぎる仕事のスタイルは、大きな目で見れば本当に効率的なのかと、疑問を感じないわけにはいかない。
(3)交通マナーが劣悪
フランスに来て先ず驚いたことは、交通マナーが滅茶苦茶なことである。どうやらフランスでは、ルールがあるということと、ルールを守るということは別のようである。広い道路に上下線を分けるセンターライン以外の車線が書いていないこともあり、右へ左へと縫うように走る車もある。交差点ではたとえ渋滞していても我先に突っ込むので、すぐにデッドロックになってしまい、交差点があちこちに向いた車でいっぱいになってしまう。方向指示器を出さずに曲がるのはまだましな方で、反対側に方向指示器を出しながら曲がる車もある。交差点の真ん中で止まって、車の中で地図を広げている人もいる。何でもありである。
バイクはもっと命知らずである。フランスでは暴走族というのを見たことがない。走っている自動車の間を高速ですり抜ける蛇行運転とか、反対車線へのはみ出し運転とか、常日頃からほとんどのライダーが当たり前のように暴走を繰り返しているので、敢えて暴走族になる必要がないためである。
歩行者も負けてはいない。横断歩道以外のところで車道を横切るのは当然ながら、横断歩道の信号が赤で、尚かつ車が通っていても渡ってくる。これは本当に危ないので、これだけはフランス人は直した方がよいといつも思う。
実際、日本では交通事故を実際に自分の目で見かけることはまれであるが、こちらでは小生の感覚では1~2ヶ月に1度のペースで交通事故を見かける。自動車はかなりの割合で凹んでいる。
フランスにも自動車教習所はあり、「AUTO-ECOLE」(自動車学校)と表示のついた車がよく街中を走っているが、一体何を教えているのであろうか。“スペースがあったら横の車に負けないようにとにかく突っ込め”というようなことでも教えているのかと思いたくなる。
一度、フランス人にフランスの交通マナーの悪さを指摘したところ、その人が言ったことは次の通りである。「おまえはイタリアに行ったことがあるか? あそこの交通マナーはひどい。だから、フランスの交通マナーは良いのだ。」
(4)意外と悪い社会マナー
レディー・ファーストや障害者の方に対する優しさという点では、フランスには大いに見習うべき点がある。
一方で、フランス人はたばこの吸い殻などのゴミを簡単に道ばたに捨てる。これだけ世界で煙草の健康に対する害が指摘されていながら、フランスは全く別世界にあるようで、老若男女が煙草を吸い簡単に吸い殻を道ばたに捨てる。もちろん、煙草の吸いがら以外のゴミも多く道ばたに落ちている。ペットを飼っている人は大変多いが、ペットの排泄物を飼い主が処理するという習慣もない。窓口の列で、きちっと並ぶということもフランス人は苦手である。
欧米は個人主義の国というが、フランス人は個人主義を通り越して利己主義的ともとれる部分があるように小生には思われる。フランスと言えば、マナーが洗練された国というイメージがあるが、どうやら実際はかなり違うようである。
4.その他
(1)人手を要するサービスの物価は高い
フランスでは、食料品などは日本に比較して安い。一方で、人手のかかったものは結構高いようである。昼の定食は、一般的なものでも日本円で1,500円から2,000円を要し、クリーニングはワイシャツ1枚が400円と日本の2倍から3倍である。
外食料金が高すぎるため、昼食にサンドイッチをかじっている人も結構いる。日本は一般に物価が高いと言われ、その通りとは思うが、都市部でのサラリーマンの日常生活を考えると、日本の方が住み易い部分もあるようである。
(2)労働者によるストが多い
こちらの労働者はストライキに訴えることが多い。また、そのストライキが中途半端なものではなく、徹底的である。
2000年春には、郵便局が1ヶ月間以上もストライキをした地域があった。この地域では、郵便物が配送されず、当地の企業が郵便局を裁判に訴えたりもした。
2000年秋には、石油価格の高騰に対する輸送業者等のストライキがあったが、フランス全土であちこちの道路を大型トラックが封鎖し、交通が数日間マヒした。精油所なども封鎖され、ガソリンの配送ができず、ガソリン・スタンドは営業停止となるばかりか、航空燃料がなくフライトがキャンセルされた航空便も出る事態となった。
また、忘れられないのは、小生が赴任して3日目に、パリ市内の地下鉄・バスが終日ストライキとなり、パリ市民はみんな徒歩か、ローラースケートで出勤する羽目になったことを記憶している。地下鉄・バスのストはしょっちゅうある。
労働者の権利が保障されることは重要であり、労働者がストライキに訴える手段が確保されることは必要であるが、日本人の目からすると“やりすぎ”で、交通・物流等が遮断されることによる社会的なデメリットの方が大きいように思えてならない。
Ⅲ 終わりに
フランスから日本に帰任する人のうち、10人に3人はフランスが好きになりもっと住みたいと感じ、10人に3人は二度とフランスには住みたくないと感じ、残りの4人はどちらでもよいと感じると言われている。なるほどと思う。自分もフランス人流になりきれれば、これほど住み易いところはないであろう。一方、謙譲の心を持つとか、時間厳守であるとか、日本のスタンダードを求める人にとっては、この地は我慢できないことになる。
日本にいると、現代でも欧州は憧れの地で、マナーも素晴らしく、先進的な地域というイメージがあるが、当たっている部分もあるものの、実際にこの地で生活してみるとプラスの面、マイナスの面様々であった。
単に工業製品の品質が優れているというのみならず、文化、伝統、社会習慣を含めて日本の方が優れていると思われる面は沢山ある。今後、我が国は経済大国としてだけではなく、1つの優秀な文化・伝統を有する国として国際的に認知され、かつ、尊敬を集めるようになりたいと思う今日この頃である。
3年間の長きにわたって小生の駐在員報告をご覧いただき、ありがとうございました。
(C)Copyright JEITA,2002
|