
【 2003年7月号 】
Ⅰ.欧州における日系IT製造業の状況
1.はじめに
今回は、日本貿易振興会(ジェトロ)が実施した「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態調査」を基に、欧州における日系IT製造業の状況について分析を行った。
当該調査は各国における日系製造業の経営動向等を把握することを目的に1983年から毎年実施されており、今回は第19回目となる。調査対象企業は西欧17か国(EU15か国及びノルウェー、スイス)、中東欧6か国(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、リトアニア)及びトルコにおいて、直接出資及び間接出資を含めて日本の親会社の出資比率が10%以上の企業であり、欧州又はそれ以外に進出している日系企業により設立された企業(孫企業)を含む。調査期間は2002年11〜12月、日系製造業986社のうち321社から回答を得ている。
当該調査は結果を21業種別に分類しているが、その中で「電気機械・電子機器」及び「電気・電子部品」を中心に取り扱うこととする。これら2業種(以下、「IT業種」)における在トルコ日系企業の回答はなく、また中東欧6か国の企業の回答も少ないため、西欧17か国の企業の回答データを中心に分析を行う。なお、全ての企業が全ての設問に回答したわけではないため、項目により企業数に変動がある。
2.進出動向と経営状況
西欧・中東欧に進出している日系製造業企業の数を、調査対象企業数ベースで5年前と比較すると、表1のようになる。西欧への進出は鈍化(IT業種ではむしろ減少)しているのに対し、中東欧への進出は大きく伸びている。
2002年末時点での進出企業数を業種別に見ると、輸送用機械部品が167社(全体の17.2%)で最も多く、次いで化学・石油製品が153社(同15.7%)、電気・電子部品が111社(同11.4%)となっている。IT業種は全体の約6分の1(17.5%)を占めている。
表1 西欧・中東欧に進出している日系製造業企業数
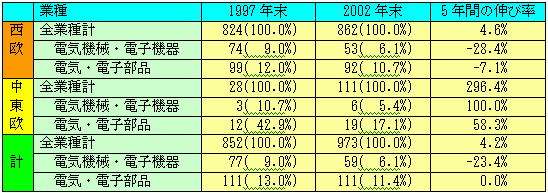
(備考)1.かっこ内は、全業種に占める当該業種の比率
2.97年の中東欧の数字は、ルーマニア及びリトアニアを含まない
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」、
「在欧日系企業(製造業)の経営実態−第14回実態調査報告−」(日本貿易振興会)
続いて、経営の現状と見通しに関して、営業利益の状況を表2に示す。
在西欧日系企業では赤字の割合は少なく、景気低迷の影響をあまり受けなかったことが分かる。他方、在中東欧企業では全業種平均で6割弱の企業が、また電気・電子部品では7割以上の企業が赤字となっている。表1から分かるように在中東欧の日系企業は操業から間もない企業が多いことや、欧州の景気低迷の影響を受けたことが考えられる。
また、2003年の営業利益については2002年よりも改善すると見込む企業が約半数、横這いと見込む企業が約4割弱となっており、企業は全般的に景気の先行きを緩やかな回復基調にあると見ている。
表2 営業利益の状況
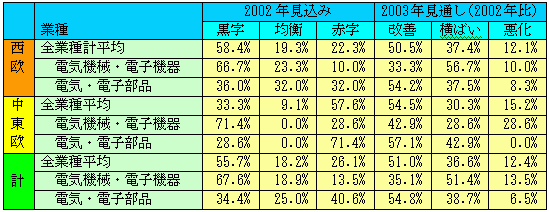
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
3.調達の状況
在西欧日系企業の原材料及び部品の現地調達率(金額ベース)を表3に示す。
全業種平均に比べ、IT業種では現地調達率がやや低い傾向にある。
表3 在西欧日系企業の原材料及び部品の現地調達率
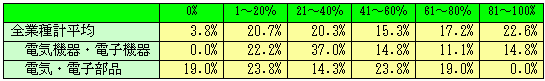
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
その理由として、IT業種ではアジアからの調達が多いことがあげられる。表4に在西欧日系企業の原材料及び部品の主要調達先を示す。全業種平均と比べ、IT業種では中国及びアジアからの調達が際だって大きく、これらの地域が在西欧日系企業に対しても原材料・部品の大きな供給センターとなっていることが分かる。
また、原材料及び部品の今後の調達方針を図5に示す。中国及び中東欧からの調達を拡大するとする企業の割合が多く、特に中国からの調達を縮小するとした企業が全くないことが目をひく。一方で、日本からの調達を縮小するとした企業は約4割に達しており、電気・電子部品では日本・中国を除いたアジアからの調達を縮小する企業の割合が高い。
ところで、進出国内での調達を縮小するとした企業が全業種平均で9.8%あった。その理由(複数回答)としては、高価格(89.5%)、品質の悪さ・不安定性(21.1%)が挙げられている。
表4 在西欧日系企業の原材料及び部品の主要調達先(複数回答)
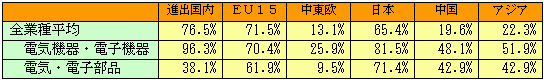
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
図5 在西欧日系企業の原材料及び部品の今後の調達方針
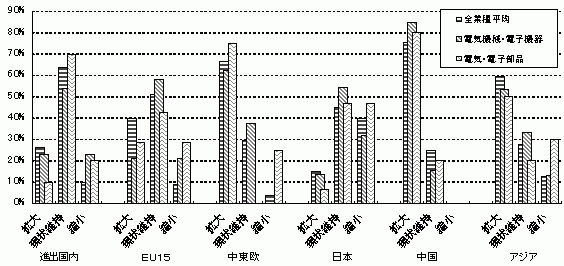
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
4.販売の状況
在西欧日系企業の販売先を表6に示す。全業種平均に比べ、IT業種ではEU15、中東欧及びロシア・CISを販売先とする企業が多い。
また、在西欧日系企業の販売の今後の方針を図7に示す。ロシア・CISでの販売を拡大するとした企業が多く、次いで中東欧、EU15となっている。在西欧日系企業が欧州・ロシア・CISを主要販売先としてとらえていることが伺える。
表6 在西欧日系企業の販売先(複数回答)
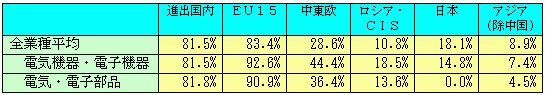
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
図7 在西欧日系企業の今後の販売方針
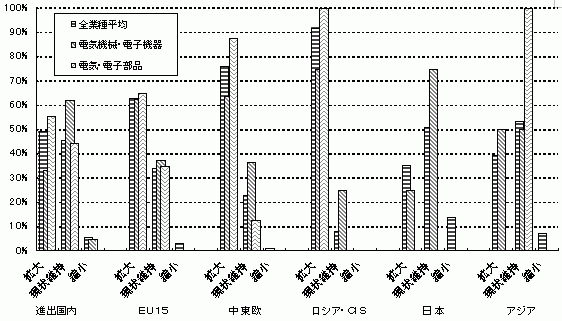
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
5.競合製品の状況
在西欧日系企業の販売市場での競合製品の製造国を表8に示す。全業種平均に比べ、IT業種では日本製、中国製及びアジア製の割合が高く、進出国製及び西欧製の割合が低くなっている。IT部品・製品の世界的な供給センターであるアジアとの競争が、欧州に持ち込まれているものと考えられる。
表8 在西欧日系企業の販売市場での競合製品の製造国(複数回答)
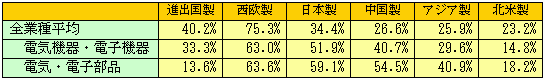
(備考)アジアは日本及び中国を含まない
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
6.EU拡大のメリット及びデメリット
在西欧日系企業及び在中東欧日系企業がEU拡大をメリットと見ているか、デメリットと見ているかを図9に示す。全業種平均でみると、在西欧日系企業ではメリットが大きい又は影響なしとする企業が86.8%を占めるのに対し、在中東欧日系企業ではデメリットが大きいとする企業が42.4%に上っている。在中東欧IT業種では、デメリットが大きいとする企業が過半数となっている。
図9 EU拡大はメリットかデメリットか
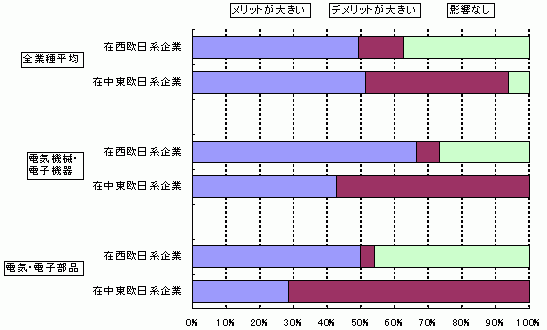
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
在西欧日系企業がEU拡大のメリットと考える点については、第1に販売市場の拡大(74.4%:全業種平均、複数回答)が挙げられ、次いで調達先の拡大(同33.3%)、生産拠点の活用(同21.7%)となっている。この傾向は、IT業種も同じである。一方、EU拡大のデメリットと考える点については、全業種平均とIT業種で傾向が異なっている(図10)。全業種平均では競争の激化が最も回答の多い項目であるのに対し、IT業種では生産拠点の優位性の低下が最も回答が多い。生産コストの低い中東欧が統一経済圏に入ってくることにより、競争の激化、生産拠点としての優位性の低下が生じるのではないかとの懸念と考えられる。
図10 在西欧日系企業がEU拡大のデメリットと考える点(複数回答)
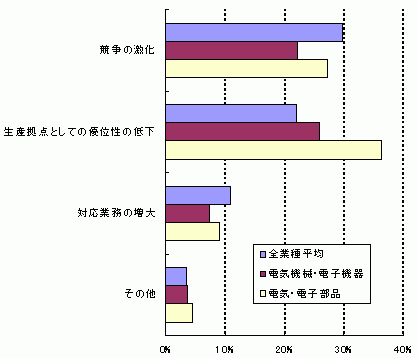
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
他方、在中東欧日系企業がEU拡大のメリットと考える点については、第1に国境措置の撤廃(79.3%:全業種平均、複数回答)が挙げられ、次いでマーケットの拡大(同48.3%)、経済法制度の調和、規格・基準制度の調和(同それぞれ41.4%)となっている。この傾向はIT業種も同じである。EU加盟により諸法制度の調和が図られ、人や物の移動がより自由になり、企業活動の自由度が増すことがメリットとなると考えられる。
逆に在中東欧日系企業がEU拡大のデメリットと考える点は図11のとおりである。投資優遇制度の廃止・縮小、人件費の上昇を挙げる企業が多く、この2つが中東欧に企業を置く大きな理由となっているものと考えられる。もっとも投資優遇制度の廃止・縮小については、先にメリットとして挙げられた諸法制度の調和と表裏一体のものであり、法制度全体が調和されたときに、企業にとってそれが全体でメリットになるかデメリットになるかの見極めは難しいように思われる。EUへの人材流入に対する懸念についても、ある面では人の移動が自由になることと表裏一体の問題である。環境規制の強化を挙げた企業の割合が少ないように小生には思えるが、中東欧への投資が比較的最近であったことを考えると、環境対策については既に相当程度先手を打っているということであるのかもしれない。
図11 在中東欧日系企業がEU拡大のデメリットと考える点(複数回答)
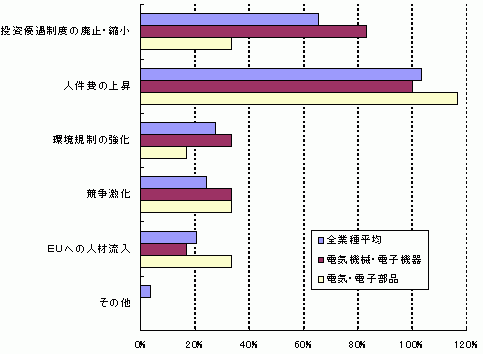
(出典)「在欧州・トルコ日系製造業の経営実態−2002年度調査−」(日本貿易振興会)
Ⅱ.産業動向
<仏:フランス・テレコム、ブロードバンド全国展開計画>
仏フランス・テレコムは6月10日、ブロードバンド・インターネットを全国に展開する計画を発表した。同計画の概要は以下のとおり。
- 2005年までに仏人口の90%以上がADSLを利用できるよう、DSLAM(デジタル加入者回線アクセス多重化装置)を現在の2.5倍以上に増やすとともに、新たに7,500kmの光ファイバーを敷設する
- 2003年9月に、衛星を使ったブロードバンドアクセスの提供を開始する(最大で下り2,048kbps、上り512kbps)
- 2003年夏に、ADSLの代替技術として衛星とWiFiを組み合わせたブロードバンドアクセスの実験を仏国内5地域で実施する
同社は、仏ブロードバンド接続人口は2002年末の140万人から2003年末には300万人を越えると見込んでいる。また、2003年初めのADSLの人口カバー率は74%であるとしている。
<仏:仏企業の情報セキュリティ対策の現状>
仏CLUSIF(フランス情報システム・セキュリティ・クラブ)は5月20日、「フランスにおける情報インシデントに関する統計調査」を発表した。この調査は従業員数10名以上の企業を対象としており、600社から回答があり、うち52%は従業員数10名から199名の企業である。
同調査によれば、仏企業の情報セキュリティ対策の現状は以下のとおりである。
- 情報セキュリティポリシー
36%の企業が策定済みだが、55%の企業が情報システムに大きく依存していることから見ると、不十分。業種別の情報セキュリティポリシー策定率は以下のとおり。
建設業 18%
商業 31%
工業 39%
サービス業 43%
通信業 87%
運輸業 24%
- 物理的セキュリティ対策の実施率
無停電電源 86%
防火設備 54%
重要区域への立ち入り制限 35%
盗難防止装置 35%
- 技術的セキュリティ対策の実施率
ウイルス対策ソフトウェア 92%
パスワード 89%
ファイアウォール 37%
IDS(侵入検知システム) 32%
- ウイルス対策ソフトウェアのパターン更新頻度
毎日 30%
週に1回 36%
月に1回 28%
月に1回未満 6%
- 暗号技術の利用率
ハードディスク上のデータの暗号化 67%
VPN(仮想プライベートネットワーク) 27%
データ交換の暗号化 26%
電子署名 24%
PKI(公開鍵基盤) 13%
- 情報セキュリティ・インシデント
60%の企業が情報セキュリティ・インシデントを経験していないとしている。残り40%の 企業が経験したインシデントは、以下のとおり。
ウイルス感染 26.3%
重要なサービスの喪失 22.6%
内部システムの停止 19.7%
使用ミス 14.4%
設計ミス 7.3%
盗難 6.7%
自然災害 5.2%
(C)Copyright JEITA,2003
|