3次元設計手順の課題解決と3DAモデル・DTPDによるものづくり現場活用
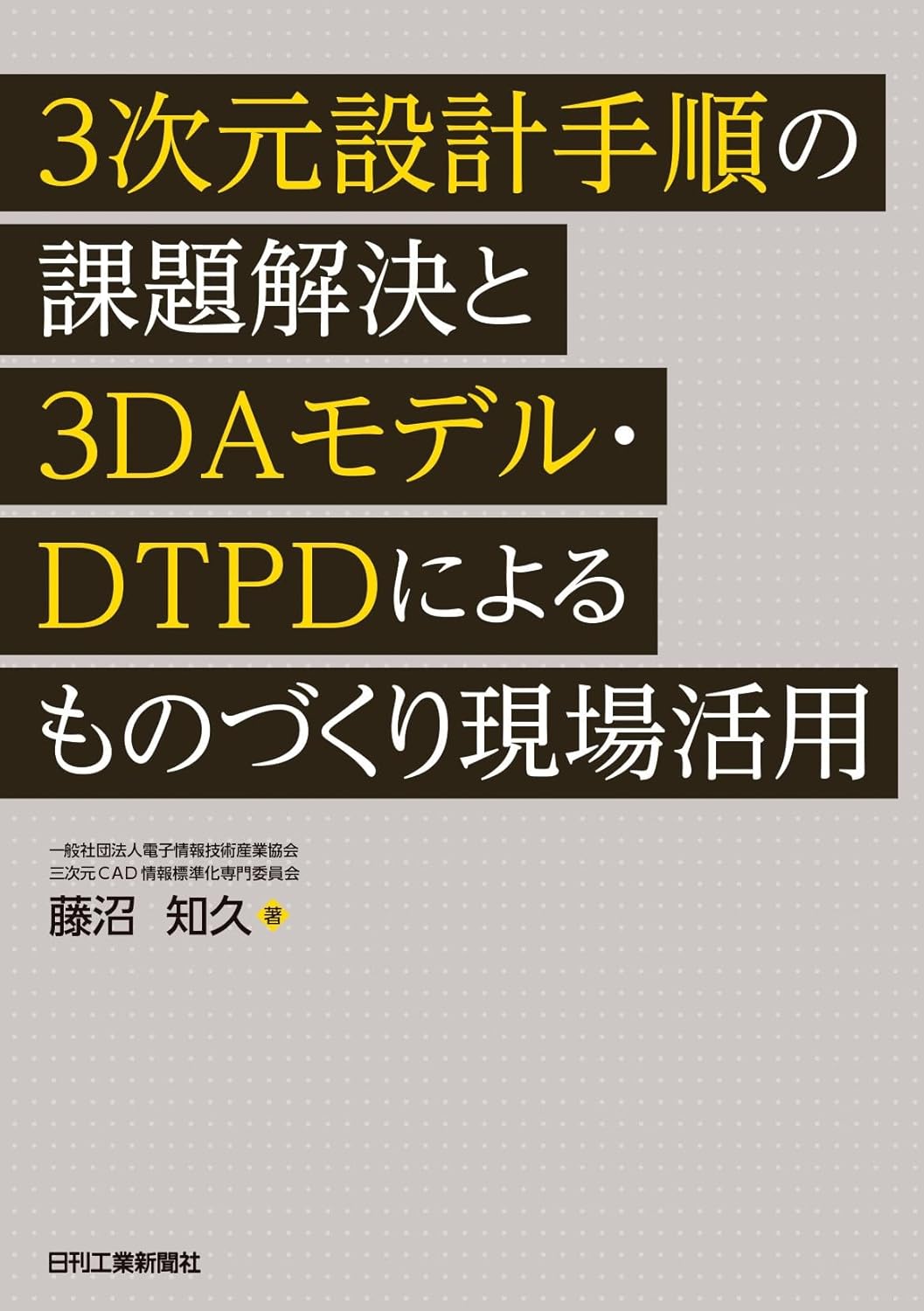
- ■体制:A5判 248頁(2024年11月発行)
■出版社:日刊工業新聞社
■定価(税込):3,520円
■ISBNコード:978-4-5260-8358-7
<ポイント>
〇 3D設計情報のモデリング(3DAモデル:3D製品情報付加モデル)とものづくり工程での活用方法(DTPD:デジタル製品技術文書情報)をまとめた実践書。
〇 3次元CAD設計の現状である3Dデータと2D図面を使った設計手順の課題を、デジタル家電機器と社会産業機器の開発事例のそれぞれで検証。
〇 3DAモデルとDTPDによる3D正運用への移行方法と今後の道筋を紹介。
〇 豊富な図面と細かな検証で丁寧に解説。
目次
- 序章
- 3DAモデルとDTPDに移行するために必要なこと
- 0.1
- 電機精密製品開発プロセスの課題と3次元CAD導入の狙い
- 0.2
- 日本と欧米の機械設計の違い:図面レスと製図レス
- 0.3
- 3DAモデルとDTPDと3D正運用とは
- 0.4
- 現場目線での3DAモデルとDTPDと3D正運用の導入
- 0.5
- 本書の構成と読み方
- 第1章
- 従来の「3次元CADとは」:製造現場での3Dデータ活用を前提としない「3次元CAD設計」の強みと課題を知る
- 1.1
- 3次元CADの強み:設計者から見た3次元CADの魅力
- 1.2
- 3次元CADの特徴:設計に役立つ機能
- 1.3
- グループ設計とは:設計効率化のポイント
- 1.4
- 基本方針:設計に3次元CADを導入するために
- 1.5
- キックオフ:3次元CAD設計の進め方
- 1.6
- 設計手法と運営ルール:3次元CAD設計の手順①
- 1.7
- 3Dデータ管理:3次元CAD設計の手順②
- 1.8
- 3Dデータと図面の出図:3次元CAD設計の手順③
- 1.9
- 3次元CADによるグループ設計:3次元CAD設計の秘訣①
- 1.10
- 3次元CAD設計の効率化:3次元CAD設計の秘訣②
- 1.11
- 量産製品「デジタル家電製品」の3次元CAD設計事例
- 1.12
- 受注製品「社会産業機器」の3次元CAD設計事例
- 1.13
- 3次元CAD設計の課題:設計事例から得られた教訓
- 第2章
- 3次元CAD設計から「3次元設計」へ:3Dデータを多面的に活かす
- 2.1
- 3次元CAD適用の目的の再確認:3次元CAD適用計画の立て直し
- 2.2
- 3次元CAD設計と3次元設計の違い:3Dデータの価値を全員で共有
- 2.3
- 3次元設計のスコープ:3Dデータを、どう使うか
- 2.4
- 製品開発プロセス分析:3Dデータを、まずどこで使うか
- 2.5
- 設計部門以外での3Dデータ活用:プロセス別の3Dデータ活用方法
- 2.6
- 3Dデータと図面の出図
- 2.7
- 設計手法と運営ルールの強化:全員で「3次元設計」をするために
- 2.8
- 量産製品「デジタル家電製品」の「3次元設計」導入事例
- 2.9
- 受注製品「社会産業機器」の「3次元設計」導入事例
- 2.10
- 「3次元設計」の課題:3Dデータを活用した2つの設計事例から得られた教訓
- コラム1.
- 効率的で、付加価値の高い設計工数の調査方法 3
- 第3章
- 3Dデータと図面を3DAモデルへ:設計情報のデジタル化と構造化
- 3.1
- 3D単独図の課題と解決:3D単独図の何が問題なのか
- 3.2
- 3DAモデルの定義:3DAモデルとは何か
- 3.3
- 3DAモデルの要件:3DAモデルは何ができるのか
- 3.4
- 3DAモデルのスキーマ:3DAモデルの作り方の原則
- 3.5
- 設計情報調査分析:3DAモデルをどう作る
- 3.6
- グラフィックPMIとセマンティックPMI: 設計情報をものづくりに伝えるために
- 3.7
- 要素間連携:3DAモデルを効率的に作るために
- 3.8
- ヒューマンリーダブルとマシンリーダブル:相反する要件の統合
- 3.9
- ものづくり工程に応じたマルチビュー:設計情報を見やすく表記
- 3.10
- 設計情報の管理システムとリンク:設計情報を効率よく運用するために
- 3.11
- 3DAモデルの検図:3DAモデルで設計することの旨味
- 3.12
- 3DAモデルの出図:3DAモデルで出図をするために必要なこと
- 3.13
- 設計手法と運営ルールの強化:全員で3DAモデルを使うために
- 3.14
- 量産製品「デジタル家電製品」の3DAモデル事例:具現化と効果
- 3.15
- 受注製品「社会産業機器」の3DAモデル事例:具現化と効果
- コラム2.
- 部品構成は、BOM(部品構成表)が先か、CADアセンブリが先か
- 第4章
- 3DAモデルからDTPDを作成し現場活用する:設計情報とものづくり情報の連携
- 4.1
- 設計と製造の連携の経緯:目指す姿と課題は何か
- 4.2
- DTPDの定義:DTPDとは
- 4.3
- DTPDの要件:DTPDは何ができるのか
- 4.4
- DTPDのスキーマ:DTPDの作り方の原則
- 4.5
- ものづくり情報調査分析:DTPDを、どう作る
- 4.6
- 3DAモデルの品質:3DAモデルをDTPDで直接使うための確認事項
- 4.7
- 3DAモデルからDTPDへのデータ変換:3DAモデルからDTPDを作る
- 4.8
- DTPDでセマンティックPMIの取扱い:設計情報をどう直接使うのか
- 4.9
- DTPDでデジタル連携:設計情報とものづくり情報を効率よく運用するために
- 4.10
- 属性情報のXML表現と運用:3Dではない関連情報のやり取り
- 4.11
- ヒューマンリーダブルとマシンリーダブル:相反する要件の統合
- 4.12
- 量産製品「デジタル家電製品」のDTPD事例:具現化と効果
- 4.13
- 受注製品「社会産業機器」のDTPD事例:具現化と効果
- コラム3.
- 異なる専門知識を持つ設計者と生産技術者が協力するための鍵
- 第5章
- 3DAモデルとDTPDの進化:実務上の課題を超えて、あるべき姿へ
- 5.1
- 3DAモデルとDTPDの課題:設計事例から得られた教訓
[1] 事前準備
[2] 技術ノウハウの流出
[3] 伝わる情報の限界(強力なインフラが必要不可欠)
[4] データの大容量化 - 5.2
- 3DAモデルとDTPDの展望:ものづくりDXに向けたステップ
[1] 産業界や国を超えた取り組みと標準化
[2] インフラの強化とクラウドコンピューティング
[3] 集約した設計情報/ものづくり情報を知識として幅広い活用
- コラム4.
- CAxからMBxへの移行
おわりに
・ 序章 3DAモデルとDTPDに移行するために必要なこと
電機精密製品産業界の特徴と課題を説明し、電機精密製品の3次元設計実践事例で考えられてきた三次元CAD情報を有効に活用する概念、3DAモデル、DTPD、3D正運用を紹介します。現場目線で、現在の図面主体の製品開発から、3DAモデルとDTPDと3D正運用に移行する方法のステップを定義しました。
・ 第1章 従来の「3次元CADとは」:製造現場での3Dデータ活用を前提としない
3次元CADの利点と特徴を再確認します。そして、現在の製造業で行われている3次元CAD設計(2D図面の出図)を紹介して、3次元CAD設計の課題を考えます。
・ 第2章 3次元CAD設計から「3次元設計」へ:3Dデータを多面的に活かす
3次元CAD設計から3次元設計(3Dデータの出図)へ移行する方法を紹介します。部品製造、生産組立、計測、電気電子設計、ソフトウェア設計での3Dデータ活用を説明し、3次元設計での課題を考えます。
・ 第3章 3Dデータと図面を3DAモデルへ:設計情報のデジタル化と構造化
3DAモデルがどのようなものか、定義と構成要素を説明します。2D図面の設計情報を3DAモデルに実装する方法と、設計で3DAモデルをどのように活用するか紹介します。その中で、3DAモデルの効果を考えます。
・ 第4章 3DAモデルからDTPDを作成し現場活用する:設計情報とものづくり情報の連携
DTPDがどのようなものか、定義と構成要素と要件を説明します。DTPDものづくり情報をデジタル化して、3DAモデルとものづくり情報を組み合わせてDTPDを作る方法と、3D正運用で設計情報とものづくり情報を取り扱う方法を紹介します。その中で、DTPDの効果を考えます。
・ 第5章 3DAモデルとDTPDの進化:実務上の課題を超えて、あるべき姿へ
3DAモデルとDTPDの課題を説明し、課題解決につながる展望を説明します。
3DAモデル(3次元CADデータ)の使い方とDTPDへの展開
-24の3DAおよびDTPDの設計開発プロセス(ユースケース)を体系化
そこで、三次元CAD情報標準化専門委員会では、電機精密製品設計の事例を、機械設計者・技術管理者の立場で、調査・分析して、設計情報のデジタルデータ化の方法をまとめて3DAモデル(3DAnnotated Models:3D製品情報付加モデル)として定義した。電機精密製品開発の事例を、各工程の専門家の立場で、調査・分析をして、3DAモデルの活用方法と各工程で使われるDTPD(Digital Technical Product Documentation:デジタル製品技術文書情報)の作成と活用方法をまとめました。
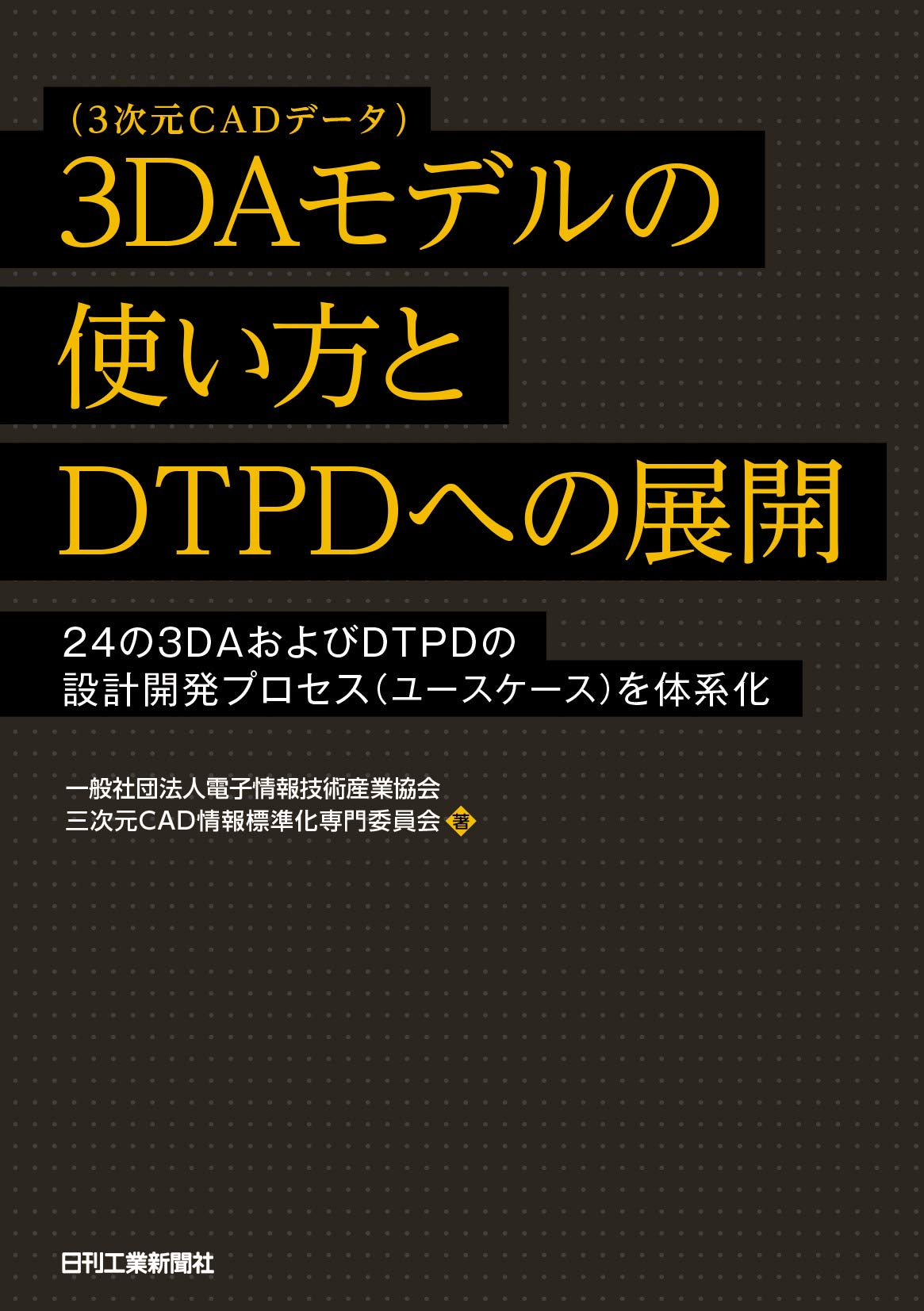
- ■体裁:A5判 272頁(2021年1月発行)
■出版社:日刊工業新聞社
■定価(税込):2,860円
■ISBNコード:978-4-526-08104-0
<ポイント>
〇 3D設計情報のモデリング(3DAモデル:3D製品情報付加モデル)とものづくり工程での活用方法(DTPD:デジタル製品技術文書情報)をまとめた実践書。
〇 電機精密量産製品の標準的な製品開発プロセスを24ケースに分けて体系化。
〇 三次元CAD情報標準化専門委員会会員各社の電機精密製品の3次元設計実践事例を収集分析。
〇 製造業で汎用の3次元CAD、CAM、CATなどを使った具体的なユースケースで、すぐに適用できる。
目次
はじめに
- 第1章
- 3次元設計における基本的な考え方
- 1.1.
- 電機精密製品産業界の課題と3次元CAD導入経緯
- 1.2.
- 3DAモデルとDTPD
- 1.3.
- 日本と欧米の機械設計の違い、図面レスと製図レス
- 1.4.
- 設計情報伝達から考えた3D正運用の定義
- 1.5.
- 電機精密製品産業界の標準的な製品開発プロセス
- 1.6.
- 標準的な製品開発プロセスでの3DAモデルの活用
- 第2章
- 3次元設計の国際標準化動向
- 第3章
- 3DAモデルによる3次元設計
- 3.1.
- 3DAモデルの定義とスキーマ
- 3.2.
- 3DAモデルの3次元設計手順(3DAモデルへの設計情報の作り込み)
- 3.3.
- 板金部品
- 3.4.
- 組立品
- 3.5.
- 樹脂成形部品
- 第4章
- 3DAモデルを利用したDTPDの作成
- 4.1.
- DTPDの定義とスキーマ
- 4.2.
- 板金加工
- 4.3.
- 組立
- 4.4.
- 金型加工・樹脂成形
- 第5章
- DTPDの作成と運用
- 5.1.
- 機械設計→検図
- 5.2.
- 機械設計→DR(デザインレビュー)
- 5.3.
- 機械設計→電気設計
- 5.4.
- 機械設計→ソフトウェア設計
- 5.5.
- 機械設計→機械CAE
- 5.6.
- 機械設計→公差解析
- 5.7.
- 機械設計→生産製造CAE
- 5.8.
- CADデータ管理(設計仕掛り)
- 5.9.
- CADデータ管理(出図)
- 5.10.
- 機械設計→見積り
- 5.11.
- 機械設計→発注
- 5.12.
- 機械設計→製造(金型加工・樹脂成形)
- 5.13.
- 機械設計→製造(板金加工)
- 5.14.
- 機械設計→製造(機械加工)
- 5.15.
- 機械設計→部品測定
- 5.16.
- 機械設計→生産管理
- 5.17.
- 機械設計→生産・組立
- 5.18.
- 機械設計→治具
- 5.19.
- 機械設計→検査(受入検査)
- 5.20.
- 機械設計→物流(梱包)
- 5.21.
- 機械設計→保守
- 第6章
- 新しいものづくりへの展開
- 6.1.
- 電機精密製品産業界の多様化
- 6.2.
- 製造プラットフォーム
- 6.3.
- デジタルツイン
- 6.4.
- コトビジネスでの3DAモデルとDTPDの役割と効果
おわりに:ものづくりのデジタルトランスフォーメーション(DX)
- コラム1
- 3次元CADの習得
- コラム2
- 様々な3Dデータの利用
- コラム3
- 幾何公差と3Dモデル
- コラム4
- デジタル連携
- コラム5
- 3Dモデルの設計変更
- コラム6
- テレワークと設計開発業務
・ 第1章 3次元設計における基本的な考え方
電機精密製品産業界の特徴と課題を説明し、電機精密製品の3次元設計実践事例で考えられてきた三次元CAD情報を有効に活用する概念、3DAモデル、DTPD、3D正運用を紹介します。3D正運用はCADデータに限定した設計情報の技術的なやり取りから製品開発の実業務に拡大した時に、3DAモデルとDTPDの運用と課題を検討したものです。
・ 第2章 3次元設計の国際標準化動向
3DAモデルとDTPDが電機精密製品産業界だけでなく他の産業界、日本だけでなく世界に広く通用するために、3次元設計の国際標準化動向と海外製造業での3次元設計への取り組みを説明します。
・ 第3章 3DAモデルによる3次元設計
3次元設計における完全にデジタル化した設計情報データ群の3DAモデルがどのようなものか、三次元CAD情報標準化専門委員会会員会社が実際に使っている汎用的な3次元CADを使って、板金部品、組立品、樹脂部品の3次元設計手順を通して具体的に説明します。
・ 第4章 3DAモデルを利用したDTPDの作成
3DAモデルを利用して作成したものづくり工程情報群のDTPDがどのようなものか、三次元CAD情報標準化専門委員会会員会社が実際に使っている汎用的なCAM、CAT、デジタルマニュファクチャリングツールを使って、板金加工、製品組立、金型加工・樹脂成形のDTPDの作成と活用を通して具体的に説明します。
・ 第5章 DTPDの作成と運用
3Dモデルだけでなく様々なものづくりドキュメントを含めて、3DAモデルとDTPDの3D正運用がどのようなものか、電機精密製品の標準的な製品開発における21プロセスを通して説明します。
・ 第6章 新しいものづくりへの展開
最後に、電機精密製品産業界で起きている新しいものづくり(製造プラットフォーム、デジタルツイン、コトビジネス)に、3DAモデルとDTPDを適用して「ものづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)」に結び付けています。
